養育費が受け取れる年齢は何歳まで?支払い期間の延長や増額はできるのか?年齢が養育費に及ぼす影響を徹底検証! (original) (raw)
養育費の取り決めで重要なのが金額と支払い期間です。

いくらもらえるのかが一番気になるところでしょうが、何歳まで受け取れるのか、増額できるのかも重要なポイントになってきます。
大学進学を想定している母親も多いことでしょう。
その時にも対応できるように、支払い期間と増額については、しっかり話し合わなければなりません。

年齢を重ねるごとに必要な養育費が変わることを念頭に置いて、養育費の取り決めをする必要があるというわけです。
そこで今回は支払い期間の変更ができるのか、年齢に伴い養育費の増額はできるのかを徹底検証していきます。
あなたが心配しているポイントを突いた内容になっているので、最後まで目を通して、参考にしてください。
目次
- 養育費を受け取れる年齢は何歳まで
- 子供の年齢が及ぼす養育費相場への影響
- 養育費の支払い条件を取り決める方法とその手順
- 大学進学時の支払い期間延長と養育費増額の可能性
- 再婚が及ぼす養育費への影響
- まとめ
養育費を受け取れる年齢は何歳まで
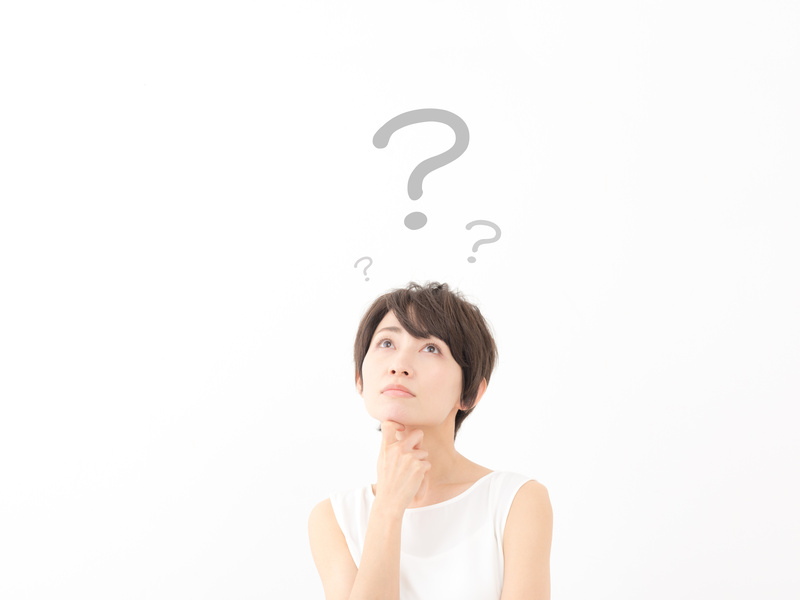
基本的な養育費の支払い期間は、成年年齢となる20歳までです。

しかし、これは法律で20歳と定められているわけではありません。
子供に対する親の監護権が消滅するのが20歳であり、親の扶養義務がなくなることから、20歳と解釈されているだけです。
詳細には、養育費の支払い期間は子供が経済的・社会的に自立していない未成熟子の間とされているので、必ずしも20歳が妥当であるとは言えません。

下記のケースでは20歳であっても、経済的・社会的に自立していない未成熟子と判断できるからです。
- 大学に進学した
- 障害があって社会生活に順応できない
そのため、支払い期間は変更することが可能です。

支払い義務者と受給権利者の双方が合意さえすれば、無条件で支払い期間を短縮・延長することができます。
双方が合意しない場合には、裁判所に裁決を求めることになるでしょう。

そこでまずは、基本的な養育費の支払い期間に関する考え方について解説します。
変更を希望するにしても基本的な情報を把握していないでは、相手とまともな交渉をすることはできません。
しっかりと目を通すようにしてください。
民法改正に伴う成年年齢引き下げによる影響

民法改正に伴い、2022年から成年年齢が18歳に引き下げられることが決まりました。
成年年齢が18歳に引き下げられるなら、養育費の支払い期間も18歳に短縮されるべきだという声も多いので、心配している人も多いのではないでしょうか。

しかし、民法改正による成年年齢引き下げにより、養育費の支払い期間が短縮されることはありません。
下記の法務省HPでも、「成年年齢の引下げに伴う養育費の取決めへの影響について」と題して、民法改正が養育費の支払い期間に影響しないと言及しています。
「また、養育費は、子が未成熟であって経済的に自立することを期待することができない場合に支払われるものなので、子が成年に達したとしても、経済的に未成熟である場合には、養育費を支払う義務を負うことになります。このため、成年年齢が引き下げられたからといって、養育費の支払期間が当然に「18歳に達するまで」ということになるわけではありません。」
参照先:法務省HP
また、現在20歳までと取り決めて養育費を支払っている人も、その影響を受けることはありません。
「平成30年6月13日に民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容とする民法の一部を改正する法律が成立したことに伴い、このような取決めがどうなるか心配になるかもしれませんが、取決めがされた時点では成年年齢が20歳であったことからしますと、成年年齢が引き下げられたとしても、従前どおり20歳まで養育費の支払義務を負うことになると考えられます。」
参照先:法務省HP
成年年齢が18歳となっても、基本的な養育費の支払い期間は変わりないと考えておけばいいでしょう。
具体的な養育費の支払い期間は20歳のいつまで
基本的に養育費の支払い期間は20歳までとされていますが、下記のどちらなのかを気にしている人は多いのではないでしょうか。
- 20歳の誕生日の前日まで
- 20歳の誕生日を迎える年度内
これは先に話した養育費の支払い期間を20歳とする法的根拠を考慮すれば、20歳の誕生日を迎えた時点で、養育費の支払い期間は終了すると判断するのが妥当です。

そのため、一般的には子供が20歳になった時点が、養育費の支払いが終了する基準時点とされています。
ですが、大学進学を見据えて、支払い期間を大学卒業時に変更することは可能です。
支払い義務者と受給権利者の合意、もしくは裁判所による採決が必要ですが、延長できる可能性があることは覚えておきましょう。
18歳で就職した場合の支払い期間
先に話したように、養育費の支払い期間は子供が経済的・社会的に自立していない未成熟子の間とされています。

となれば子供が20歳を迎えていなくても、高校卒業と同時に就職した場合、養育費の支払い期間を短縮できるのではと考える人もいるでしょう。
就職して自分の力で生活できるなら、経済的・社会的に自立していると考えられます。
となれば、こう考える人がいても不思議ではありません。

事実、子供が高校卒業後に就職した場合、養育費の支払い期間を、18歳の3月までに短縮する取り決めをする人も少なくないのです。
よって、このケースでは支払い期間を短縮できる可能性はあるでしょう。
しかし、これは養育費の取り決めで、支払い義務者から支払い期間の短縮要望があった場合です。
あなたから進言する必要はありません。
また短縮の可否もあなたが同意しなければ、裁決を裁判所に委ねることになります。

短縮できる可能性はありますが、絶対という保証はないのです。
支払い義務者から要望があった場合は、必ず応じる必要はないと覚えておくといいでしょう。
断るかどうかはあなたの考え1つというわけです。

以上の様に養育費の支払い期間は、延長・短縮できる可能性はあります。
しかし、当事者同士の話し合いでまとまらず、裁判所に裁決を委ねた場合は、どうなるかは断言できません。
延長・短縮を求める理由や両親の条件など、様々な事情が考慮されるため、裁判官の判決が必ずしも同じではないからです。
これについては下記の記事で詳しく解説しています。
更に詳しい情報が知りたい人は、この記事を覗いてみましょう。
ーーー
子供の年齢が及ぼす養育費相場への影響

養育費相場を決定する要因の1つが子供の年齢です。

基本的には、子供の年齢が高いほど、受け取れる養育費相場は高くなるとされています。
年齢が高いほど生活指数も高くなるので、これは当然のことでしょう。
そこで、ここでは子供の年齢が、養育費相場にどう影響するのかを見ていきます。
養育費の増額を希望している人は、しっかりと目を通すようにしてください。
年齢が上がれば受け取れる養育費も上がる!
今言ったように、子供の年齢が高いほど、受け取れる養育費相場は高くなります。

しかし、年齢を重ねるごとに、受け取る養育費が高くなるわけではありません。
養育費は取り決めた金額が、支払い期間終了時まで変わらず支払われます。
月額5万円と決めたならば、支払い期間終了まで受け取れる養育費は月額5万円だけです。

年齢が上がったからといって、受け取る養育費が上がるわけではありません。
養育費取り決め時の子供年齢が高ければ、それが養育費相場に考慮され、取り決め時に高めの養育費を受け取れる可能性があるというだけです。
この点は誤解しないように、よく理解しておきましょう。
子供の年齢が養育費に与える影響はそれほど大きくない!
養育費は子供の年齢と共に、下記の2つを考慮して決定されます。
- 夫婦それぞれの年収
- 子供の人数
ここで理解しておいてもらいたいのは、子供の年齢と人数が養育費相場に及ぼす影響です。
実は、残り2つの子供の年齢と人数は、それほど大きく影響しません。
養育費相場に大きな影響を及ぼすのは、支払い義務者の年収です。

子供の年齢が高いからといって、必ずしも高い養育費がもらえるわけではありません。
養育費相場を算出する際、子供の年齢は下記の2つに区分して計算されます。
- 14歳以下
- 15歳以上
かなり大きな幅で区分されていますよね。

そのため、子供の年齢が養育費に全く影響しないというケースも出てくるのです。
まずはあなたが受け取れる養育費に、子供の年齢がどう影響しているかの確認が必要でしょう。
下記の記事では「年収・年齢・人数別」に分けて、様々なケースのシミュレーションをして、養育費相場を紹介しています。
後述する養育費の増額を希望するにしても、受け取れる養育費相場は把握しておく必要があります。
是非この記事を覗いて、あなたが受け取れる養育費相場を確認してみましょう。
年齢が上がり教育費が増えた!この時に養育費を増額できる可能性
残念ではありますが、養育費に含まれる教育費は公立の小・中・高校に通うことを前提として算出されています。

そのため、下記の費用は養育費に反映されていません。
- 進学塾に通う費用
- 家庭教師を雇う費用
- 習い事に掛かる費用
子供が成長するにつれ、受け取っている養育費だけで教育費を賄いきれないのは当然の事なのです。

となれば、あなたは当然これら費用を請求したいと考えるでしょう。
しかし、この養育費の増額は認められる可能性が低いのが実情です。
もちろん、相手がすんなり同意してくれれば問題はありません。

ですが裁判所に養育費増額調停を申し立てた時は、認められる可能性は低くなります。
特に進学塾や家庭教師、習い事の費用は、養育費の増額事由として認められていません。
これらは親権者が任意で通わせていると判断されるからです。

裁判所としては、負担できないなら諦めてくださいというスタンスになります。
これら教育費を求めて増額を希望しても、相手が同意しない限り、増額できる可能性は薄いでしょう。
この養育費増額に関しては、下記の記事で更に詳しく解説しています。
増額される可能性がある条件も紹介しているので、ぜひ目を通して増額の可能性を探ってみましょう。
養育費の支払い条件を取り決める方法とその手順

養育費の請求時には最低でも下記条件を取り決めなければなりません。
- 支払い額
- 支払い期間
- 支払い期日
- 支払い方法
支払い期日や方法は任意となりますが、残り2つは下記条件が基本ラインとなってくるでしょう。
- 支払い額:養育費相場
- 支払い期間:20歳まで
そのため支払い額の増額、支払い期間の延長を求める際は、正当な請求事由を挙げて、相手に納得してもらう必要があります。

できるならば、当事者同士の話し合いで決着をつけるのがベストです。
ここまで話した通り、養育費の増額や支払い期間の延長を裁判所の裁決に委ねた場合、認められない可能性が高くなります。
それを避けるためにも、話し合いで相手に合意してもらう必要があるのです。

離婚して時間がたてば、相手も子供に対する愛情が薄れがちになります。
離婚時であれば子供への愛情や愛着に変化がないため、「子供のために絶対に必要だ!」とアピールすれば、合意してくれる可能性も高いでしょう。
合意に至らなければ、裁判所へ養育費請求を申し立て、裁判所で養育費の取り決めることになります。
そうなる可能性は否定できません。

その時に備えて、申し立て方法とその流れは理解しておくべきです。
この方法と流れについては注意点と共に、下記の記事で分かりやすく解説しています。
話し合いで決着がつかなかった時の対処法として、頭に入れておくようにしてください。
話し合いで決着がついた時は公正証書の作成を忘れずに!

また、話し合いで条件合意が得られた場合は、必ず取り決め事項を公正証書として作成してください。
養育費を受け取るようになった後、一番心配しなければならないのが未払いへの対応です。
あなたもニュース等で養育費の未払い問題が深刻化していることは理解していることでしょう。

あなたが未払いにならないとは限りません。
その時、最終的な回収手段となるのが差し押さえです。

しかし、この差し押さえは誰でもできるわけではありません。
裁判所に養育費回収を求めて、差し押さえの申し立てをするには、下記3つの申立要件を満たす必要があるからです。
- 債権名義の取得
- 差し押さえる相手の現住所の把握
- 差し押さえる財産情報の把握
この3つの申立要件を満たさない限り、未払いとなっても差し押さえることはできません。

そしてこの中で、最も重要なのが債権名義です。
債権名義とは差し押さえできる権利があることを、公文書として証明した書類です。
この債権名義を取得していなければ、差し押さえする権利がなく、申し立てすらできません。
となれば債権名義の取得がいかに重要かは、理解してもらえるでしょう。
債権名義となる公正証書の作成方法

債権名義にはいくつかの書類がありますが、公正証書もその1つです。
養育費の取決め時に、協議書を執行認諾文言付き公正証書として作成しておけば、申立要件の「債権名義の取得」をクリアすることができます。
養育費取り決めを裁判所裁決に委ねた場合は、自動的に債権名義が取得可能です。

しかし、裁判所を介さず、当事者同士の話し合いで取り決めた場合は、この公正証書を作成するしか、債権名義を取得することはできません。
もちろん取得方法はありますが、それには時間と労力、費用が掛かります。
そのため、取り決め時に公正証書を作成した方が簡単なのです。

話し合いで決着がついた際は、必ず執行認諾文言付き公正証書を作成するようにしてください。
公正証書の作成方法は、下記の記事で分かりやすく紹介しています。
必ず目を通して、公正証書の作成方法を覚えるようにしてください。
大学進学時の支払い期間延長と養育費増額の可能性
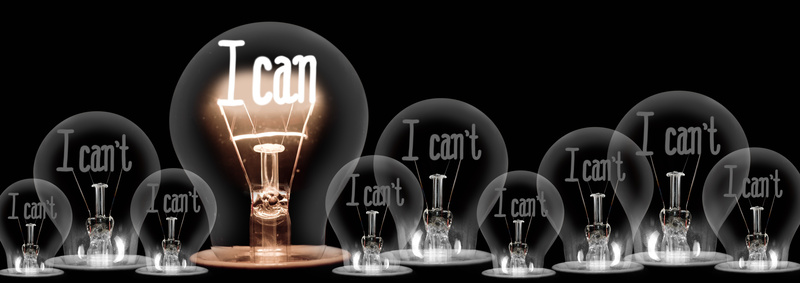
先にも話した通り、大学進学による支払い期間延長と養育費増額が裁判所で認められる保証はありません。

一番確実なのは、相手と話し合って同意してもらう方法になるでしょう。
しかし、大学進学となれば進学費用だけの問題ではありません。
進学に向けた受験勉強に伴う費用も必要になります。
大学進学に掛かる費用を全て把握した上で、相手に要求しなければならないのです。

また、裁判所に裁決を委ね、請求が認められなかった時の対応も考えておかなければなりません。
これら情報は下記の記事で詳しく解説しています。
ぜひ目を通して、必要な情報を入手してください。
大学進学に伴う養育費の支払い期間延長と増額の裁判所判例
裁判所に大学進学に伴う、養育費の支払い期間延長と増額を認めてもらうのは難しいと言いました。
しかし、全く可能性がないわけではありません。
近年は大学進学率が50%を超えたことで、大学に進学するのは一般的だとする風潮が出てきています。

それによって、養育費の支払い期間延長と増額を認める傾向が出てきたのです。
そこで裁判所がどのようなケースで、養育費の支払い期間延長と増額を認めたかを判例から見ていくことにします。
あなたの状況と比較して、裁判所に認められる可能性を探ってみましょう。
大阪高等裁判所・平成27年判例
これは私立大学に進学した子供の養育費増額と支払い期間延長を求めて、その子供が申し立てをした事件判例です。
裁判所の判決は下記の通りで、養育費増額と支払い期間延長が認められました。
- 22歳まで養育費の支払い期間の延長
- 大学進学費用を両親とその子供が3分の1づつ負担
この決定が下された理由は下記の通りです。
- 高校進学時に大学進学を目指していたことを両親が認識していた
- 夫婦収入での学費負担は不可能であり、大学進学時には子供が奨学金、あるいはアルバイトすることが前提認識だった
この決定は普遍的な決定基準とな異なり、様々な事情を考慮した決定事例と言えるでしょう。
広島高等裁判所・昭和50年判例
これは大学医学部への進学を果たした子供が、養育費増額と支払い期間延長を求めて申し立てをした事件判例です。
裁判所は下記の通り、養育費増額と支払い期間延長を認めました。
- 大学医学部を卒業して独り立ちするまで養育費の支払い期間を延長
- 大学進学費用を支払い期間終了時まで分担費用として認める
この決定が下された理由は下記の通りです。
- 父親の職業が医師である
- 父親に経済力がある
- 子供が医学部に進学することを父親が望んでいた
この決定は先ほどとは異なり、普遍的な決定基準による判決と言えます。
父親の職業・経済力・社会的地位を考慮した上で、扶養義務となる生活保持義務に照らし合わせ、子供が大学進学をして医学教育を受けさせることが相応だと判断された結果です。
東京家庭裁判所・昭和50年判例
これは大学進学に伴い、母親が父親に対して、養育費増額と支払い期間延長を求めて申し立てをした事件判例です。
裁判所は養育費増額と支払い期間延長を認めました。

ここまでにも触れましたが、近年は大学進学が当然の事として受け入れる傾向が強くなっています。
この判決はまさに大学進学が一般的な傾向であり、家庭環境によっては大学進学が当然であるとした判例です。
昭和50年当時でも、こうした判決が下されているのですから、2020年現在であれば可能性は更に高くなるでしょう。
そんな期待を覚える判例ですね。
東京高等裁判所・平成12年判例
これは子供が大学進学を果たした際に母親が、父親に対して下記の養育費増額と支払い期間延長を求めて申し立てをした事件判例です。
- 進学費用と未払い養育費137万6,000円の一括払い
- 20歳になるまでの支払い期間延長(*取り決めでは18歳まで)
原審では親の扶養義務は成年年齢までと判断し、成年年齢以降の養育費支払いが却下されました。

しかし、抗告審では原審の判断を不当とし、差し戻されることになったのです。
手元の資料上では最終判断は下されていませんが、実質的には大学卒業時までの扶養義務が認められたと言えます。
これは養育費の支払い期間は20歳まで、そして親の扶養義務の有無や判断基準を示した判例と言えるでしょう。
大阪高等裁判所・平成21年判例
これは子供が大学進学を果たしたことで、母親が父親に対して、養育費増額と支払い期間延長を求めて申し立てをした事件判例です。

裁判所は下記の通り、養育費増額と支払い期間延長を認めました。
- 大学卒業するまでの養育費を両親が分担する
この決定が下された理由は下記の通りです。
- 両親とその兄が大学に進学している
- 父親は子供の進学に熱心である
- 子供が中高一貫の進学校を卒業している
この決定も普遍的な決定基準による判決と言えます。
両親だけでなく、その兄も大学に進学している。
そのため生活保持義務に照らし合わせば、両親と同等の教育を受けさせることが相応だと判断された結果ですね。
再婚が及ぼす養育費への影響

それでは最後に離婚後の再婚が、養育費にどう影響するのかについて解説します。
離婚後の再婚はどちらにも可能性があることです。
特にあなたの再婚は、子供にとってもいい影響を及ぼすことになるでしょう。

しかし、残念ながら再婚は養育費が減額・免除される可能性が出てきます。
その理由は再婚が養育費減額の請求事由になるからです。
これはどちらが再婚したとしても変わりません。

特に女性の再婚では注意が必要で、大幅減額・免除となる可能性すら出て出てきます。
再婚後、養育費をが必要ないなら、気にする必要はありません。
ですが、再婚後も養育費が必要な人にとっては深刻な問題です。

養育費の減額幅と免除される可能性は、再婚時の条件によって異なります。
そのため、お互いの再婚でどれくらいの減額されるのか、免除となる可能性があるのかは、しっかりと把握しておく必要があるでしょう。
お互いの再婚が養育費にどう影響するのかは、下記の記事で詳しく解説しています。
必ず記事に目を通して、再婚によって養育費がどうなるのかを、しっかり頭に入れておきましょう。
ーーー
まとめ
今回は支払い期間の変更ができるのか、年齢に伴い養育費の増額はできるのかを検証しました。

支払い期間の延長と養育費の増額を請求することは可能です。

しかし、その請求が必ずしも認められるかは、断言することはできません。
当事者同士で合意できれば話は別ですが、裁判所に裁決を委ねると、簡単ではないのが実情です。
請求はするべきですが、認められなかった場合を考慮して、他の方法を模索する必要があるでしょう。
また下記記事では、今回の記事情報をさらに詳細に紹介しています。
もっと詳しい情報が知りたいという人は、覗いてみるといいでしょう。