【養育費の取り決め方】これを読めば完璧!金額相場・支払い期間・支払い方法の決め方を分かりやすく解説!! (original) (raw)
養育費は支払い金額だけを決めればいいわけではありません。
他にも下記の様に、取り決めに欠かせない重要事項がいくつもあります。
- 支払い期間
- 支払い方法
- 書面化方法
また、養育費を受け取った後に想定される下記問題にも、対処する必要があるのです。
- 養育費の増額
- 支払い期間の延長
- 再婚時の養育費変更
- 養育費の不払い
そこで今回はこれら養育費の取り決め方を徹底解説していきます。
最後まで記事に目を通してもらえば、あなたは安心して養育費の取り決めに取り掛かれるようになるでしょう。
目次
- 養育費相場を知って適正な養育費を請求しよう!
- 養育費の受け取りが可能な期間
- 養育費の支払い方法は分割じゃなきゃダメ!?
- 養育費の取り決め時には公正証書の作成が必須!
- 養育費の取り決めは離婚後でも問題なし!
- 離婚後でも養育費の増額や支払い期間の延長は請求できる!
- お互いの再婚は養育費に影響する!
- 養育費が不払いになった時の対処方法
- まとめ
養育費相場を知って適正な養育費を請求しよう!


基本的に養育費は当事者同士が話し合って決めることです。
しかし、支払う側はできるだけ金額を抑えようとしますし、受け取る側はできるだけ多く請求しようとします。
そのため、合意にいたらず、裁判所に調停申立するケースも少なくありません。
調停が不成立になれば、審判になるため、養育費の取り決めには時間と労力、そして費用が必要になってしまいます。

そこで、極力話し合いで取り決めがまとまるために、まず把握しておかなければならないのが養育費相場です。
あなたが請求できる養育費相場を把握しておけば、金額で揉めることもありませんし、請求金額の正当性を実証することもできます。
請求できる養育費相場の確認方法

養育費相場の確認方法として、最もおすすめなのは「養育費算定表」です。
養育費算定表は裁判所が公開している養育費の相場データで、裁判所が養育費を決定する際の基本データとして使用されています。

そのため、現状では最も実効性と信頼性の高い相場データと言えるでしょう。
そこでおすすめしたいのが、養育費計算機ツールです。
今は、この養育費算定表の相場データを基に、WEB上で養育費計算機ツールがいくつも公開されています。
データの確実性が実証されているものであれば、養育費算定表よりも養育費計算機ツールの方が使い勝手はいいでしょう。

下記データを入力すれば、数秒であなたが請求できる養育費データが確認できます。
- 夫婦それぞれの年収
- 子供の人数
- 子供の年齢

しかし、残念ながら養育費算定表や養育費計算機ツールは、下記に該当する人は利用できません。
- 子供の人数が4人以上
- 夫婦それぞれが子供を引き取っている

この場合、養育費算定表の相場データ計算でも用いられている標準計算式を使って、自ら計算するしかありません。
少々面倒ですが、この方法しかないのであきらめて計算するしかないでしょう。
これら養育費相場を確認する方法は、下記の記事で詳しく解説しています。
この記事を覗いて養育費相場の確認方法を学んで、あなたが請求できる養育費相場を確かめてみましょう。
ーーー
養育費相場は人によって違う!
養育費相場は、下記3つの条件を基に算出されています。
- 夫婦それぞれの年収
- 子供の人数
- 子供の年齢
そのため、個々で条件が異なるため、人によって請求できる養育費相場は違ってくるのです。

「なんであの人と私の養育費はこんなにも違うのだろう・・・。」
こう思ったことがあるなら、あなたとその人は上記3つの条件のどれかに違いがあるからでしょう。
これら3つの条件が異なると、養育費相場にどれくらいの影響が出るのかは、下記の記事で条件別に分けてシミュレーションしています。
この記事を見てもらえば、あなたが感じている疑問や不安は解消できるでしょう。
ぜひ目を通して、3つの条件が及ぼす影響を確認してください。
養育費の受け取りが可能な期間

原則、養育費の支払い期間は子供が成年年齢である20歳になるまでです。

20歳になった時点で、親に課せられた養育費の支払い義務は終了します。
これは法的に成人として認められ、親の監護権が消滅するからです。
しかし、養育費の支払い期間については、もう1つ違った解釈の仕方もあります。
この解釈からすれば、養育費の支払い期間は変更することが可能になるのです。
養育費の支払い期間は子供が未成熟子である間
養育費の支払い期間は、子供が経済的・社会的に自立できない未成熟子である間とする考えもあります。

そのため、下記のようなケースでは支払い期間の変更が可能になるのです。
- 20歳であるが大学に進学している → 支払い期間の延長
- 20歳未満だが高校卒業と共に就職した → 支払い期間の短縮
当事者同士の合意、または裁判所の裁決が必要になりますが、希望がある際は相手に相談してみるといいでしょう。

しかし、注意して欲しいのは、必ずしも要望通りの結果になるとは限らない点です。
特に裁判所に裁決を委ねた場合は、認められない可能性が高くなってくるでしょう。
この養育費の支払い期間の変更については、下記の記事で分かりやすく解説しています。
あなたが子供の大学進学を見据えて、支払い期間の延長を求めているなら、知っておくべき重要な情報が満載です。
必ず目を通して、交渉時の参考にしてください。
養育費の支払い方法は分割じゃなきゃダメ!?

「養育費を一括で請求したい。」
あなたがこう考えているなら、いくつか注意して欲しいことがあります。
養育費を一括請求するのは可能です。

しかし、これは相手が合意した場合に限定されるでしょう。
裁判所は原則、養育費の一括支払いを認めていません。

そのため養育費支払いの長期的な履行が期待できないと判断される場合を除いて、一括請求を認めることはないのです。
裁判所に一括請求を求めて調停申立しても、認められる可能性はないと考えておきましょう。
また、相手が一括請求を認めた場合も注意が必要です。
高額な贈与税を支払うことにもなりかねません。
養育費の一括請求は贈与税の課税対象に!
原則、養育費は非課税です。

しかし、一括請求した養育費を銀行に預金すると、非課税条件を逸脱してしまい、課税対象になってしまいます。
その際の贈与税は受け取った養育費によって10%(200万円以下)から、最大で55%(3,000万円超え)もの税率が課せられることになるのです。
一括請求となれば総額で数千万円に及ぶことも珍しくありません。

となれば、この贈与税の支払いだけは、何としても回避しなければなりませんよね。
養育費の一括支払いをする際の注意点と、贈与税支払いの回避方法は、下記の記事で詳しく解説しています。
あなたが養育費の一括支払いを検討しているならば、この記事で必要な情報を入手してください。
養育費の取り決め時には公正証書の作成が必須!
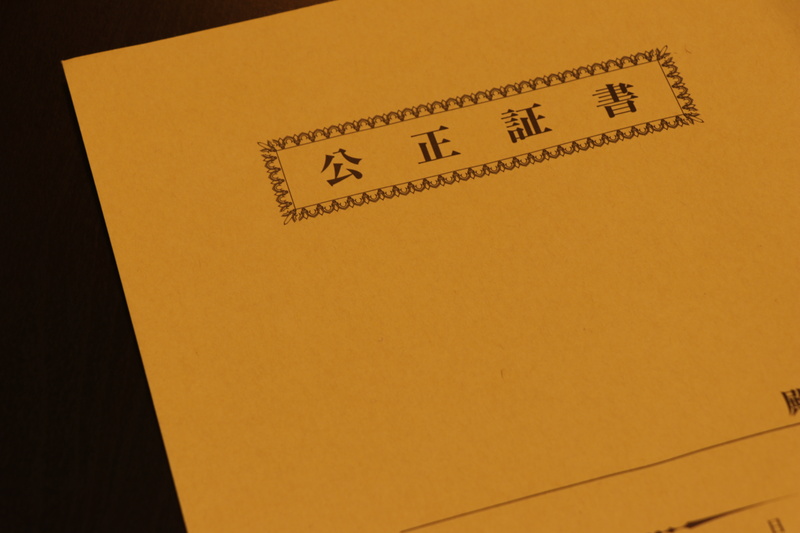
当事者間で養育費の取り決めがまとまった場合には、必ず取り決め事項を書面化しなければなりません。

中には口約束だけですます人もいるようですが、口約束は絶対にNGです。
支払いに問題があった際、口約束では取り決め事実を証明できません。
言った言わないの争いになって、請求自体も危ぶまれることになるでしょう。

絶対に口約束は避け、取り決め事項を協議書として書面化しておくことをおすすめします。
【公正証書の重要性】養育費の取り決め事項の書面化は必ず公正証書で!

書面化の方法としては、下記の3つが挙げられます。
- 離婚協議書(または養育費協議書)
- 公正証書
- 念書

書面化するのであれば、この中でも下記3つの効力が最も高い公正証書がおすすめです。
- 証明力
- 安全性
- 執行力

この中で最も重要なのが執行力です。
公正証書に強制執行認諾文言を付ければ、不払い時にすぐさま強制執行による差し押さえを申し立てることができます。

養育費の取り決めを公正証書で作成する一番の目的は、養育費が不払いになった時に、すぐに差し押さえで回収するためです。
裁判所で養育費の取り決めをする場合は、書面化にこだわる必要はありません。

しかし、裁判所を介さず、当事者間で取り決めた時は公正証書を作成しなければ、強制執行による差し押さえを申し立てる権利が得られないのです。
公正証書の効力や作成方法については、下記記事の「万全を期するならば離婚協議書を公正証書で作成しよう!」で、分かりやすく解説しています。
裁判所を介さず養育費の取り決める場合は、公正証書の作成が必須です。
あなたが話し合いで決着がつきそうならば、記事を読んで公正証書の効力と作成方法を理解しておきましょう。
養育費の取り決めは離婚後でも問題なし!

別れる時は離婚することだけに気を取られ、養育費の取り決めをしなかった。
こんなシングルマザーは少なくありません。
事実、離婚時に養育費の取り決めをしたシングルマザーは、全体の半数にも達していないのです。

しかし、安心してください。
養育費は離婚後に取り決めることもできます。

養育費の支払いは親に課された義務のため、離婚時に取り決めをしていなくても、その義務が免除されるわけではないからです。
離婚後に養育費を取り決める方法と注意点
離婚後の養育費取り決めは、下記の様に離婚時の方法と何ら変わりはありません。

まずは相手との話し合いに臨み、そこで決着がつかなければ、裁判所に養育費請求調停を申し立てるという流れです。
裁判所に申し立てれば、必ず取り決めが成立するでしょう。
離婚後に養育費を取り決める時の方法と注意点は、下記の記事で詳しく解説しています。
養育費の取り決めに必要な情報を漏らさず紹介しています。
ぜひ目を通して正しい方法で、養育費の取り決めに取り掛かるようにしてください。
ーーー
離婚後でも養育費の増額や支払い期間の延長は請求できる!

離婚時に養育費の取り決めはしたが、その条件変更が必要になった。
こういったケースは珍しくありません。
養育費相場として算定された金額は、必要最低限の費用しか考慮されていません。

そのため、受け取っている養育費だけでは、子供に満足な教育を受けさせてやれず、増額を請求するケースは多々見られます。

また、子供が大学に進学することになり、その学資支払いや支払い期間の延長を求めたいという人もいることでしょう。
こんな時は相手に、養育費の取決め内容の変更請求してください。

相手が同意すれば、養育費の増額や支払い期間の延長は可能です。
しかし、注意して欲しいのは、裁判所に裁決を委ねた場合で、裁判所が養育費の取り決め変更を認めるの可能性は決して高くありません。
裁判所が養育費の取り決め内容変更を認める可能性・・・
裁判所で養育費の取り決め内容の変更が認められるためには、請求事由に正当性と妥当性が求められます。

下記のような理由ならば、あなたは裁判所も認めてくれると思っているかもしれません。
- 子供を大学に進学させたい
- 子供を進学塾に通わせたい
- 子供に家庭教師を雇ってやりたい
- 子供に習い事をさせてやりたい
筆者も心情的には同意見です。
親ならば負担して当然の事だと思います。

しかし、この考えは大きな勘違いなのです。
子供の教育を理由に、裁判所が養育費の取り決め変更を認める可能性は高くありません。

裁判所は子供の教育費不足を、養育費の取り決め条件の変更事由として認めていないからです。
全く可能性がないわけではありませんが、認められるのは一部条件を満たした場合に限定されるでしょう。
この問題に関しては、下記の記事で分かりやすく解説しています。
あなたが子供の教育を理由に養育費の増額や、支払い期間の延長を請求したいなら、この記事に目を通して、その可能性を探ってみましょう。
お互いの再婚は養育費に影響する!


最初に言っておきますが、離婚後の再婚は養育費減額の可能性があります。
これはどちらが再婚しても同じです。
元夫が再婚すれば高い確率で養育費は減額されますし、あなたが再婚した時には養育費が免除される可能性すら出てきます。

これは再婚が養育費の減額理由として認められているからです。
減額幅や免除となる可能性は、再婚時の結婚条件が大きく影響してきます。
よって、再婚が養育費に及ぼす影響度合いを、理解しておく必要があるでしょう。
- どんな条件でどれくらいの養育費の減額対象となるのか
- どんな時に養育費が免除されるのか
これについては、下記の記事で詳しく解説しています。
再婚はお互いに、十分可能性があることです。
その時になって慌てないように、基礎知識として身に着けておくことをおすすめします。
養育費が不払いになった時の対処方法

養育費の支払い期間中に、一番心配なのが不払いです。
養育費の不払いは今や社会問題となっているので、あなたも頭のどこかには引っかかっていることでしょう。

そして、この不払い問題を解決する一番の方法といえば、強制執行による差し押さえです。
相手が支払いに応じない時には、この方法を取らざるを得ないでしょう。
そこで重要になってくるのが、裁判所への申し立てに必要な申立要件を満たしているかです。
法改正前に比べて差し押さえでの回収はしやすくなった!

裁判所への申し立て時には、下記3つの申立要件を満たしていなければなりません。
- 債権名義を取得している
- 相手の現住所を把握している
- 差し押さえる財産情報を把握している
以前はこれら3つの申立要件を満たせず、差し押さえの申し立てを、断念しなければならなかった女性が少なくありませんでした。

しかし、2020年4月の民事執行法改正に伴い、これら条件を満たすことがずいぶん簡単になったのです。
債権名義さえ取得できていれば、高い確率で申立要件を満たすことができるでしょう。
申し立てさえできれば、高い確率で不払いの養育費回収が可能です。
強制執行による差し押さえを申し立てる方法と注意点は、下記の記事で詳しく解説しています。
養育費の不払いは誰にでも可能性のあることです。
不払いになった時にすぐ差し押さえの申し立てができるように、しっかり目を通して対策を講じておくようにしてください。
まとめ
今回は養育費の取り決め方を徹底解説しました。
養育費の取り決めで揉める夫婦は少なくありません。

交渉を上手く乗り切るためにも、そのポイントはしっかり押さえておくべきでしょう。
また、支払い期間中に起こりうる問題にも、対応しなければならない可能性もあります。
今回の記事を参考にして、問題解決に取り組むようにしてください。