鴎庵:書評 (original) (raw)
鴎庵:書評 2024-09-22T17:35:13+09:00 wavesll カモメとは特に関係のない話をする縁側サイト Excite Blog フェルナンド・ペソア著 澤田直訳編『ペソア詩集』 望みを絶った先の真情の詩 http://kamomelog.exblog.jp/33574043/ 2024-09-22T14:26:00+09:00 2024-09-22T17:35:13+09:00 2024-09-22T14:26:17+09:00 wavesll 書評  ポルトガルを代表する詩人、フェルナンド・ペソア
ポルトガルを代表する詩人、フェルナンド・ペソア
ペソアのことを知ったのはTwitterで幾つかの文学者などのbotをフォローしているときにみつけた@FPessoa_bというアカウント。
そのあまりのネガティヴさ、ペシミスティックさに少々食らいながら”だけどこの人は凄いな”と思いつつ、長いことペソアの作品自体は手に取らずにいて。
たまたま今年、読書へ気が向いたときに”読んでみようかな”と購入したのがこの『ペソア詩集』。今年増刷されたはずなのにすぐに品切れになっていた。
で、読んでみると”あれ、意外と力強さがあるぞ”と思って。ただ読んでいくとやっぱりこのペソアには喪失感というか不能感というか、無力な絶望感があって。その絶望の果てにどう生きるか、どう生きれるかというのが強さがあるというか、これはアドラーの『嫌われる勇気』を読んだ時のような、他者への期待感・愛されるという期待をすべて棄てた上でのサヴァイヴするための行為者という感じがしましたね。
恐らくそれは、若くして留学などをし文学などに才覚を発揮しながらも、実生活では経済的な不能感というか、彼の自意識での自分への期待値とはまるでかけ離れた経済的・社会人的な無能の烙印の中で、文学をいくらかいても”それが何になるんだ”という自問自答が心の中でこだまし続けた人生の発露でもあったのかもしれません。
「ぼくらはみな ふたつの生を生きている ひとつは生きられた生 もうひとつは思考された生 ほんとうの唯一の生は 本物と偽物のあいだに 分かたれた生
しかし このふたつの生の どちらが本物で どちらが偽物なのか それを説明できる者は この世には 誰ひとりとしていない それでぼくらは 自分の生が 思考される生であるかのように 生きることになる」
こんな調子で平静のなかで淡々と真実そのものを語っていくペソアの詩を読んでいると、まるで中学の時に『人間失格』を読むような、自分の存在自体や恥部が切り裂かれて血が滴るような感覚に襲われるというか、この言い放つ存在の本質に届く力は、ロックという表現だなと感じて。
さて、ペソアは「異名」という形式で詩を発表して。本人であるペソア名義のほか、アルベルト・カエイロ名義、リカルド・レイス名義、アルヴァロ・デ・カンポス名義の詩がこの書には収められていて。彼らには髪の色や人生自体の設定も創られていて、ペソアの世界では各人が同じ世界で相互作用しながらオペラのようなインスタレーションとして存在していると。
ただ小説の登場人物と違うのは、ペソアの研究によると、「キャラクターのために詩がつくられた」というよりも「詩のためにキャラクターがつくられた」とのことで。このペソアの同位体である異名たちは、現代においてはハンドルネーム等を多数アカウントを持つSNS人としてイメージするといいのかも。と同時にこの虚構性・フィクション的な感覚がペソア自身に「俺は文章の中の世界ではこんなにも力強いのに、そんなのは現実では何のパワーも持たず、嘘の存在として霧散してしまう」という感慨を持つことになったのではないかと思ったり。
さて、ペソアの異名のキャラは各人魅力的なのですが、中でもペソアが「自分の師である」としたアルベルト・カエイロの詩に現れる思想、それはこの世には物理的なことが真実すべてで、象徴がどうだとか、”その奥にある意味”だとか、そんなことは何の意味もありはしないことだ。それは神についてすらそうだ、という唯物的、あるいはスピノザや仏教の悟りにも近いような思想も、一旦社会に希望を断ち切られたうえで、すべての幻想を廃して生きていくアティチュードにみえて。
この不能感と、一種の攻撃性は、どこか矛盾している感もある気がしていたのですが、ペソアの詩を読むと、自分自身の人生の挫折感と、ポルトガルという国が大航海時代では世界の覇者だったのに今や凡国以下に国力が衰退してしまった国家としての栄光と挫折を重ね合わせていたようにも感じて。
また永遠の少女リディアに語り掛けるリカルド・レイスの詩と、今から100年強前の第一次世界大戦頃の技術増進の時代の未来派としてのパワーにみせられつつ、自分の非モテさを出したりもする男っぽいアルヴァロ・デ・カンポスの詩も、キリスト教以前のギリシャ・ローマの神話や詩人から「現代」に通じる時空を自在に行き来するようなペソアの哲学がみてとれ、キリスト教を排そうとしつつも認める距離感とか、近代人の懊悩にあふれた思想概念は非常に現代的というか、それこそネット時代に生きたらサイバーパンクを書いてそうな人だなと思いました。
何かになろうとしたけれど、何物にもなれず、年老いてしまった己。その中でくすぶり続ける心の焔。他者への期待はもう持てないのに、悟って”あきらめたよ”と嘯きながらももがき続けてしまう、滑稽な男の中にある思想の伽藍。
いつの世にも地獄をみた人間が真情と事実を遠慮なしに吐き散らすことへの魅力というのはあって。ロックンローラーやラッパーもそうだし、永野などの芸人もそうでしょう。その刃は、攻撃側である書き手自身も切り刻んでいく諸刃で、その生々しい鮮血と生肉が、リスボンの海に拡散し、時代も地域も超えて行って。いや、これはちょっと凄い詩集でした。]]>
魯迅『野草』 近代中国のストレスフルな引き攣りから生まれる文藝 http://kamomelog.exblog.jp/33454199/ 2024-09-06T00:15:00+09:00 2024-09-06T00:15:13+09:00 2024-09-05T14:48:10+09:00 wavesll 書評 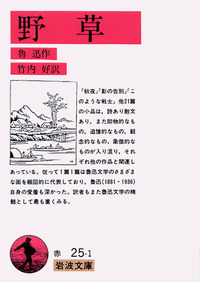
魯迅『野草』を手に取ったのは本年の横浜トリエンナーレのメインテーマがまさにこの魯迅の「野草」であったこと。
私自身、実は今回の横浜トリエンナーレは、というかヨコトリは今までもそこまで食指が動かなくて。といいつつやはり横浜の街で開かれている芸術祭だけあってパブリックアートは普通に横浜で暮らしているうちにみていて
で、会期末間際になって、というかもう終わっちゃってから多読せよ、精読せよ…第8回横浜トリエンナーレはテキストの祭典か?市原尚士評を読んで”あっ!こういう企画だったのか…日美だけじゃまるでどんな展示かわからなかった”となって
結局トリエンナーレ本体をみることは出来なかったのですが、そんな経緯もあって魯迅『野草』を読んでみたかったんですよね。
そして読み進める内にかなりぞわぞわとした圧を受けて。というのも、この残暑すら底冷えするような、フェルナンド・ペソアやトーマス・ベルンハルトにも匹敵するような劇烈に鬱鬱とした感情が、それを伝導するに足る筆致で描かれていて。
実はこの読書、Apple Musicでカミラ・カベロのエロエロなライヴをかけながらみたのですが、それくらいしないとこちら迄陰鬱な谷に引き擦り込まれてしまうような精神波長がありました。
今の、例えばHowie LeeとかBagedai, RUNRUNRUN, 麻伊/outtawave/Yaniussとか南方酸性咪咪みたいな豊かになった後の中国の現代のヒト達のバイブスとは全く異なる、貧困・清冽・陰惨といった、ちょっと顔が引き攣っているような鬱屈した頃の中国人の顔つきが読んでいて頭に浮かぶというか。
一つ面白かったのは市原尚士評の「利口者」と「馬鹿者」のダイアローグという形式は『野草』の「賢人と愚者と奴隷」へのオマージュだったのだなというところ。この評もそうでしたが、横トリ自体も相当歴史的に積み重なってきた知見への学びとレファレンスがあったようで、う~んやっぱり行くべきだったなぁ。
魯迅は近代中国を代表する文学者ですが、やはりこの『野草』に於いてもその才覚は発揮されているように感じて。個人的なコンプレックスで”私の書く文には文学的な光がまるでない”というのがあって。どうも説明文的になってしまう。webとかで他の人たちの魔法的な魅力ある文章を読むと一抹の悔しさもあったり。
ただ、『野草』を読んで、”あぁ、文学というのは説明文からの発展というか、物事や心の動きを子細に見つめ、それをしっかりと出力することでも成しえるのかもしれない”と想って。魯迅のストレスフルそうな表情を想像しながらこの人からも文学が紡がれたのだということに一縷の希望を観た次第でした。
]]>
ダンテ・アリギエーリ (著)・平川 祐弘 (訳)『神曲 地獄篇・煉獄篇・天国篇』でキリスト教世界の地の底・浄罪の山・宙を旅する http://kamomelog.exblog.jp/33442905/ 2024-08-23T23:24:00+09:00 2024-08-26T11:34:54+09:00 2024-08-23T16:28:03+09:00 wavesll 書評 
この三日間でダンテ『神曲』の『地獄篇』『煉獄篇』『天国篇』を一日ずつ読んでいました。
この大著を手に取ることになったのは、コロナ禍の緊急事態宣言の頃にボッカチオ『デカメロン』を読んだ際に訳者の平川氏が「『デカメロン』は『神曲』を下敷きにして描かれている」というようなことを後書きで書かれていて、”そんな繋がりがあったのか”と購入して。
ただ、実は一巻辺り500頁近いものが三巻という大著さと、前に「『神曲』は輪読しないと訳が分からない」という話を聞いていたことからなかなか手が出なくて、今回数年の時を経てこの頂に挑戦することになったのです。
先に難解かどうかについて述べれば、確かに夥しい古今東西の英雄や市井の人々に地獄や煉獄、そして天国で出逢うため、西洋世界の古典作品の知識が読解の為に必要には成ります。ただ、平川氏の翻訳は大変に読みやすく、適切な脚注もついているために一気呵成に読めるというか、その面白さに惹きこまれてぐいぐい読ませる力が本書にはあります。いってみればルネサンス版のFGOとでもいえば伝わりやすいでしょうか。
物語の冒頭、ダンテは深い森で迷っています。当時ダンテはフィレンツェを政治犯として追放されて流浪の身であり、この森は人生の混迷の比喩なのかもしれません。そこで彼が敬愛する古代ローマの詩人ウェルギリウスに出逢い、ウェルギリウスと共に地獄と煉獄を、そしてダンテが恋焦がれるも他人の妻になった末に夭折した幼馴染のベアトリーチェと共に天国を旅することになるのです。
(あ、そうだ。このエントリは一定のネタバレが含まれます。全くのサラで読みたい方はどうかページを閉じられてください)
『神曲』は『聖書』に次いで西洋美術の数多のモチーフとなってきた作品ですが、何しろこの筆致が凄くて。地獄の圏谷を下っていく末に見る景色や煉獄の山を登っていく様、そして天国の果てでみたその景色の描写は、震えるような体感を与えてくれます。
そして、この世界観は徹頭徹尾キリスト教中心主義で。辺獄(リンボ)に始まる地獄にはウェルギリウス自身もいるのです。それは何故かと言えば、ウェルギリウスはキリスト教以前の人であり、キリスト教信仰がなかったために善き人であっても地獄の第一層に押し込められていて。実はここにはアリストテレスやプラトンもいるのです。
そこからどんどんと圏谷を下りて行って最深部へ目指す過程で『イーリアス』や『オデュッセイア』で読んだギリシア神話の英雄たちや神々、クレオパトラなんかもいて。
そして実は神曲はイスラム圏に於いては忌み嫌われる書で。というのもマホメットとアリーが凄惨な姿で地獄を味わっているから。ダンテが生きた当時、マホメットはキリスト教を分派させた悪人と考えられていたのです。
マホメットへの偏見もそうですが、実は『神曲』でダンテは自分と敵対した現世の人間を地獄などに、非常に良くしてくれた人間を天国に配置して。そう、ここが面白いのが神曲の地獄煉獄天国には神々やケルベロスのような化け物、歴史上の偉人たちと並んで当時のフィレンツェなどで実在していた人物たちも組み込まれているのです。さながら『Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band』のジャケのような一大絵巻が展開されるのです。
地獄の惨状は本当に筆舌に尽くしがたいというか、まるで『原爆の図』の広島の有様や、恐山の荒涼とした景色の様で
地獄の深部へ行くにつれて、凍えるような寒々とした景観がやってきて。封印されている巨人族(これらもギリシア神話から)たちを越えて、ついにコキュートスへ達するとそこには悪魔大王(サタン/ルシフェル)がブルータスとカシウスとユダを噛み締め食っていて。その獣性には息をのむような想いをしました。
”ここからどうやって抜けるんだ?”と想ったら悪魔大王の體を登ると悪魔大王が反転して、地表へ辿り着いたのです。地獄はエルサレムの地下にあり、悪魔大王は地球の最深部にあり、そこで反転すると反対側の南半球に出て、煉獄が拡がっていて。そこにはレテの河も流れていました。忘却の河であるレテ、ceroの『POLY LIFE MULTI SOUL』にも「レテの水は飲まない」という詩があったなぁ。
この煉獄、私はこれまではっきりと煉獄とは何かを掴んでいなかったのですが、煉獄は「天国に行くための浄罪界」であり、煉獄山として存在しています。この険しい山を環って上がっていくことで、一環ごとに七つの大罪に対応して罪を贖っていきます。ダンテ自身も一環づつ上がるごとに身が軽くなっていきます。また別モノではあるのだけれども、ぐるぐると上がっていくその景色はまるでブリューゲルの『バベルの塔』だなと想起しました。
地獄でも、そして天国でもそうですが、何を罪とするか、何を徳とするかの序列は『神曲』の読みどころの一つで。例えば高利貸しなんかは地獄のかなり深いところに封じられます。なんか現実世界っぽ過ぎる気がして宗教の精神世界で取り扱うのは違和感が有る気がしますが、宗教が世を統べる規範として中世世界では大変な権威があったんだなと。
そして辿り着く煉獄の頂上にある地上楽園、ここにおいてダンテは最愛の人、ベアトリーチェに逢います。ところがベアトリーチェは今の言葉でいうところの「おこ」で。ダンテが彼女が逝去した後乱雑な人生をして彼女を想わなくなったことに腹を立てていて。
と同時に『神曲』におけるベアトリーチェは天国の解説者であり、絶対的な神に帰依した存在、ちょっとこの例は通じるか分かりませんが、江川達也の『Golden Boy』の金剛寺に帰依するオンナみたいな、ちょっとカルト幹部な上から目線のキマりかたをしていてwだがそのSっ気がまたいいwそして天国を登っていくにつれてベアトリーチェの神々しく気高い美貌も輝きを増していって。
天国は、宇宙。月から始まり、太陽や木星などの天をめぐって。『神曲』の地獄篇と煉獄篇はその景色がリアルすぎるほどの克明な描写で綴られるのですが、天国に於いては実は空間物理的な描写は少なくて。何しろ光に包まれていて、眩しすぎてダンテは目がやられてベアトリーチェの笑みすらみえなくなることがあって(後に回復)。
では天国では何が描かれるかと言えば、キリスト教の神学というかダンテが基督教の理解を試されることもあるし、ダンテの心に浮かんだ基督教への疑問が天国の民たちによって回答されていって。
一大旅文学と言えば『西遊記』もありますが、いってみれば1/3が天竺での物語だとクライマックスってつくれるのかな?と想いつつ、”結婚式のニセ神父の言葉を聴いても、西洋の社会の根幹をなすのはやっぱりこのロゴスなんだよなぁ”とも思いながら読み進めて。ちょっとこの問答はチベット仏教の聖地、ラルンガルゴンパも想起しましたね。と同時にエチオピアの人々のキリスト教信仰を認めなかったりするのは欧州中心主義の差別的な視点の軛からダンテもこの時代の人間として逃れられなかったのだなと。
さて、そうして読む内に気づくのは天国における音楽の描写の多さ。神の御業をあらわす視覚的描写がない一方でそこで鳴り響く聖なる音が幾たびも幾たびも綴られて。実は雰囲気を盛り上げるために『神曲』を読んでいる時にらじるらじるでNHKFMのクラシック番組をかけていたのですが、これが非常にマッチして。特に天国篇に於いて聴覚の刺激が文学を立体的に展開してくれました(オススメです)(さらに追記すると熾天使等はBASTARDのヴィジュアルで読みました)。
そして遂に出逢うアダム、エバ、モーセ、マリア、三位一体。至高天(エンピレオ)で眩くすべてを超越する光がさんざめいて、ページを読む手が止まらない。とてつもない奇蹟が眼前に広がるような、これはまことの最高潮でした。
この物語の中で過ぎた時間は一週間程だそうですが、実際本書は詩の形式であって文字数も比較的少ないので、一気呵成に読まなくとも一週間あれば読めると思います。一週間で地獄と煉獄そして天国を、旅してみませんか?
私はウェルギリウスが描いた『アエネイス』や、あるいは本書の題名に『神曲』という訳を出した森鴎外/アンデルセン『即興詩人』をめぐってみたくなりました。文学の廻遊の旅は尽きるところがありませんね◎]]>
アブー・ヌワース『アラブ飲酒詩選』背教な飲酒と男色・女色の放蕩の限りを愉しんだ8~9世紀の詩人の言葉 http://kamomelog.exblog.jp/33440932/ 2024-08-20T19:52:00+09:00 2024-08-20T19:52:07+09:00 2024-08-20T11:10:21+09:00 wavesll 書評 
新橋駅前の古本市で入手した『アラブ飲酒詩選』。最初は”イスラム教以前の自由なペルシャの空気なのかな?”と想ったらバッリバリにイスラム教が支配する時代でw(これは『ルバイヤート』でもそうでしたね)
まぁ詩人アブー・ヌワースが活躍したアッバース朝イスラム帝国の最盛期は相当に文化が爛熟していたらしく、結構酒も飲まれていたみたいで。それでも公然と酒を飲むヌワースは投獄されたり、都落ちもしたとのこと。彼に言わせれば背教的だからこそ飲酒は愉しいのだとw藁w
ヌワース、本書の一発目から朝酒を謡ってwマジでアル中の極みじゃw
面白いのはこのアブー・ヌワース、酒だけでなく淫猥な方面も美少年への男色と、さらに女性への性行為もやる両刀でw放蕩の限りじゃないかとw
ただ、本書の半分くらいを占める飲酒詩のあとに収録されているのは故郷であるバスラで片思いしたジャナーンという女性への熱烈且つ清純さも感じるような恋愛詩で。ただこのジャナーンからは畜生のごとく毛嫌いされていたらしく、バグダードへ出てからの男色趣味はその反動でもあったのかもしれないと解説にはありました。また晩年は放蕩の罪への許しをアッラーに乞う詩も描いていて。
このアブー・ヌワースの歯に衣着せぬというか、自分の欲望・思いにどこまでも馬鹿正直に忠実に綴る筆致が読んでいてスカッとするところがあってw何しろ酒を愛するあまり擬人化・神聖視までしてるしw
アブー・ヌワースは当代随一な位の知識人だったらしいですが、教養ある人が必ずしもポライトとは限りませんからねw寧ろその脳を快楽や放言にやりたい放題にすることもあるw
酒を愛し、性欲放蕩を愛し、あるがままに生きたヌワースの言葉の清々しさに、思わず酒を乾杯したくなりましたw清廉潔白なだけが人生じゃありませんねw
]]>
川端康成『雪国』感傷的な、不能と情愛の物語 http://kamomelog.exblog.jp/32897101/ 2023-02-15T21:36:00+09:00 2023-02-16T06:52:57+09:00 2023-02-15T11:57:03+09:00 wavesll 書評 
Roméo Poirier - Living Room (bandcamp link)

川端康成の『雪国』を読みました。
「国境の長いトンネルを抜けると雪国であった」というあまりにも有名な書き出しは「夜の底が白くなった」と美文が続々と続いて行って。
主人公の島村が恐らくは越後の温泉地を訪ね、そこで芸者の駒子と葉子という二人の女との触れそうで触れない感情の交わりを過ごすという物語で。
十代の頃に島村と出会った駒子は島村に情愛を深く持っていて、それに対して島村は駒子の心に気づき、情愛を持ちながらも「友人でいたいから肉体関係は持たない」と突き放している。駒子とつかず離れず、いやヤらないだけで恋愛的な密接な関係性を遊んでいて、さらにはこの旅で新しく出逢った葉子にも強く惹かれている、という。
”さんざん魅惑し心を奪っているのに、カラダに手を出さない、責任を持たないで心を弄ぶなんてクズ男じゃないか”とは思うのですが、どうやら島村は親の財産を食いつぶしながら、世間的に何の役にも立たない西洋舞踊の研究を(それを映像として観ているわけではなく書物で)研究するという生活をしていて、さらには細君もいるということで、なんというか不能感が島村の心の芯には纏わりついているのではないかなと想いました。
また個人的に印象的だったのは物語に幾度も挿入される虫の描写。なんというか小さい虫を潰したり逃がしたりするような描写なのですが、温泉と虫というと志賀直哉の『城の崎にて』を想起させて。一人男が温泉地に泊まりに行くという行為・環境はどうにもエモーショナルな風合いが高まるのかもしれないなとも考えさせられました。
まるで活動写真のように物語はアップされパンされ、不意に終わります。インモラル性があるからこそ耽美さと冷酷的というくらいの現実味がこの小説には宿されているなと。さらに言えばモラル、インモラルの前に「そうであってしまった現実」がさらりと描かれているように読めるのはやはり筆力ということなのだろうなと。
この小説、文庫にして148ページ。読むのに何か凍れる音楽をかけようとRoméo Poirier『Living Room』をかけたら2周80分ほどで読み切れて、今日のような寒日にはぴたりと嵌った読書体験となりました。
]]>
川端康成 新潮文庫『伊豆の踊子』「伊豆の踊子」「温泉宿」「抒情歌」「禽獣」鋭利で深山な智筆の作家の若き青春短編 http://kamomelog.exblog.jp/32670617/ 2022-07-28T00:06:00+09:00 2022-07-28T00:51:58+09:00 2022-07-27T15:27:14+09:00 wavesll 書評 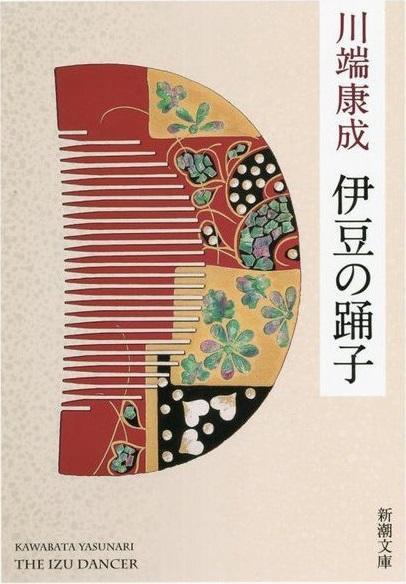 踊り子 / Vaundy
踊り子 / Vaundy
夏だしなんか爽やかな小説読むか。Vaundyの「踊り子」にかこつけて、大作家の大有名作を何気に読んでないから『伊豆の踊子』読んでみよか。と手に取った川端康成『伊豆の踊子』。
で全然事前情報を入れてなかったので驚いたのが「伊豆の踊子」って僅か40ページの短編なんですね。東京のエリートらしき学生が伊豆を旅して、旅芸人の一行の若い踊り子にちょっと惚れて、一行と仲良くなり共に伊豆の宿場町をめぐり、そして別れる。読んでみて”あれ?ほんとに何てことない話だぞ?”と最初思って。踊子との淡い恋は本当に淡い恋で、当初学生は踊り子と寝たいと思っていたのだけれども化粧して大人びていたけれども彼女は幼き生娘で、ちゃんと保護者の管理下にあって、あっけらかんとした温泉シーンはあるけれども、特にコトが起きるわけでもなく、言ってみると本当に爽やかなひと夏の出会いが描かれて。
で、ちょっと拍子抜けした後に読んだ『温泉宿』が、温泉宿の娼婦たちの季節がめぐる様が描かれた作品で、まるで南米小説、ガルシア・マルケスやバルガス・リョサのような淫靡で溌溂とした一種の明るさと暗さが入り混じる様がうっすら日本の情景に混じる読み口に”これ、何気に凄くない?”と。
さらに次の「抒情歌」は思いを果たせなかった想い人に未練というか連綿とした心持を綴る女性の語り口なのですが、古今東西の宗教・スピリチュアル思想が引用されて”おいおいこれは凄いぞ”と。
そして「禽獣」!小鳥を始めとした小動物を多数飼う独身男の、嗜虐的というかフェティッシュの極みであり一種の非人間的な快楽と自虐性のある思想が展開されて、これが一番ぐわっと来ましたね。これはヤバすぎた。
で、新潮文庫に収録されている解説が素晴らしくて。これで目から鱗が落ちて。竹内寛子による川端康成の人生含む基本情報の解説で川端が早くして家族を亡くし孤児となったのを知ります。東大卒なことも。
そして目を見張ったのが三島由紀夫筆の『伊豆の踊子』解説。これによって後の三篇に見られる非常に深い、性と生を感じさせる小説世界が、『伊豆の踊子』においても「処女性」をキーワードに展開されていると明かされて。俺、全然読めてなかった。
さらに重松清による『伊豆の踊子』解説では、主人公の学生が孤児根性のひがんだ気持ちに耐えきれなく伊豆旅行へ出た一節や、旅芸人たちが乞食芸人とされた看板の一文などを軸にいかにこの旅が、学生にとっても旅芸人一行にとっても心を通わせた思い出になったかということが滔々と解説されて。まじで「何も起きなかった」なんて言ってしまってすみませんm(_ _)m
と同時に川端自身が後半生で『伊豆の踊子』に関して”ひがごころ”があると語っていたことも紹介されて。世に知られる超大ヒット作が、作家にとって幸運なことであり有難いことではあるけれども、同時にそれでずっと自分が語られることへの”ひがごころ”。ミュージシャンでもそういうことは好くあるよなぁなんて思いながら読みました。
で、もう一度読み直した『伊豆の踊子』。爽やかで、確かに自分はバイオリズム的にも後のもっと嗜虐性の高い大人な作品たちの方が好きだけれども、鬱屈した青春の日々で一陣の風が吹いて”あぁわかりあえた、俺は世界にいていいんだ”と想えた瞬間のきらめきを描いた、確かな名作だなぁと想いました。
]]>
ゲーテ『若きウェルテルの悩み』高橋義孝 訳 書簡により表現される激情に揺り動かされる恋愛 http://kamomelog.exblog.jp/32632625/ 2022-06-17T21:32:00+09:00 2022-06-17T15:23:25+09:00 2022-06-17T13:32:15+09:00 wavesll 書評 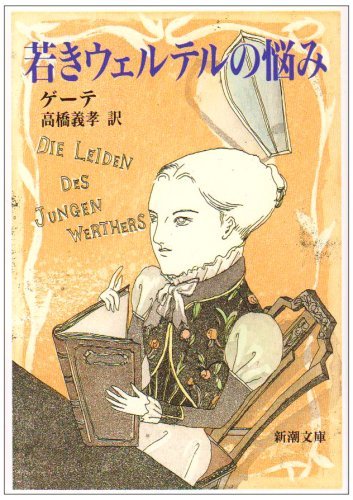 ゲーテ『若きウェルテルの悩み』を読みました。
ゲーテ『若きウェルテルの悩み』を読みました。
これはグイグイ読ませる名作ですね!物語は基本的にウェルテルから親友のウィルヘルムへの書簡で綴られていて。基本的にはウェルテル発の言葉だけで物語は推進していきます。
この書簡文学という形式、小劇団の演劇の独白のようにも感じれば、或いは”これ、Twitter文学やLINE文学としても応用できるんじゃないか?”等とも妄想したり。
ストーリーはウェルテルが婚約者のいるロッテといううつくしい人に人生最大の恋をし、その叶わない恋への激情に苦しんで…という話。
ウェルテルのキャラクターが、いわゆるインテリ的にとめどなく言葉が脳内から湧いてくる雄弁なタイプなのもTwitter民的でもあったりwけれど実務能力はそんなにないというか、上を舐めてトラブルを起こす、恋愛に限らず激情になりやすい青年で。またロッテの小説の趣味にもときめくとこなんか500日のサマーみたいで。そんなところもちょっと読みながら笑ったり。
そのウェルテルの友人へ向けた書簡の韜晦にFullになった文体が、これが意外と読みやすくて。全体的に非常にSmoothに読めるこの文章の良さは翻訳者の高橋さんの功績ですね。
なのでその文章の一部分を取り上げるというより、総体としてのウェルテルの「こころの駄々洩れ」が、読んでいるこちらの脳にもDLされていくような読書体験でした。
終盤に書簡形式から通常の三人称へ文体が変わったのは残念ではありましたが、それによってウェルテルが「天使…かな」と一目ぼれし想いを寄せるロッテの心の裡を知ることが出来て。
さらにクライマックスとなるオシアンの詩が詠まれる場面はとてつもない感動がありました。ここの詩の表現の翻訳に関しても同じ高橋氏が訳した『ファウスト』よりも素晴らしく浸透していったなと想いました。
この激的な恋愛の行く末は伏せますが、当時「精神的インフルエンザの病原体」と呼ばれただけあって、とんでもない刺さりをもたらす書でした。
]]>
アシュターヴァクラ・ギーター 真我の輝き 訳:福間巌 読むだけで心的容量が拡がる感のあるインドの聖賢に愛された最も純粋な聖典 http://kamomelog.exblog.jp/32455726/ 2022-01-29T07:15:00+09:00 2022-01-29T09:46:17+09:00 2022-01-29T07:15:50+09:00 wavesll 書評  Webで知った本書。インド哲学というのをしっかり読むのは初めてだったのですが、平易な言葉で「真我」について画かれ、読むだけでこちらの心の容量が大きく広がるような想いになって。素晴らしかった。
Webで知った本書。インド哲学というのをしっかり読むのは初めてだったのですが、平易な言葉で「真我」について画かれ、読むだけでこちらの心の容量が大きく広がるような想いになって。素晴らしかった。
「アシュターヴァクラ」というのは『ラーマーヤナ』にも登場するキャラクターだそうですが、本書の著者は不詳です。けれど、その言葉たちの澄明さは、大いなる力を以て読者に語り掛けてきます。
そこで展開される論は、端的にまとめてしまえば「あなたは宇宙すべてである。観照者、気づきである。故に身体はあなたではない、真我に目覚めれば、『心』から解放される」というもの。
「己」が「宇宙」まで満ちていれば、俗世での怒り、悲しみなどはそもそも存在もせず、何にも心脅かされず、瞑想すら必要なくなる、と。こういうことが幾度も幾度も変奏されていきます。
仏教でいう「悟り」とはこういうものか、とか、あるいは我執を滅して心の安定を得るという意味ではマルクス・アウレリウス『自省録』からすらさらにその深奥に進む論な気も。あるいはそこで在る「神」はスピノザ的にも感じて(アシュターヴァクラ・ギーターでは神という概念すら認識する必要がなくなるそうですが)
ただ、現代日本視覚文化に触れている人間としては、『私』が溶けていく、完全たる存在になるというのは人類を補完する計画にも感じられたり、エヴァ旧劇の元ネタである漫画版『風の谷のナウシカ』終盤での、完全になることを否定し人間の業を引き受け生きる選択を想ってしまうところはありました。
自我・個人の意志という活動の源である力と、本書で画かれる圧倒的な心的空間・絶対的な真我の自由。この二つの間で揺れ動きながら、一種両輪を以てこの世界を渡っていけたらなぁと想う処です。少なくとも一読には真に値する名著だなと感じました。
]]>
トーマス・ベルンハルト『凍』池田信雄 訳 凍てつく寒村にて展開される鬱から生み出される暗澹たる思想の圧壊 http://kamomelog.exblog.jp/32446910/ 2022-01-20T21:42:00+09:00 2022-01-20T22:34:58+09:00 2022-01-20T11:06:56+09:00 wavesll 書評  この『凍』という作品を知ったのは何かの文学賞のニュースに関連したものだったと思いますが数年前のことで詳細は記憶になくて。ただ『凍(いて)』という言葉がそれから脳内にずっとあり、”折角読むなら厳寒の時期が好いだろう”と数年温め、本年に入って読むことができました。
この『凍』という作品を知ったのは何かの文学賞のニュースに関連したものだったと思いますが数年前のことで詳細は記憶になくて。ただ『凍(いて)』という言葉がそれから脳内にずっとあり、”折角読むなら厳寒の時期が好いだろう”と数年温め、本年に入って読むことができました。
研修医である”ぼく”が上司の下級医から命じられ、ヴェングという寒村に滞在する上司の弟である画家シュトラウホを観察し行った27日間の記録がそこでは認められて。
このヴェングという田舎町に篭っている腐敗臭というか陰気な空気感は、読んでいてタル・ベーラによる映画『サタンタンゴ』が補助線になってくれました。宿の女将の爛れた性関係、そして発電所建設で命の危険を冒しながら働く労務者、すべてがゆっくりと奈落に落ちていくような”篭る空気”。
そんな中で本作のメインである画家シュトラウホの弁舌は、読んでいてつらくなるほどの鬱の病症を感ぜさせて。
私自身も鬱になったことがありその症状は身をもって味わいましたが、鬱になった人というのは自分の思索の重みが脳を潰していて、汲めども汲めどもいくらでも思考がヘドロのように噴出するものです。余りにもその分量が大きく、圧壊するまでの、意味の壮烈でありながら意味の葬列ともいえるような状況になります。
逆に、私自身が朋の鬱の話し相手になったこともありますが、これはこれで底なし沼のような暗鬱たる言論に引きずり込まれる恐ろしい危険性がありました。本来、鬱状態の人には心療内科の薬と共に、資格を持ったカウンセラーにかからないと、まるで中性子惑星の重力に絡めとられるように共倒れになってしまう恐れがあるなと読んでいて”あのころの記憶・心持”を想い出さずにはいられなくなりました。
画家シュトラウホの、すべて連関し深淵な意味があるようにも読めるし、その難解さ、入り組みさから読んでいてまるで頭に入ってこない重厚・暗澹たる弁は、逆に鬱というものを身近に知らない人にはその疑似体験として非常に強度をもって顕然させる書物にこの『凍』はなっていると想います。そういった意味では疫苗としても読む価値のある一冊だと感じました。
cf
]]>
志賀直哉 - 城の崎にて 湯治で靜に想う死と生 http://kamomelog.exblog.jp/32393266/ 2021-11-30T05:59:00+09:00 2021-11-30T06:36:23+09:00 2021-11-29T13:58:33+09:00 wavesll 書評 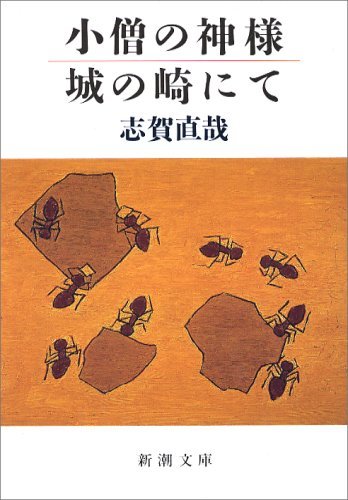 湯冷めしがちであった私は温泉というものがそんなに好きでもなかったのですが、去年、別府で温泉に目覚めて。以来、銀山温泉に行ったり、TVの温泉番組を好んでみるようになったりして。西表島の日本最南端の湯では温泉むすめに遭遇などもしました。
湯冷めしがちであった私は温泉というものがそんなに好きでもなかったのですが、去年、別府で温泉に目覚めて。以来、銀山温泉に行ったり、TVの温泉番組を好んでみるようになったりして。西表島の日本最南端の湯では温泉むすめに遭遇などもしました。
そんな中でひょいと”温泉の噺を読んでみても愉しいかも知れない”と手に取ったのが志賀直哉の『城の崎にて』。読み始めて初めて知ったのですが、これは十頁ほどの短編で、『小僧の神様』等の第二期志賀直哉の作品集として纏められた一冊でした。
『城の崎にて』は後に取っておいて、先に他の短編を読んだのですが、『小僧の神様』のようなジュブナイルと小粋さとエモーショナルさのある作品よりも全体としては痴情、特に夫の浮気などの道ならぬ情事が描かれているものが多くて。これは志賀自身の関心ごとというか性向に起因するものかなとか編者解説を読んで想いました。
そして『城の崎にて』。”これも温泉地のことだし、艶っぽい噺だろうか?”などと読み始めると冒頭から”自分”は山手線に撥ねられて、その養生に城崎温泉へ湯治へ行くという話で。
偶然にも生を得た”自分”は城崎温泉にて蜂や鼠などの小さき生き物たちの様をみて死を想います。死に親しくなった、と想いながらも、いざ死に瀕したらきっと狼狽し必死に死を避けるだろう、とか。偶然に生きた自分もいれば、意図せず偶然に死が訪れたものもいる、とか。それが志賀自身の澄明な視線によって城の崎の風景の中から見出され、思索が清澄な筆によって画きあらわされるのです。
一篇のキネマをみるような、落ち着いた、深みの淵に立つ小説。思いもかけない内容だったのですが、とても感慨深い読書体験となりました。
]]>
マルクス・アウレリウス『自省録』神谷美恵子訳 煩悩の焔を抑える剛柔な自己啓発の書 http://kamomelog.exblog.jp/32389794/ 2021-11-26T20:42:00+09:00 2021-11-29T21:30:12+09:00 2021-11-26T11:10:12+09:00 wavesll 書評 
哲人皇帝といわれるマルクス・アウレリウス・アントニヌスが己のためのストア派哲学としての自省の覚書として認めた『自省録』、この本のことを旧友に勧められたのもう十年以上前、ようやく今に読むことになるというのは、わが身のレスポンスの遅さにはバツが悪いですが、本に限らず、その人その人によって作品と出逢う機というのは千差万別であるなぁと改めて思います。
『自省録』、読んでいると煩悩の焔が収まって心が静かに高みへ行くような、非常に力をくれる書物で。
ストア派哲学というと難しそうな印象を持つ方もおられると想いますが、全十二巻が巻当たり20ページほどで書かれ、そしてその中でまるでマルクスの心の裡の呟きをみるような、短文から中文の章によって構成されていて、とっつきやすいものでした。
その内容も例えば「朝眠くて起きられないときどうするか」なんて砕けたテーマのものもあったり、と同時に極めてハードな、”どんな人間も死に、その人を知っている人もみな死ぬ、土に還り分解されるのみ。人間が考えるべきなのは死後の名誉・賞賛ではなく、現在のみをよく生きるのが肝要だ”といった思想もあったり、”他人が自分に害をなしてきても、彼がなぜそうなってしまったのか考えて、決して怒らず、どんな人にも親切に接するべきだ”というストイックとも言える人生訓があったり。
ストア派哲学における「神」あるいは「法」というのは宇宙自体が神で、その唯物論的な史観の中で、自然(ピュシス)に従って生きることが宇宙に適うことなのだという思想で。この一種の汎神論な思想は、私自身が想う神という存在の在り方にも似ているところがあるなぁと。
とにかく名誉を欲しない、あるいは他人に怒らない、わが身に与えられたものに満足し、全うしていれば、いつ死んでも生は完成しているのだという剛健な思想は、”これは逆説的にマルクスはそうあれなかったゆえに何度もそう記しているのだろうな”とか”皇帝という立場だから言えた観念でもあるよな”とか、あるいは”これは「自省」だから成り立つけれども、この姿勢を例えば他人に「良いものだから」と強要したらとんでもないハラスメントだよな”なんても想いました。また気候変動などの問題を考えると「現在だけを考えて生きろ」というのはちょっと足りない思想にも思えて。”他者がどう思おうが我関せず”はちょっと傲慢にもなりえるのでは?と。
けれども、この本を読んでいると、例えば承認欲求であったり、あるいは他人が想うように動いてくれないときのイラつきなんかがみるみる鎮まっていくのです。それはマルクス・アウレーリウスがその生涯をかけて常に自分の在り方を理想に近づけようと、己に言い聞かせている姿からの伝導でしょう。
自然(ピュシス:身体的な自然と内なる指導理性【ト・ヘーゲモニコン】)のままに生きよというメッセージは、今でも全然指導力をもって響きます。また人生において心が焼かれているときなどに読み返したい、力ある一冊であり、そして引用されている古代の名著から、ギリシア・ローマの思想書たちへの入口にもなるような書物でした。]]> セルバンテス『ドン・キホーテ』牛島信明訳 愉快な狂人である遍歴の騎士の滑稽なメタ大著 http://kamomelog.exblog.jp/32366145/ 2021-11-05T18:51:00+09:00 2021-11-11T03:37:23+09:00 2021-11-05T13:37:04+09:00 wavesll 書評  セルバンテス『ドン・キホーテ』を漸く読み切れました。『ドン・キホーテ』は因縁というか、思い出深い書物で、大学時代に第二外国語のスぺ語の講義で『ドン・キホーテ』の原著を読むという奴を途中で行かなくなって落としたり、今回も読み始めたころは夏だったのに気が付けば晩秋になっていたり。
セルバンテス『ドン・キホーテ』を漸く読み切れました。『ドン・キホーテ』は因縁というか、思い出深い書物で、大学時代に第二外国語のスぺ語の講義で『ドン・キホーテ』の原著を読むという奴を途中で行かなくなって落としたり、今回も読み始めたころは夏だったのに気が付けば晩秋になっていたり。
と、いっても読みにくい本かというと非常に読みやすい、楽しく笑えるエピソードの連続の書物で。
アロンソ・キハーノという郷士が騎士道物語を読みまくっているうちにフィクションを現実と認識する狂気に目覚めて、自ら遍歴の騎士ドン・キホーテとなり旅に出るという話。
ドン・キホーテは一人で一度、従士サンチョ・パンサを連れて二度冒険の旅へ出ます。
特に前編の大半を占めるサンチョ・パンサとの一度目の旅は、”え?こんなすぐに風車の下りが出てくるんだw?”と、次から次へと「冒険」が起きるのですが、その「冒険」は客観的に見ればなんでもない普通の情景が、ドン・キホーテの狂気にかかると風車は巨人となり旅籠は城となり、床屋の金ダライは伝説の兜となるという具合で、サンチョならずとも”正気になってくれwww”と言う気持ちと、読者としては”このおかしいお爺さんめちゃくちゃ面白いなwww”となります。
このなんでもない出来事を伝説の冒険へ変えていく想像力のなせる狂気はただ、昔私自身が騎士道ならぬロックンロールに狂っていた時の思考法というか、「フィクションの現実的な元ネタ」を探ることで現実をメタ・フィクション化させていた時期を思い出して軽い冷や汗もありました(苦笑
メタ・フィクションというと此の『ドン・キホーテ』自体も大いなるメタ・フィクションというか、数多の騎士道物語への批判的パロディであると同時に、セルバンテスは自らを第二の作者として、実はこの本はアラビア人の史家シデ・ハメーテ・ベネンヘーリの書いた原典をスペイン語で著したものだとしているのです。この構造は物語の途中で「もうこの先の原稿がない」として街を探求したまたまシデ・ハメーテのその先の原稿を手に入れるセルバンテス自身の描写があったり徹底していて。
そしてさらに凄いメタ構造なのが、『後編(機知に富んだ騎士ドン・キホーテ・デ・ラ・マンチャ)』では、この『前編(機知に富んだ郷士ドン・キホーテ・デ・ラ・マンチャ)』が物語世界の中でも大ベストセラーになっていて、ドン・キホーテとサンチョ・パンサが冒険の旅で会う人々のほとんどがこの二人を知っているという仕掛けなのです。
さらには『前編』が出た後に、偽物の著者が現実世界で勝手に出した『続編』を、『後編』ではドン・キホーテ自身が「あれはとんだ偽物だ」と幾度も口さがなくけなしたり、さらには『続編』に出てくる偽ドン・キホーテを精神病院に入れたという『続編』のキャラクターが本物のドン・キホーテとサンチョ・パンサに出会い、「あなたこそ本物だ」と語るような、メタと現実とフィクションがマーブルに絡み合う構造になっていて。
で、『後編』では実はドン・キホーテは風車を巨人と見間違えるような狂気はなく、旅籠は旅籠と認識するという変化があります。ところが、ベストセラー『ドン・キホーテ』を読んで喜んだ人々が、ドン・キホーテとサンチョ・パンサをからかって遊んでやろうと物語内の現実に寸劇であったり饗応であったりで「冒険」を仕立ててしまうのです。つまり狂人というのもここまで狂えば愉快な存在、まさに17th Century Toyとして人々に歓待を受けたのでした。
こうした非常に面白い構造をもったこの物語の主人公ドン・キホーテ自身の人物造形も、騎士道の話が出ると途端にそれをリアルだと論ずる狂気を発揮しますが、それ以外については非常に理知的で、実に立派な弁舌を披露し、彼に出会う人々は”この人間が狂っているのか正気なのか判断に迷う”と思うという面白さがあり、その従士サンチョ・パンサも、憎めない単純至極な明るい心をもって物事に対処しながらも、ドン・キホーテがいう「島の領主にしてやる」という褒美を信じる馬鹿さ加減と、特に『後編』ではことあるごとに素っ頓狂なことわざを披露しながらそれでいて非常に機知に富んだふるまいを魅せるキャラで。
この二人の掛け合い、駄弁りが物語のメインというか、誰もがおっかしく思うこのコミュニケーションの楽しさがこの『ドン・キホーテ』最大の魅力でした。
また「冒険」では、いわゆる戦闘も多く引き起こされるのですが、実は恋愛沙汰の事件が多数収録されていて。恋に狂う若者たちとドン・キホーテの絡みが描かれて。これには”なるほど、バレエ版のドン・キホーテも、ある意味主軸をつかみつつの舞台化だったのだなぁ”と。
そして物語の終焉は初読時は”え?そうなっちゃうの!?”と思いましたが、二度目に読み返してみると”なるほど、確かに伏線が張られていたのだなぁ”と。
「狂っている人をからかう人間も狂人から指二本も離れていないのだ」という箴言も、また狂いを正そうとして活きる勢いを止めることも含め、改めて色々な狂気のありように思いを馳せる読書となりました。
]]>
谷崎潤一郎『文章読本』 そこまで熟れきれない己を認知する卓越の書 http://kamomelog.exblog.jp/32338192/ 2021-10-13T21:03:00+09:00 2021-10-14T06:21:14+09:00 2021-10-13T16:12:37+09:00 wavesll 書評  谷崎潤一郎『文章読本』を読みました。本書では谷崎が1935年に上梓した「日本語での美しい文章とは何か」が書かれていて、読みながら私自身の文章や、ひいては生きる姿勢やセンスを添削されているような心地になる読書でした。
谷崎潤一郎『文章読本』を読みました。本書では谷崎が1935年に上梓した「日本語での美しい文章とは何か」が書かれていて、読みながら私自身の文章や、ひいては生きる姿勢やセンスを添削されているような心地になる読書でした。
谷崎は本書において、基本的に好い文章を書こうと思ったら出来得る限り平明で、分かりやすい語を使うことに努めるべきであり、新奇な用語であったり難解な用語で文章を装飾するのではなく、出来得る限り表現を切り詰めて、饒舌を慎み、寧ろ「間隙」をつくるために論理的に繋ぐこともあえて書かないことすら推奨しています。
ことに用語に関しては西洋(から翻訳された)言葉ばかりか、漢語も避けるように促し、大和言葉でタイムレスなものを書くべき、翁にも媼にもわかる言葉で書くべきだと主張し、また「間隙」に関しては、日本語にはそもそも文法というものはなく、語彙も少なく朦朧としたのが自然の状態であり、主語を指定する必要もなければ、関係代名詞のような概念も本来日本語にはなく、日本人というのはお喋りな人間よりも寡黙な人間を貴ぶ民であるから、出来得る限り「語らないこと、含蓄を持たせること」が重要であると説きます。
これには参ったというか、私などはついつい新しい表現であったり、装飾としての漢語であったりを使いたがったり、音楽の感想においてもやたら「物凄い」とか「ヤヴァい」とか、そういった表現を使ってしまうため谷崎からしたら「品格がない」と言われてしまうだろうと思います。思えば、文豪botの言葉を借りれば「珍しいものをありがたがるな」とか「新しさに惑わされるな」といった箴言は世に多くあり、日本人の味わいというのはいかに淡いところの彩の違いを愉しむかといったものでしょう。
また昔から私は私の文章に「俺は」とか「自分は」という表現がほかの人が書くものよりも多いなと思っていたのですが、これは幼児のあたりから英会話教室とかに通った影響もあるのかもなとか思ったり、あるいは昔は”何故周りの人間はモノをWebに書かないのだろうか、あるいは何故自分のオンラインの発言は軽視されるのだろうか”と思っていたのですが、それはこの本で谷崎が書いた日本人のものの感じ方が今も息づいていて、日本社会では寡黙は雄弁に優り、そもそもお喋りというのがよしとされない社会だということが根底にあるのかもなと。
逆にTwitterなんかが心地がいいのは、あそこは「書くこと」が「存在」になる世界で、言葉で表現する人でほぼ占められているからだなと感じます。Twitterを世間と認識すると大いなる過ちが生じるのは間違いないですが、140字の中で日本語が英語よりも適性があったのは日本語が持つ「間隙」が丁度フィットしたからでしょう。私自身にとっても文字数の制約があることで簡潔な表現を書く訓練になっているなぁと思います。私のような人間が生きやすい空間が、現在にはWebに存在しているのだなと。
新語・流行語をなるだけ使うなという戒めについては、やはり谷崎自身が人生経験を重ねて時が経つと摩耗し消えていく表現というのを目の当たりにしたからでしょう。「新しさではなく、真の価値を見出すことを希む」ということ。これに関しては私はまだ熟(な)れていないのでしょう、まだまだ新しさを求める冒険をしたいし、その遊ぶ領域を広げる旅に人生の喜びを見出してしまうなぁと想います。けれども、老年を迎えたときは、谷崎のような思想に達しているかもしれないなとしみじみと想う読書となりました。
]]>
『リグ・ヴェーダ讃歌』辻直四郎訳 古代インドの人たちの精神活動を顕したバラモン教の根本聖典 http://kamomelog.exblog.jp/32305806/ 2021-09-15T02:49:00+09:00 2021-09-15T06:48:33+09:00 2021-09-15T02:49:35+09:00 wavesll 書評  リグ・ヴェーダ、インド文化の初頭を飾りインド哲学の本源をなす重要文献.すべて口授で伝承され,後にサンスクリット語で集録された.もろもろの神を讃えて,財産,戦勝,長寿,幸運を乞い,その恩恵と加護を祈った歌たち。インドの仏教以前の宗教的知見・神話的な世界には前々から興味があって。で、この本が絶版になっていると聴き、手に入れられるうちに買った方がいいだろうと古本屋サイトで取り寄せたのでした。
リグ・ヴェーダ、インド文化の初頭を飾りインド哲学の本源をなす重要文献.すべて口授で伝承され,後にサンスクリット語で集録された.もろもろの神を讃えて,財産,戦勝,長寿,幸運を乞い,その恩恵と加護を祈った歌たち。インドの仏教以前の宗教的知見・神話的な世界には前々から興味があって。で、この本が絶版になっていると聴き、手に入れられるうちに買った方がいいだろうと古本屋サイトで取り寄せたのでした。
そこで描かれるのは暁紅の女神ウシャスや雨神パルジャニアといった自然神を讃える歌達。ヴィシュヌであったり、ルドラ(のちのシヴァ)であったり、後世のヒンドゥーとは神の立ち位置が違っていたり、アグニ(火の神)とか、何か日本語の語源にもなってそうな語感だとか、アーディティア神群の中でヴァルナの伴侶としてミトラが登場したり、洋の東西をまさに繋ぐ感覚が面白い。リグ・ヴェーダの神々の源流はイランの『アヴェスター』から来ているものもかなりあるようです。一方でヤマ(死者の王)は仏教では閻魔大王になったり。ヤマは知っていましたが、それに近親相姦を迫るヤミーという妹がいるのは今回初めて知りました。
リグ・ヴェーダにはデーヴァ(神)とアスラ(悪魔)が登場しますが、二つとも超自然的な力を持っている存在で、一読したところ仲魔のように入り混じっている感じ。また全十巻の内、第九巻はソーマ(神酒)について描かれたもので、神々が痛飲するこの蜜のような酒は、雨のメタファーであり一種性液のメタファーにもなるのかなと思いながら読んでいました。
そのソーマ(ゾロアスター教のハオマ)を大変好むヴァジュラ(金剛杵)を使う雷霆神インドラは父殺しの出生の秘密を持つところなどはゼウスとクロノスに通じる処もあるなと。またブラフマナス・パティ(祈祷主)の概念はウパニシャッド哲学においてブラフマンに繋がっていきます。さらにリグ・ヴェーダでは宇宙創成論と関連して子が親を産み親が子を産む循環発生という神話があり、これは非常に興味深い処でした。プルシャ(原人)の体から世界がつくられたというのは北欧神話のユミルに通ずるところがありました。
また讃歌には神々のことを歌うだけでなく、例えば賭博をやって全財産すったことを嘆く歌とか、長髪のヨーガの修行者の歌とか、主婦が指導権を握るための歌もあったり。リグ・ヴェーダの最後の讃歌は和合のための歌でした。
読んでいて、”あぁ、なるほど、科学が発展していないときは世界の成り立ちや不可解な現象をこのような形で処理していたのだな”と。自然は災害ももたらすし、多くの戦や、人間関係の諸々の事象も含め、古代インド社会で生きる上で起きる様々な厄災などの根本原理を神に求め、一種呪文のように神の力を借りて精神的に解決していく。
現代からすると「科学が発展していないから」という事も出来ますが、だからこそ人間の身体体験に基づき肚に落ちる説明体系になっていて、当時も一種のカウンセリング的な効果があったのかもなぁと。その見返りにバラモンはダクシナーを求めたのだなと。また西洋と東洋の間にある世界を垣間見る上でも新しい旅な読書になりました。
こうなるとゾロアスター教のアヴェスターとか、その後のインドのウパニシャッド哲学も気になるwいつか読んでみたい処です。]]> ガブリエル・ガルシア=マルケス『族長の秋』鼓直訳 朽ちていく独裁者の暴虐と孤独な悲哀を魔術的リアリズムの文体で画く http://kamomelog.exblog.jp/32297873/ 2021-09-08T02:22:00+09:00 2021-09-08T02:55:49+09:00 2021-09-08T02:22:51+09:00 wavesll 書評  本読みを本格的に始動させた際”秋になったら挑戦しよう”と想っていたのがこの『族長の秋』。
本読みを本格的に始動させた際”秋になったら挑戦しよう”と想っていたのがこの『族長の秋』。
「挑戦」というのは以前、本書を読もうと取り組んで、挫折したことがあったから。私が今まで読んだ本の中でもガルシア=マルケスの『百年の孤独』はずば抜けて面白い一冊だったのですが、学生当時の自分では『族長の秋』はどうにも歯が立たなくて。
それが今回読み始めてみると、確かに頁を隙間なく”魔術的リアリズム”の発話者に関係なく地の文がぎっしりと敷き詰められた描写が続くのですが、予想以上にスルスルと読めて。これはバルガス=リョサ『緑の家』なんかで読む体力をつけていたのもありますが、やはりガルシア=マルケスの文章がとんでもなく面白いことがその主要因でしょう。最高に面白過ぎてグイグイ読めてしまいました。
舞台はラテンアメリカの架空の一国家。列強の後ろ盾で「大統領」になった男が主人公。昔は才気あふれる実力を持っていたのかもしれないけれども、この物語時点ではもう老いさらばえていて、老醜・腐臭・朽ちて行っている。超人的な魔術の片鱗がいまだに残りつつ、誰も信じられない、また裏切られる、あるいは弱さゆえに最悪の邪悪さ、暴虐さをみせながら、その百年以上に及ぶ治世を果てようとしている大統領の「秋」が画かれます。
影武者や彼が惚れる美人コンテスト優勝者、腹心の部下、母親、ローマ教皇庁から来た審問官、正妻、大統領を魅了しその権限を使い虐殺を繰り返す男など、強烈な印象を残すキャラクターが大統領に関わり、そして去っていく。
その「物語」も相当に面白いのですが、何よりも強烈に面白いのが本書の筆致。延々と現実と幻想がゴチャ混ぜになるような光景描写が続いて。この”魔術的リアリズム”の文体は、極めて一種絢爛な風景描写なのですが、比喩を駆使しているというよりも個別具体的な事物の列挙によって”Real”でありながら”Magic”を産んでいるという点が特異で驚愕させられ魅了されます。牛と鶏の糞だらけになる大統領府で貝のぶつぶつに寄生されながらの大統領の晩年、人の領域を超えるような生の虚実。
権力が長期にわたって溜まると、かならず悪辣さが栄えていくという見本でありながら、とてつもない残虐さをみせながらあまりにも「弱い」大統領の姿には独裁者の虚しさも強烈に感じさせられ、その権勢と悲哀の奇妙な混合が、ラテンアメリカのカオスな情緒を深く表現している、そんな感慨を持った読書となりました。]]> https://www.excite.co.jp/ https://www.exblog.jp/ https://ssl2.excite.co.jp/