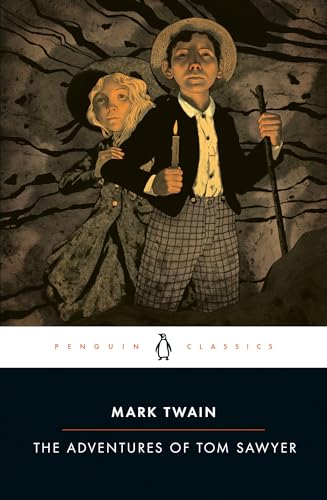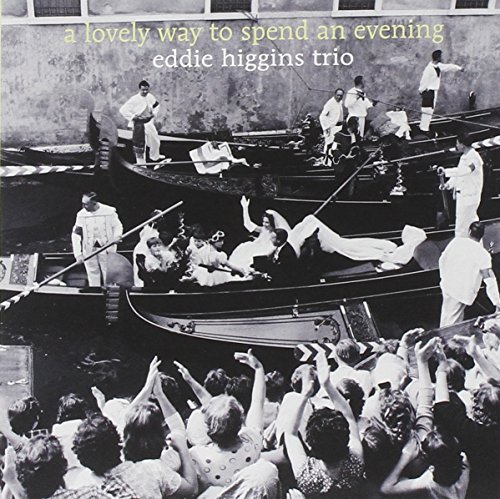ビンゴー・キッドの洋書日記 (original) (raw)
きのう、今年のブッカー賞最終候補作、Charlotte Wood の "Stone Yard Devotional"(2023)を読了。Charlotte Wood(1965 - )はオーストラリアの作家で、デビュー作は "Pieces of a Girl" (1999 未読)。one of Australia's most original and provocative writers との評もあり、"Stone Yard Devotional" は7作目である。さっそくレビューを書いておこう。
[☆☆☆★★] コロナ禍の時代、われわれはなにを行ない、なにを考えたのか。本書はその答えのひとつである。無名の語り手「わたし」は人里離れた尼僧院を訪れ、未信者のまま滞在。静寂につつまれるなか、やがて「わたし」は夫と別れ、職を辞した女性とわかるが、詳しい経緯は語られない。その脳裡に去来するのはもっぱら、若い娘時代のつらく悲しい、あるいは苦い思い出だ。亡き両親、とりわけ病没した母、みんなでいじめたクラスメイト。ところがなんと、その同級生ヘレンがいまや世界を舞台に活動する修道女となり、「わたし」のいる尼僧院へやってくる。おりしもコロナ禍と重なり、院内ではネズミが異常発生。語り手はネズミ退治に悲鳴をあげながら、ヘレンをはじめ修道女たちとの交流を通じて自他それぞれの過去のトラウマと対峙。死別の悲しみはもとより、罪とあやまち、赦しなどに思いをめぐらし人生を検証する。そう、たしかにコロナ禍とは、「わたし」同様われわれ自身にとっても自分の問題とむきあう絶好の機会だったのだ。あのとき自分はどう生きたか、どう生きるべきだったか。本書はそのことを静かに思い起こさせる佳篇である。が、人生これからいかに生きるべきか、という問いかけはない。ここにはタイトルどおり「祈り」しかない。むろんこの世に処方箋などありはしない。神を信じる信じないにかかわらず、ひとはただ祈ることしかできない、というのが現実なのだろうか。
あらためて "Nostromo"(1904)をボチボチ読んでいたが、みたび中断。きのう届いた "Stone Yard Devotional"(2023)に乗り換えた。いまチェックすると、ブッカー賞レースの3番から2番人気に浮上。
作者 Charlotte Wood のことはまったく知らなかった。Wiki によるとオーストラリアの作家(1965 - )で、デビュー作は "Pieces of a Girl"(1999 未読)。one of Australia's most original and provocative writers との評もあり、"Stone Yard Devotional" は7作目だそうだ。
出来は? ううむ、いまのところ、物語性という点にしぼれば、表題作(2024)のほうがおもしろいです。あちらは、ひと口にいうと、最初から最後まで「動」。早々に主人公の黒人奴隷 James の逃避行がはじまり(p.35)、嵐のさなか、James がガラガラヘビに咬まれるなど(p.47)、いろいろな事件が起きてテンポよく進む。
一方、"Stone Yard Devotional" は「静」。開巻、「わたし」はある修道院に宿泊することに。「わたし」が何者で、どんな理由で滞在し、どこの国の修道院なのかも当初はわからない。そこにはただ静寂があるだけ。It's shockingly peaceful.(p.12) In the contemporary world, this kind of stillness feels radical. Illicit.(p.15)
もちろん謎はしだいに解け、沈黙もやぶられる。しみじみとした味わいで読ませるが、回想がまじるなど定石どおりの展開で、滞在にいたる経緯も、まあ、意外なものではない。後半どんなツイストが待っているか、それしだいでしょうな、相変わらず1番人気の "James" を上回るかどうかは。
その "James" だが、これはぼくの数え間違いでなければ、Percival Everett の24作目の長編。2022年のブッカー賞最終候補作 "The Trees"(2021 ☆☆☆★)は22作目。多作家である。
"The Trees" は「中盤までよく出来たユーモア怪奇小説のおもむき」で、なかなかおもしろかった、とは思い出した話。じつは内容どころか、Everett の旧作であることさえ忘れていた。
彼の守備範囲はひろく、Wiki によると、numerous genres such as western fiction, mysteries, thrillers, satire and philosophical fiction をものしてきたらしい。博識でもあり、Everett earned a bachelor of philosophy degree from the University of Miami. He studied a broad variety of topics including biochemistry and mathematical logic. In 1982, he earned an M.A. in fiction from Brown University.
これに加え、彼は「アメリカにおける人種差別という、もはや文学史的には陳腐とさえいえるテーマから」、"The Trees" ではユーモア怪奇小説に挑戦。"James" では『ハックルベリー・フィンの冒険』の本歌取りを試み、かなり成功している。どんな作家でも創意工夫を凝らすものだが、Everett は経験豊富なアイデアマンといっていいだろう。
で、そのアイデアから生まれた作品は感動的なものかどうか。そこですな、問題は。(つづく)
(最近BSの再放送で見た新日本風土記『津軽晩夏』、とてもよかった。6年前の冬に訪れた斜陽館もちらっと出てきた)

もっかブッカー賞レースの下馬評はこうなっている。
1. James
2. Orbital
3. Stone Yard Devotional
4. Held
5. Creation Lake
6. The Safekeep
表題作はロングリストの発表前から一番人気。その秘密は、ひとつには、これが『ハックルベリー・フィンの冒険外伝』だから、ということかもしれない。
例によってぼくは予備知識なしに取りかかったので、冒頭、Those white boys, Huck and Tom, watched me.(p.9)という一文を見ても、あれ?としか思わなかった。
その Tom が Tom Sawyer で(p.16)、Huck が Huckleberryと明示され(p.19)、そこでやっと、『トム・ソーヤーの冒険』か『ハックルベリー・フィンの冒険』が下敷きだと察知。Tom の出番は少なく、すぐに後者がルーツだとも気づいた。
こうした流れで、アメリカ人の読者ならずとも、「(マーク・)トウェインのファンなら雀踊りしたくなるほど興味を惹かれる」はずだが、あいにくぼくはファンではない。しかも『ハックルベリー・フィン』は完読した記憶がない。
ふたつの冒険のうち、ぼくが少年時代に愛読したのは『トム・ソーヤー』のほうだ。いま書棚を見わたすと、原書(1876)もゲットしていた。
その橫にならんでいるのは、"Treasure Island"(1883)、"King Solomon's Mines"(1885)、"The Jungle Books"(1894-1895)、"The Lost World"(1912)、"Tarzan of the Apes"(1912)など。同じ古典巡礼でも、こちらのほうがずっと楽しそうだ。いまより老衰が進んだときのカンフル剤か。
一方、『ハック』の原書は見当たらなかった。奴隷制の批判などシリアスな色彩がつよい作品というのは後日得た知識で、挫折した当時はわけもなく、ただつまらなかった。
というわけで、「ハックとジムのほか、トム・ソーヤーやパップ・フィン、サッチャー判事など、マーク・トウェインの名作と同じ人物が登場する」とわかったのも、なんとレビューをでっち上げる前、Wiki で原作について調べたときだ。
本来ならきっと、上の me が Jim と判明した時点で(p.10)、ああ、あの逃亡奴隷のジムか、ピンとくることだろう。そして新旧両作を子細に比較検討すればするほど、"James" が名作の換骨奪胎であることに感嘆するのではないか。ゆえに一番人気なのだろうと推察する次第です。(つづく)
ああ、残念! "My Friends"(☆☆☆★★)、ちょっと期待していたのにショートリストから漏れてしまった。
懸念材料はあった。(2)で述べたとおり、「一朝有事のさい、自由という理想に殉じて帰国すべきか、それとも移住先で確立した地位を守り、勝ち得た信頼に応えるべきか」という問題が深掘りされていないこと。それから、最近のブッカー賞受賞作や最終候補作とくらべ、ややインパクトが弱いこと。
そのせいか、読後一ヵ月近くたったいま、あらためてふりかえっても、さほど強烈に訴えかけてくるものがない。迷っていた点数も、けっきょく原則どおり変更しないことにした。
ここで interlude。現地ファンによるショートリストの直前予想はこうだった。
1. James
1. Creation Lake
3. Playground
4. My Friends
5. Orbital
6. Stone Yard Devotional
6. Held
それがフタをあけると先日の結果となり、最新の人気ランキングはこうなっている。
1. James
2 or 4. Stone Yard Devotional
3 or 2. Orbital
4 or 3. Held
5. Creation Lake
6. The Safekeep
ぼくはこのうち、2~5まで注文したばかり。既読の候補作が "James"(☆☆☆★★)だけだったとは気が重い。同書も傑作とはいいがたいのに、もしほかの作品が下馬評どおりの出来ばえだとすれば、いやがうえにも意欲をそがれてしまう。
表題作にもどろう。カダフィ圧政時代、イギリス留学中の主人公 Khaled は友人の Mustafa ともども反政府デモに参加。リビア大使館から銃が乱射され、瀕死の重傷を負う。これは1984年4月17日、実際に起きた事件(死亡した英国人警官にちなみフレッチャー事件)をもとにしているとのことだが、ぼくはその史実を知らなかった。
それよりぼくにとって興味ぶかかったのは Khaled が英文学専攻で、こんな作品を読んでいることだった。Schoolwork was demanding. ... I read Mrs Dalloway. I read Richardson's Clarissa. I read the Brontës and Dickens. I read Trollope, George Eliot, Thackeray and Gaskell. I read earnestly and chronologically, from Chaucer to the Elizabethans to Graham Greene. I had some good teachers. I took things too seriously. I was silently horrified, for example, when in the first week, a lecturer took us to the college bar and said casually, ..., that he did not expect us to always read absolutely every single page of those big Victorian novels. I did, and ...(p.213)
ぼくも今年はたまたま古典巡礼に出かけ、いまひと休みしているところ。every single page of those big Victorian novels という phrase が、ずしりと重く感じられる。Dickens なんて、見るからに戦意喪失のボリュームだ。
そういえば、だれのどんな小説だったか、アメリカの高校生が「国語」の授業で Faulkner を読まされるというエピソードがあった。そしてイギリスの大学で出される課題は、上のように demanding。むろんフィクションだが、おそらく実際も似たようなものだろう。マジかよ、といいたくなった。
本書には先月紹介したとおり、Conrad の話も出てくる。ぼくはたまたま "Nostromo"(1904)を読んでいる途中、"My Friends" と "James" に乗り換えざるをえなくなり、もっか上の四冊が届くまでのつなぎに再挑戦中。
中断したせいでかなり人物関係を忘れてしまい、英語版 Wiki で確認しながらボチボチ読んでいる。それでもやっと面白くなりかけてきたところだ。いやはや。
(最近寝床の友は時代小説)
きのう、今年のブッカー賞候補作 Percival Everett の “James” (2024)を読了。Percival Everett(1956 - )は多作家で知られ、本書は長編24冊目。短編集も4冊上肢している。22冊目の長編 “The Trees”(2021 ☆☆☆★)は2022年のブッカー賞最終候補作だった。こんどの新作できっと雪辱を果たしたいところだろう。
[☆☆☆★★]『ハックルベリー・フィンの冒険外伝』。といってもハックは脇役で、主人公は黒人の逃亡奴隷ジム(ジェイムズ)。ハックとジムのほか、トム・ソーヤーやパップ・フィン、サッチャー判事など、マーク・トウェインの名作と同じ人物が登場するので、トウェインのファンなら雀踊りしたくなるほど興味を惹かれることだろう。が、名作の換骨奪胎と知らなくても、アメリカにおける人種差別という、もはや文学史的には陳腐とさえいえるテーマから、よくぞこれほど面白い冒険小説を仕立てあげたものと感心させられる。南北戦争当時、ミシシッピ川と流域の町が舞台の逃避行で、ジムは嵐に遭ったり、ガラガラヘビにかまれたり一難去ってまた一難。とりわけ第二部、ハックと離ればなれになったジムが、一見白人に見える黒人ノーマンと行動を共にするあたりから緊張の連続で、あわや蒸気船の外輪に巻きこまれそうになるシーンは圧巻。トウェインの原作とちがってジムは標準英語も読み書き話せ、夢のなかでなんと、ヴォルテールやジョン・ロック相手に自由思想と奴隷制について議論をかわす。が、この新工夫より心にひびくのは、理不尽な鞭打ちやレイプ、家族との離別など、昔ながらの黒人の悲惨な物語である。これにときおりユーモアたっぷりの会話が混じるあたり、さすが多作家らしく手馴れた筆さばきだ。しかし上の自由論をはじめ、戦争の大義や、正義と不正義、過酷な二者択一など、明快な答えのない道徳的難問を小出しにしては引っこめるのはいかにも中途半端。人種差別を痛烈に批判したトウェインのほうが、単純だがよほど真剣な作家だったのではないか、と思えてならない。
今回もまず、現地ファンの下馬評から。少し変化があり、本命 “James”、対抗 “My Friends” に固定。単穴は集計方法のちがいにより、“Creation Lake” か “Held”。
ぼくはいま “James” を読んでいるところだけど、たしかに “My Friends” といい勝負だ。どっちが上かはまだわからない。
“Creation Lake” と、4番人気に落ちてしまった “Playground” は現時点では未発売。なのにランクインしているわけは、ARC(Advance Reader Copy)で読める特定の読者がいるから。いま一般に入手可能なのは “Held” だが、ショートリストの発表(9月16日)前に読むためには、アマゾンUKの最速便で6千円以上もかかる。日本経由では間に合わないようだ。ってことで、ぼくは本命・対抗だけツマミ食い。
さて表題作。本筋についてはレビューもどきでほぼカバーしたつもりなので、きょうは周辺情報その一。「過去と現在が交錯し、微妙な心の動きや、ふと目にした光景に詩情が宿る」。つまり細部がしっかり書きこまれているわけだ。具体例をひろってみよう。
語り手 Khaled はロンドンのリビア大使館前でおこなわれた反政府デモに参加中、館員による銃の乱射で被弾。The bullets sounded. ... What did impress me was the sensation. It literally into me and then ran through me with unremitting force, ... I was now empty and standing, my life reduced to a single unbroken line of a swirl locked inside a child's glass marble. And there it rolled out, that marble, rolled out of me, taking everything with it.(p.86)
これ以前にも詩的描写はあったはずだが、ここではじめてメモ。つぎは、Khaled がある女友だちと会話したあとの場面。Shame ― yes, shame, that's what it was ― cold, imprecise and endless as a moonless sea. Then I saw it in my mind's eye, felt the tug too, as the rope snapped and the anchor was lost to the depths.(p.125)
詳しい状況はさておき、とてもわかりやすい比喩表現で、心情はよく伝わってくるはずだ。つぎもわかりやすい。どんな事件後のことか説明しなくてもいいだろう。I walked off feeling an emptiness well up inside me. It made me want to run away, dive deeper into myself, into that cold desolation, to the very bottom of it, out of whatever it is that attracts us to pain, which tempts us, when we know that a complaining tooth should be left alone, to bite on it.(p.159)
以上は「微妙な心の動き」の例だが、つぎは「ふと目にした光景」。A few weeks later, on a cloudy February afternoon, I was on a bus going along Regent Street when I spotted Hannah and her mother walking on the busy pavement. Hannah seemed under strain but patient. Her mother, walking half a step behind her, looked a little vulnerable, as though all this might be too much without her daughter beside her. Something about the scene affected me very deeply and I still do not know why.(pp.249 - 250)
Hannah は Khaled がこの時点でつきあっていた女性だが、これも不要な情報。不要といえば、そもそもこんな場面は物語の本筋とはまったく関係のないエピソードで、べつに添えなくてもいい。が、添えると、小説としてのふくらみが出てくる。
このくだりを読んでぼくも、ふと思い出した情景がある。調べてみると16年前の冬、恩師の葬儀の行き帰り、バスの車窓から目にした路傍の花が雨に濡れていた。あれはなんの花だったのか。(つづく)
(あるとき恩師と映画の話をしていたら、ルイ・マルの『恋人たち』を評して恩師がひとこと。「あれはすごい映画だったね」)
さていま、あらためて現地ファンの下馬評をチェックしてみると、本書は Percival Everett の “James” と並んで相変わらず首位を併走。三位も Richard Powers で変わらない。
本来ならツマミ食いは禁物で、たとえハズレでも、なぜそれが凡作かと考えることで勉強になる。今年ロングリストにノミネートされた作家でいえば、Claire Messud の “The Last Life”(1999 ☆☆☆★★★)を読んだのはジャケ買い時代。
☆☆☆はもちろん、ひどい場合には☆☆★★の作品に出会ったこともあるが、ここはいいけど、ここはラフ、などと気のついた点をメモしていくうちに、ぼくなりの洋書乱読術が身についたようだ。ときたま、上の本のように未知の作家の未知の佳篇を「発見」した自己マンにひたるのはゴキゲンだった。
とはいえ、いまや年金生活。予算と時間にかぎりがあり、ランダムに手を出すゆとりはない。それにまだまだ、少なくとも英語では訪れたことのない巡礼地が多い。定評のある古典がほんとうにその評価どおりの名作なのか、それをたしかめるのは格別の楽しみだ。いきおい、新作については厳選せざるをえない。
評価といえば表題作、まだ迷っている部分がある。読みはじめてからしばらくは☆☆☆★★だったが、「一朝有事のさい、自由という理想に殉じて帰国すべきか、それとも移住先で確立した地位を守り、勝ち得た信頼に応えるべきか」という問題が提出されたところで、★をひとつ追加。たしかに人気を集めているだけのことはありますな、と感心した。
ところが、その問題がどんどん深掘りされるのかと思いきや、話はあちこちに飛び、それはそれで面白いのだけど、いつのまにかまた、☆☆☆★★にもどってしまった。はて、どうしようか。落ち穂ひろいをしているうちに、めったに変えたことのない点数、変更したくなるかもしれません。
最近のブッカー賞受賞作や候補作とくらべると、 "Shuggie Bain"(2020 ☆☆☆★★★)や "The Promise"(2021 ☆☆☆★★★)、"Small Things Like These"(2021 ☆☆☆★★★)などより、ちょっと弱いかな。でも、"Prophet Song"(2023 ☆☆☆★★)よりはいい。これも迷う材料のひとつだ。
もっとも、ぼくは「しんみりした泣き」のある作品ほど点数が甘くなる傾向があり、だから「泣かせどころ」の比較的少ない表題作には辛くなったのかも。上に洋書乱読術と書いたが、いい加減なものです。(つづく)
(下は、この記事を書きながら聴いていたCD)