Ranun’s Library (original) (raw)
夏から続いていた目まぐるしい日々のため、季節を感じる余裕がありませんでした。
先日、ふと朝のニュースをみると、百万遍にある知恩寺「古本まつり」の映像が流れていた!
そうか、もう11月!
毎年恒例の「古本まつり」に行くことを忘れていたとは、我ながらショックです。
というわけで、今日はお天気も回復したので行ってきました。
この辺りの雰囲気、懐かしいし、やっぱり好きだなあ。
案の定、すごい人の多さ、
(ちなみに、明日まで開催されています)
かき分けながら、じっくり吟味して選んだのはこの2冊。

2冊とも全集なのに1冊しか買えないというお財布事情。
それでも満足度は大きい。
ボルヘスが愛読していたホーソーンは、
「ウェイクフィールド」がとても面白かったので、他も読んでみたくなりました。
カズオ・イシグロが愛読していたチェーホフは、昔「犬を連れた奥さん」を読んで面白かった記憶があります。
本書(全集5)には収録されていませんが「女たち」「決闘」「妻」「モスクワで」「気まぐれ女」というラインナップ。女性がタイトルになっている作品が多いのと、中篇「決闘」を読んでみたかったので、これに決めました。
しばらく積読になりそうですが、積んどくのもいいか~。
読みかけの『薔薇の名前』は、やっと下巻に入ったので、まずはそちらをこつこつ読もうと思います。
ウンベルト・エーコ著『薔薇の名前』を少しずつ再読しています。

( 原タイトル:Il nome della rosa, 1980 )
本作は、中世、北イタリアの修道院で繰り広げられる知と笑のミステリー。
1980年イタリアで出版されて以来ベストセラーとなり、世界中で翻訳されました。
私は最初、映画の世界観に魅了され、小説に手を出したものの、
歴史、神学、哲学、科学、西洋古典の背景知識が乏しくて難解でした。
それでも、単純にミステリーとして楽しめたし、ボルヘス好きが幸いして、なんとか読み通すことが出来ました。
かなりスローテンポで上巻を読み終えたところで、ひと休みして、エーコ自身の覚書、そして様々な解説本を再び読んでいます。
バベルの塔を思わせる「ごたまぜ言語」「つぎはぎ言語」が、多くの古典や聖書の寄せ集めであることの縮図であり、そのことがこの物語の本質にも通じるとうことが、うっすら見えてきたように思います。
本作は、見習い修道士アドソがラテン語で記した手記を、マビヨン師が語り、修道士ヴァレによってフランス語に訳され、さらに著者がイタリア語に訳したという設定。
「覚書」で、著者はこのことを第四レベルの容器に入れたのだと述べています。
つまり書物というものはどれも、すでに語られた話を物語っているのだと。
しかも、書物はしばしば別の書物のことを物語り、書物同士は語り合うのだ、ということをウィリアムに代弁させています。これはまさにボルヘスへの敬意に他ならない。
いろいろかきたいので、続きはまた次回......。

アリストテレスの『魂について』
なんだかそばに置いておきたくて、古本で購入しました。
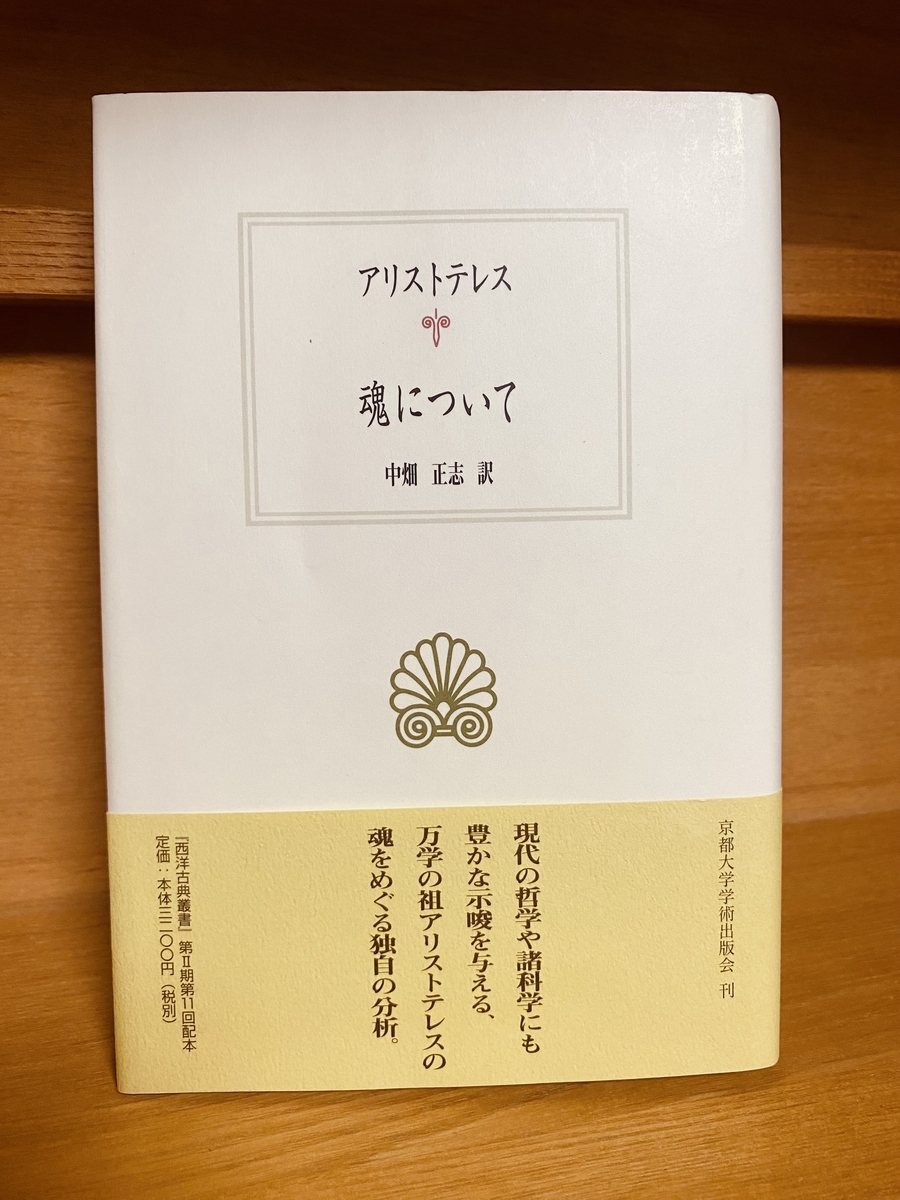
原タイトル Aristotelis De Anima
ラテン語では『デ・アニマ』といいます。
素敵な響きですね~。
難しんだけど、とても読みやすい哲学書です。
訳者解説では、
「これほど思想史上に出ずっぱりの書物も珍しい」
「現代においても、心について考えるために「アリストテレスの復帰」が求められたりもしている」
と述べられていて、現代でもなお読み継がれています。
初めて読んだのは、カズオ・イシグロの『クララとお日さま』を読んだあとでした。
魂とはどのようなものか、
心はどこにあるのか、
生きているとはとはどういうことか、
ということを知りたくて読みました。
本書はアリストテレスの講義ノートのようになっていて、考える道筋を示してくれています。
日々、なにげに感じ、考えることが、
魂と心にどう結びつくのか、
テーマごとに、ひとつひとつ解説されています。
難しいことはわからなし、
読んだからと言って、なにか明確な答えが出せるようなものでもありませんが、
繰り返し読んでみたくなるような、
大切な一冊になりそうです。
「素朴な人」(または「純な心」Un cœur simple )は、
『三つの物語』(_Trois Contes_)に収録されている短編小説である。
「聖ジュリアン伝」(_La Légende de Saint Julien l'Hospitalier_)と
「へロディアス」(_Hérodias_)の3つが含まれていて、
いずれも1875~1877年 に書かれたギュスターヴ・フローベールの遺作である。
「素朴な人」はその名の通り、尊いほど純粋な主人公フェリシテが、未亡人オーバン夫人に仕えた半世紀の物語。
あらすじ
フェリシテは少女時代、両親を相次いで亡くし孤児となった。ある小作人のもとで働くことになるが、つらい経験ばかりだった。そのうえ唯一恋した男性にも裏切られ農場を去る。その後オーバン夫人の召使として雇われ、生涯かけで身をささげる。決して感じが良いとはいえない夫人を支え、とりわけ二人の子供たちには愛情を注いだ。また甥(姉の子)に再会すると、同じように世話を焼き彼らのために奔走した。しかし娘と甥が次々に死んでいく。悲しみを埋めるために鸚鵡(オウム)をプレゼントされるが、ある日オウムがいなくなると、フェリシテは無我夢中で町中を探した。見つかったオウムは間もなく死んでしまい、彼女は心身ともに壊れかけ寝込んでしまう。そんなに悲しいならオウムを剝製にしてもらったら?というオーバン夫人の勧めで剥製にしてもらう。そのオーバン夫人もついに病に苦しみ逝去する。愛するものを全て失ったフェリシテは、悲しみと孤独を癒すため、オウムの剥製を神聖化するようになる。キリスト教の聖体行列の光景を夢見ながら、オーバン夫人の屋敷で死を迎える。死ぬ間際、フェリシテが見たものは、空が開かれていく瞬間と、自分を包み込もうとするオウムの大きな羽だった。
感想
度重なる不運に苛まれるフェリシテであったが、どんな時も彼女は小さな喜び見つけて生きていた。とくにオウム存在は彼女の最大の癒しであった。オウムは人の言葉をおぼえ反復する能力がある。自分が発する言葉をオウムを通して再び受け入れることで、言葉の重みを感じていたのだと思う。正常なコミュニケーションがとれているとは言えないが、それでも心は通じ合っていると思うことで喜びを感じていたのだろう。
そこで、ふと思い出した聖書のことばがある。
人はパンだけで生きるものではない
(マタイによる福音書 4:4)
これは、イエスが40日間断食したときの、サタン(悪魔)との会話に由来する。
サタンは空腹なイエスにこのように誘惑した。
「(あなたが)神の子なら、これらの石がパンになるように命じたらどうだ」
するとイエスはこう返した。
人はパンだけで生きるものではない。神の口から出る一つ一つの言葉で生きる。
と。いくら食べ物(パン)があっても、人はそれだけでは生きていけない。神の言葉によって生きることができるのだ。という教えであるが、まさにこの物語のオウムの言葉は、フェリシテにとって神の言葉だったに違いない。オウムが反復する「アヴェ・マリア」や「フェリシテ」という言葉に、どれだけ励まされたことだろう。オウムはまさしく愛の象徴だったと私は思う。無学だったフェリシテは、オーバン夫人の娘とともにキリスト教を学び信仰を始めたのだった。オウムは剥製になっても「聖霊」と化してフェリシテを励まし、寄り添い続けた。感動的な最期だった。
フローベールといえば『ボヴァリー夫人』だが、私はまだ読んだことがない。解説によると、フローベールは友人の女流作家ジョルジュ・サンドに、次はもっと憐れみの情が滲み出るような作品を書いてみてはどうかと勧められ「素朴な人」を書き始めたという。しかし作品の完成をまたずに友人は逝去した。フロベール自身も『ボヴァリー夫人』で植え付けられたイメージ、すなわち冷徹で意地の悪い観察眼というものを払拭したかったという。次は『ボヴァリー夫人』読んでみたいと思う。
カナダの作家、ヤン・マーテルの『パイの物語』( 原タイトル Life of Pi , 2001 ) を読みました。パイというのはお菓子のパイではなく、主人公16歳の少年の通称です。本作は2002年に英国のブッカー賞を受賞し、2012年には映画『ライフ・オブ・パイ/トラと漂流した227日』が公開されました。
映画のタイトルが示している通り、この小説は、インドの少年パイと、ベンガルトラ(リチャード・パーカー)の、227日に渡る漂流物語であるが、それだけでは終わらない。漂流物語は、主に第二部に集中しているため、第一部と第三部は一見無意味に感じられるが、全てを総合的に読むことで、解釈の幅が広がるように仕組まれている。読み終えたらまた最初に戻って「覚え書きとして」を読み直してみることをおススメする。
始まりは、カナダの作家が小説のネタ探しにインドへ渡った際に出会った老人に「あんたが神を信じたくなるよう話を知っているよ」と、言わたれことに端を発する。その話の張本人というのが、現在カナダに住んでいるというパイであった。作家はカナダに戻り「パイの物語」を聞き、それを小説にしたという、なんだか回りくどい背景がある。
第一部では、少年パイのインドで過ごした日々が、ゆったりと描かれている。父が動物園を経営していたので、パイは動物学や宗教に関心をもっていた。異例ともいえる3つの宗教(ヒンドゥー教、キリスト教、イスラム教)を同時に信仰していた。やがてインドの政権に不満をっていた父が、家族と動物をつれてカナダへ移住することを決意する。第一部は、わりと平和で宗教的な話が心地よく、私の好きなパートである。しかし悠長に読みすぎてしまい、後から伏線のようなものを探しに戻ることが何度かあった。
第二部は、メインである漂流物語となっている。カナダへ向かう途中、日本の貨物船ツシマ丸は沈没してまった。救命ボートに乗せられたのは、パイと、トラ(リチャード・パーカー)、オラウータン、ハイエナ、シマウマだった。シマウマは足を骨折していて、ハイエナに食べられてしまう。それを見たオラウータンはハイエナを襲うが、逆に食べられてしまう。しかしハイエナは結局は最強のリチャード・パーカーに食べられてしまったのだった。家族もみんな死んでしまったため、残されたのはパイとリチャード・パーカーのみ。そこから227日間、命がけの漂流の旅が始まる。頭のいいパイは、リチャード・パーカーを手なずけ、距離を取り、食料を確保し、なんとか生き延びようとするが、照り付ける太陽と飢えで、疲労が限界に達する。途中たどり着いた島はミーアキャットの群れがいる人食い島。再び海に出て、次にたどり着いた島がメキシコの海岸だった。ここでリチャード・パーカーは振り向きもせず、森の中へ消えてしまった。パイは一人きりになり、現地人に救助される。
第三部は、日本人オカモト氏が、ツシマ丸沈没の唯一の生存者であるパイに取材をした時の音源を頼りに、作家が文字お越ししているという設定(これもまわりくどいが、その意味するところは?)。パイは取材に対して、トラとの漂流話をするが、オカモト氏には信じてもらえない。それならと、全く別のアナザーストーリーを作り語ったのだ。
彼と救命ボートに乗ったのは動物たちではなく、船のコックと、台湾の水夫がひとり、そして母親だった。そこで展開された出来事は、吐き気がするほど悲惨なものだった。詳細は割愛するが、よくよく読んでみると、あのとき救命ボートで繰り広げられた、動物が動物を食うということを、人間同士がやっていたのだった(シマウマ→台湾水夫、オランウータン→母、ハイエナ→コック、トラ→パイ という構図)。つまり真実は後者のほうで、パイは悲惨な出来事に蓋をするために、人を動物に見立てて「パイの物語」を創作した可能性がある。
どちらの話なら信じてもらえるというのか? 動物バージョンか、人間バージョンか? パイは正直にオカモト氏に突き詰める。オカモト氏が選んだのは、動物バージョンだった。すなわちオカモト氏も同様、悲惨な現実に目を背けたかったのだ。信じられないほうを、あえて信じようとした。神を信じたくなくなるような話とはこのことだ。オカモト氏は「動物バージョン=真実=パイの物語」だと結論づけた。嘘だとわかっていても、これはパイのためでもあった。パイの心を傷つけないよう、今後強く生きていけるよう、彼なりの配慮だったかもしれない。
*******
なにかを話せば、必ず物語になる。
なにかを語るということは、すなわちなにかを創作すること。
人生は物語にすぎないのだから。
パイは、こんなこともいっていた。
救助されること以外でぼくが何より欲したのは本だった。
決して終わることのない長い長い物語の本。
何度でも読み返すことができて、
そのたびに新鮮で新しい発見がある本。
彼には物語が必要だったのだ。なにも持ち合わせていないなら、自分でつくればいい。そうすることで精神的な支えが得られると知っていたのだろう。それは、困難な状況においても希望や慰めを求める人間の本能だ。3つの宗教はどうだったか。どの神も救ってはくれなかった。神を愛することは辛い、しかし愛そうとすることで慰めにはなっただろう。
生きるか死ぬかの究極を迫られたサバイバルにおいて、パイの精神力は尽きかけていた。眠ろうとすれば現実の夢とが混ざり合う。そのためだろう、パイが作った物語は断片的なエピソードが組み合わさり、日記調になっていたのが印象的だった。
第三部のパイの話に、どんでん返しをくらったが、取材をしたオカモト氏とその部下の態度にも面食らった。つらい過去の出来事と、取材時のブラックユーモアは、相反するものに思えるが、これこそがこの物語の本質ではないかと思えてくる。
どんな証言(物語)を話しても、沈没した原因はわからないし、家族も戻ってはこない。言い換えれば、どちらの物語でも船は沈み、家族は死ぬ。結果が同じなら、たのしい物語のほうがいいじゃないか。宗教と同じく選択肢はひとつでなくてもいいのだから。
重要なことは、自分の経験が人々に影響を与え、記憶に残るものであってほしい。そこに魂を感じてもらえたら、こんなに嬉しいことはない、そんなパイからのメッセージが聞こえてくるような最後だった。


