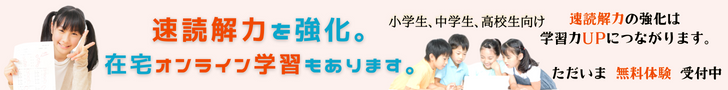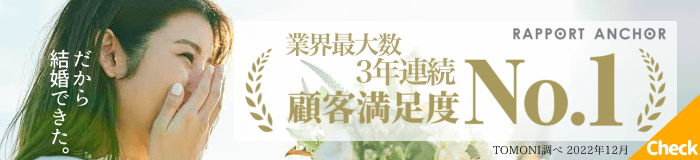★よし★の雑記ブログ (original) (raw)
(みんなのお題より)
この「お題」シリーズ、なんだかんだで7投稿目です(笑)
やってみるとなかなか面白いですね。
僕の「〇〇恐怖症」、じつは2つあります。
ひとつは「高所恐怖症」、もうひとつは…。

まじで無理!犬恐怖症!
僕が非常に大きな恐怖を感じる対象。
それは犬です。
無理無理!
犬を目の前にして「ワンちゃん」なんて呼べるほど、気持ちに余裕はありません。
とにかく怖い、怖すぎます。
中でも大きい犬は絶対無理!
妻は「大きい犬の方がおとなしいよ」なんて言いますけど、そんな問題じゃないんです。
見た目の問題です。
で、なぜ無理なのかというと、子供の頃非常に怖い思いをしたからです。
小学校3年か4年のときの出来事。
近所で学校の友達と自転車に乗って遊んでいるときに、放し飼いされていたのか逃げてきたのかわからないんですが、1匹の白い大きな犬に出くわしたんです。
僕も友達もお互いに「怖い」と感じたみたいで、ふたりで自転車を全力で漕いで坂道を下って逃げたんです。
で、犬って、逃げると追いかけてくるじゃないですか。
ふたりとも半泣きで自転車を必死で漕いでいたときに、お互いの後輪がからまって、ガッシャーン!!
僕も友達も派手に転倒し、腕や足を豪快に擦りむいたんです。
でも、それで終わりじゃないですよね?
すぐ近くに恐怖の犬がいるわけですから!
ふたりして「ギャーッ!」と泣きました。
これは擦りむいた痛みで泣いたのではないことはわかっていただけると思います。
そう、痛みを感じている暇なんてないんです。
目の前の恐怖のほうが何倍も上回っているんですから。
ものすごく幸いなことに、僕たちが転倒した場所のすぐ近くに1人のおっちゃんがいて、そのおっちゃんが犬をうまく追っ払ってくれたんです。
で、軽トラの荷台に僕と友達と自転車2台を乗せて、僕の家まで送ってくれたのでした。
「また来たらどうしよう」と怯えながら乗っていましたね。
ここまで鮮明に記憶に残っているんですから、それだけ僕の人生において衝撃的な出来事上位だったと言うことができます。
犬は元々好きではなかったんでしょうけど、このような非常に怖い思いをしたことで、絶対的に受け付けなくなってしまったというわけです。
「トラウマ」ってやつです!
でもね、皆さん。
僕は犬種によっては全然大丈夫なワンちゃんもいるんです。
今度は「ワンちゃん」って呼んでますね(笑)
「犬がダメ」とはいっても、じつは全犬種拒否ではないんです。
もしかしたら、ミックス等も含めると、1種類だけではないのかもしれませんが、「この犬だけは絶対的に大丈夫」という犬種があるんです。
さて、その犬種とはなんでしょう???
気が向いたら当ててみてください(笑)
僕からのお礼のスターが15個ついていたら正解です(笑)
普通にコメント or ブックマーク上でコメント、どちらでもOKです。
ではでは。
最後まで読んでいただき、ありがとうございます!
また当ブログに遊びに来てください!
当ブログは「にほんブログ村」のランキングに参加しております。
上のバナーをポチッとひと押し、応援をお願いします!
こんにちわ!
★よし★です。
昨晩、我が家の中2娘に夫婦そろって説教を食らいました。
延々と1時間以上も。
原因は僕たちにあります。
「なぜ説教されたのか」はさておき、娘の内面的な成長にものすごく驚かされました。
僕は失礼ながら、娘くらいの年齢の子だと、カーッとなって一気にまくし立ててくるイメージを持っていたのですが、そんなことはありませんでした。
終始、冷静沈着で淡々と相手を諭すような話しっぷり。
言葉や言い回しも「本当に13歳か?」と思ってしまったほど。
指摘もズバリ的を射ており、僕たちは何も反論できず、素直にゴメンナサイしました。
子供って、すごいですね。
子供は本当に親をよく観察しているな、見られているな、評価されているな、と感じずにはいられませんでした。
例えるなら、心理カウンセラーさん等の専門家の方と話しているようでした。
僕や妻の性格や特徴を深いところまで把握しており、それぞれの「いけないところ」を大人が使うような言葉や言い回しを巧みに操り、理路整然と、的確に指摘してきました。
こちらへの配慮を感じさせる言葉も随所に織り交ぜながら、です。
娘に言われました。
「私もう、お父さんが思っているほど小さくないよ」と。
こちらが驚いている様子が伝わったんだと思います。
マジメな話、「何を言っているんだ、ガキのくせに」などとは到底思えませんでした。
我が家の子達に限らず、子供のすごさは今まで事あるごとに感じてきましたが、昨日は改めてビックリしました。
鋭い洞察力&語彙力&巧みな話術等をどうやって身に付けたのか、妻と話し合ってみました
娘は本が大好きです。
中でも小説を好んで読みます。
子供らしくマンガも読んだりしますが、娘によるとマンガより小説のほうが好きだとのことです。
登場人物の心情をしっかり読み取りながら、本を読み進めているのかもねと妻と話していました。
そういえば、いつだったか娘が読んでいた小説について「どんな内容の本なの?」と聞いた時に、話し出したら止まらないくらいに自分の言葉でわかりやすく説明してくれたことがあったことを思い出しました。
その時も、内容を把握する力、説明する力に驚かされたものです。
それから、日々スマホでいろんな動画を視聴していることも無駄ではないのかもしれません。
人が話している動画を継続して見ている(=聞いている)うちに、だんだんといろんな言葉や言い回しが自分の脳に刻み込まれ、それを自然と使いこなすようになっているとも考えられます。
スマホを持っている子供って自然と動画視聴の時間が長くなりがちで、それは問題でもあるのですが、すべてを否定的に捉えるべきではないのかもしれません。
僕の勝手な想像ですが、動画配信者の中には早口で話す人も多いので、それを日々継続的に聞き続けることで速聴能力のようなものも鍛えられるのかもしれないなとも思っています。
速聴能力が鍛えられると、頭の回転や言語処理のスピードが速くなり、話の内容を瞬時に詳しく理解できるようになるばかりか、相手が話している途中でも「話し終わったら次自分はこう返そう」と先の返答を頭の中で準備できるようになる気がしています。
つまり頭が良くなる?
大げさですかね?(笑)
でも僕はあながち間違った考えではないと思っています。
これをリアルな世界で発言したら、「あいつ、また変なことを言いだしたな」って声があちこちから聞こえてきそう(笑)
普段、周囲からそういう目で見られることもあるにはあります(笑)
娘の長所を大事にしてあげたい
説教された時に感じたことって、言ってみれば娘の「長所」だと思うんです。

長所を伸ばすきっかけを作ってあげたり、子供に自分の長所を気づかせてあげるのも親ができることのひとつかなと思います。
その「長所」がいずれ将来の進路選択に関係してくるかもしれません。
「自分の長所が何であり、それはどのように活かせるのか」ということを考える時って必ず来ますよね。
自分ではなかなか気づかない「長所」も、人から褒められたりすることで自ら認識するようになると思うんです。
我が娘よ、社会でその長所を活かせる場面や職業、しっかりありますよ!
言われて言い返しての親子ゲンカをするより、まずは子供の話を聴いてみることが大切だと実感
ただのケンカになってしまっては、見えるものも見えなくなります(もちろん、前向きな親子ゲンカというのも存在するとは思っています)。
子供が一生懸命話しているのに、親が「生意気だ」で終わったり、話をまともに聴かないとあっては、子供に大きなストレスが残るだけで、そこから生産されるものは何もないでしょう。
それから、子供が話している途中で話をさえぎって自分の話したいことを先に話そうとするのも✕だと思います。
そのうち、子供も諦めて何も話してくれなくなるか、ある程度成長した段階で溜まりに溜まった不満を大爆発させる時期がやってくると思います。
僕の親が「話を聴かない」親だったので、僕はそういった過去から学んだことを現在の子育てに活かすべく、日々子供と接しています。
あんな思いは絶対にさせたくありません。
娘には感謝しています。
僕たち夫婦にとっても自らを見つめ直すいい機会が得られたと思います。
そして、娘との関係も以前より良くなりました(悪かったわけでもないのですが)。
娘は僕たちが話をちゃんと聴いて理解を示したことを、好意的に受け止めてくれた様子です。
「反抗期だから」とか「生意気なガキだ」等で済ませることなく、きちんと向き合えばちゃんと親子でわかり合えるのかな、と改めて感じたことが昨日の収穫でした。
娘、ありがとうな。
わが子のやる気を引き出す伝え方・励まし方がわかる!伝え方コミュニケーション検定 
当ブログは「にほんブログ村」のランキングに参加しております。
上のバナーをポチッとひと押し、応援をお願いします!
こんにちわ!
★よし★です。
息子も高3(私立高)になり、学校側からの連絡や配布物も今までより増えてきました。
先日、保護者向けの進路説明会があったり、奨学金の資料が配られたりと、受験がらみの情報が多くなってくると「いよいよその年なのか」と保護者の気持ちも自然と「受験モード」へと切り替わってきます。
長かった小学校の6年間と比べると、中学校や高校の3年間などはあっという間です。
ついこの間、入学式に行ったばかりなんですけどね。
いろいろ思い返してみると。
当時はコロナの影響で保護者の入場制限がかかっており、中学の卒業式は妻だけが行き、そして高校の入学式は僕だけが行きましたね。
さらに遡ってみると、息子が小学校6年生の時、みんな本当に最後の最後で学校に登校できなくなってそのまま卒業式を迎えたので、当時の6年生クラスを受け持っていた先生方も、この年の卒業生のことは特に印象に残っているのではないでしょうか。
コロナの流行で受験も変わり、授業も変わり、働き方も変わり…世の中そのものが本当にいろいろと変わりました。
そんな時代を生きてきた息子が高3になり、いよいよ大学受験を迎えます。
1.基本は一般受験
息子は普通科ですが、所属しているコースの問題もあって、基本は一般受験で大学を目指すことになります。
推薦等の可能性がまったくゼロとは言い切れませんが、コース上制限が設けられており、9割~9割5分がた、一般受験になる見通しです。
文系だった僕とは正反対の理系(私立)なので、英・数・理が柱になってきます。
それと、場合によっては「情報」も。
1月に共通テストを受け、その後、各大学の選抜試験を受けることになります。
2.模試が本当に多くなる&各模試間での「偏差値」の違い
今年度は、模試の受験回数も増えてきます。
一般受験をする以上は、学校の中間・期末といった校内の試験以上に、模試での「偏差値」に着目することになります。
模試での「偏差値」がその子の真の実力を表す数値。
まぁ、そりゃそうですよね。
僕も高校生の時「進研模試」とか「河合塾」の模試とか受けましたね。
「進研模試」というのは、全国のいろんな学校・いろんな受験生が受験するので、河合塾の「全統模試」よりもずっと受験者数が多い模試。
受験する生徒が所属する高校の偏差値も低~高と幅広いので、イメージとしては全国の1位から最下位までを決める模試、といえそうですね。
その進研模試と比較すると、河合塾の「全統模試」は受験する生徒の平均学力が高くなるそうです。
ですので、偏差値が高めに出るのが「進研模試」、低めに出るのが「全統模試」。
そして、今年度は今までよりも模試の受験者数は増えてきます。
今まで受けていなかった人たちも参戦してくるので、それによって偏差値は思うように上がらなくなってくることが予想されます。
つまり、頑張っても頑張ってもなかなか簡単には偏差値が上がらず、受験生にとっては非常につらく大変な時期となるのだと思います。
このあたりは僕らの時代も同じようなことが言われていましたね。
努力してもなかなか結果に結びつかない、報われない。
そんな中でも強い信念を持ってやり抜かないといけないわけで。
大変だと思います。

3.私立高校は設備環境も良く、指導・サポートも手厚い
息子は幼稚園の頃から比較的、担任の先生には恵まれてきました。
高校の担任の先生も非常に生徒をよく見てくれていて、子供の特徴をしっかり把握してくれている印象です。
話せばわかります。本当に良い先生です。
学校としての普段の学習指導も充実しており、プラスアルファの金額で補修講座が用意されていたり、自習室環境もいろんな意味で充実しています。
私立高校って、公立と比較して入学金や制服代等も高いので、費用面においては、高校入学時点ですでに大きな差が出ています。
さらに「無償化」といっても純粋な「授業料」の部分が無償化の恩恵を受けられるだけで、その他さまざまな名目でかかってくる費用まですべて都道府県や国が支援してくれるわけではありません。
が。
公立高校に通っている生徒が、さらに塾通いをした場合を考えてみると…。
高校生の塾代、めちゃくちゃ高いですよね。
で、それも月々の授業料だけで済むはずもなく、季節講習や特別講習費なども別途かかってくるので、それらが3年間積み重なってくると、とんでもない出費となります。
場合によっては、私立高校を大きく超える出費になってくるケースも充分あり得ます。
そう考えると「公立+塾となるくらいなら、最初から私立高校に入れてしまって、手厚く見てもらったほうが良い」と話していた先輩保護者の方々の意見も、今になってすごく納得感があります。
僕は自分が公立だったのですが、塾には行っていませんでした。
塾に行かなくて済むのなら、公立はとにかく安く済むと思います。
家計は大助かりです。
息子も公立を目指していました。
ですが、おそらく息子の場合は最低でも英語1科目は塾のお世話にならないといけなかったと思います。
そして彼の場合、最後まで1科目のみの受講で通せる状況だとも思えないので、結局は大きな塾代がのしかかって来ることになったと予想されます。
そう考えると、我が家の場合、私立に進学したのは彼にとっても親にとっても正解なのかもしれません。
4.親として過度な期待はかけていない
息子にはバカ正直に話したりはしませんが、僕は「現役合格」にはこだわって欲しいとは思っていますが「何が何でも上位校に!」などとは思っていません。
周囲の評判も気にしてはいません。
過度な期待をかけるというのは、一歩間違えると本人をつぶすことにもなりかねないのです。
息子にも「どこに行くか」以上に「そこで何をするか」にこだわって大学・学部学科を選んで欲しいと思っています。
もちろん、行きたいところへの合格を少しでも確実にするために、より偏差値の高い大学・学部学科を目指して努力することの大切さは息子も理解しています。
なかなか大きな成果は出てきませんが、それでも息子は日々コツコツと頑張っていますので、結果以上に経過を認めてあげたいと思っています。
大学受験は子供の試練でもあり、親の試練でもあります。
まだまだこれから、本人も親ももっともっとピリピリする時期がやってきますが、表面上はできる限り普段通り接して、一番大変なのは息子本人であることをきちんと理解した上でコミュニケーションを取って家族一体となって息子を支えていきたいと思います!
当ブログは「にほんブログ村」のランキングに参加しております。
上のバナーをポチッとひと押し、応援をお願いします!
先日、仕事で疲れて帰宅した僕に、中2娘から思わぬプレゼントが!

横浜くりこ庵のたい焼きです!
いやぁ、うれしいなんて言葉では足りません!
「愛娘」からですからね(笑)
テンションMAX⤴️⤴️
疲れなんて吹っ飛んじゃいます💪
横浜くりこ庵のたい焼き、娘の大好物で小さい頃、外出先でよく買ってあげてたんですよね。
笑顔でもぐもぐ食べる姿がとても可愛かったです🤗
で、今度は成長した娘が自分の小遣いで買ってきてくれたんです🥰
娘は現在、反抗期真っ只中ですが、そんな中でもこうした優しさを見せてくれることがあります。
ありがとう!
反抗期、落ち着いたらまた一緒に出かけような!!
当ブログは「にほんブログ村」のランキングに参加しております。
上のバナーをポチッとひと押し、応援をお願いします!
(みんなのお題より)

人生で一番やり込んだゲーム!
コレですね!
PCエンジン(HuCARD)「カトちゃんケンちゃん」!!
リンク
アクションゲームです。
ゲーム内では、カトちゃんとケンちゃんは「迷探偵」という設定。
事務所に電話がかかってきて、誘拐事件を解決してくれという依頼!
フィールド上の敵を倒し、障害物を蹴散らし、ボスを倒し、最終的にさらわれた人を助け出そうというゲームです。
このゲーム、カトちゃんでプレイするかケンちゃんでプレイするかを選択できます。
カトちゃんよりケンちゃんのほうが足が速いのですが、停止させようとすると滑るんです。
なので僕は足元が安定しているカトちゃんでプレイします。
ケンちゃんで全クリアできる人がいるとすれば、相当な上級者だと思います。
ゲームエリアは全6フィールド24エリア。
1-1からゲームがスタートし、6-4が最終面になります。
最初はわかりませんが、慣れてくると途中、ワープが可能だということにも気づくようになります。
ゲームの難易度は超高いと思います。
はっきり言って、難しいです。
それをどうにかクリアしてやろうということで、めちゃくちゃやり込みました。
で、クリアできるようになった頃にはかなりのテクニックが身に付いていて、周囲の友達はそれを「神業」(かみわざ)と呼ぶようになりました。
最初にクリアしたときは、それなりの達成感がありましたね(笑)
今でもPCエンジンは自宅にあります(笑)
CDロムロムもあります!
息子が小学生のとき(まだコロナ前)、我が家にたくさん友達が来てゲーム会みたいなのをやっていたんですけど、やはり男の子って格闘系のゲームが好きみたいですね!
これが大好評で、超~盛り上がっていました!
「スト2」ってやつですね。
リンク
このゲームも楽しかったようです。
人生ゲームです!
リンク
あとはコレ。
対戦ゲームの定番「ボンバーマン」!
リンク
PCエンジンというゲーム機が子供達には新鮮だったみたいですし、人数が集まればやっぱり対戦ゲームが盛り上がります!
僕がひとりで盛り上がっていたゲームもあります。
高校生くらいの時だったかな。
リンク
息子もやっていました(笑)
30歳くらい歳の離れた息子でも「面白い!」と感じたようです。
なんかいいですよね。
自分が子供の頃に楽しんだゲームを、長い年月を経て、今度は子供達と一緒に楽しめるって。
カトちゃんケンちゃんの話から、いろんなゲームの話になってしまいましたね(笑)
すみません、ついつい自分が楽しくなってしまいました。
今は、ほとんどゲームはしませんが、時々家族で桃鉄やら遊々人生やらをやっています。
スト2で娘と対戦し、娘をいじめることもあります(笑)
息子や娘がやっている最新のゲームには正直ついていけていないところがありますが、桃鉄みたいな長続きしているゲームなんかは、特別な難しい操作もいらないし、大人も子供も楽しめますから、家族間のコミュニケーションを深めるのに最適ですよね!
桃鉄シリーズは、ずぅ~っと続いて欲しいと思います。
※関連記事
●おまけ●物価高に負けるな!ゲームを楽しみながら節約生活へ!
ゲーム好きの方。
せっかくゲームを楽しむなら、ポイントを貯めてAmazonギフト券・Dポイント・Vポイント・Pontaポイント等に交換して買い物時の足しにしませんか?
ゲーム以外にも、クレジットカードの作成等、ポイントを大量獲得できる案件も。
まずは以下をクリックして説明を読んでみましょう。
ポイントを貯める手段もいろいろ、交換先もいろいろです。
ご自分に合うポイントの貯め方があれば、節約への第一歩になると思います。
当ブログは「にほんブログ村」のランキングに参加しております。
上のバナーをポチッとひと押し、応援をお願いします!
こんにちわ!
★よし★です。
この間妻の買い物に同行して、ふとお店の棚に目をやると、そこには。

よっちゃんいか!
この「よっちゃんいか」には思い出があります。
僕は城下町で育ったのですが、城のお堀にザリガニが住みついていて、小学生の時に何度か友達とザリガニを釣りに行ったという思い出です。
うちの場合は「ザリガニ釣りに行きたい」とか親に話すと面倒なので、それが良いことか悪いことかは別として、僕は内緒で行っていました。
(よい子の皆さんは、決して真似しないでください。場所によっては危険な場合もあります!)
なかなか楽しかったですよ、ザリガニ釣り。
そこにザリガニが存在してさえいれば、コツさえつかめばちゃんと釣れます。
エサはよっちゃんいか。
何種類か試した中では、これが最高のエサだと思いました。
他のいかに比べて、よっちゃんいかに対する食いつき方は特別なものがありました。
よっちゃんいかにはよだれを垂らして食いついて来るような印象があります。
で、そのよっちゃんいかをたこ糸で結んで固定し、水中のザリガニに近い場所にひょいと入れると、ザリガニ君のほうからいとも簡単に来てくれたものです。
で、食い付きを確認したら、ゆっくりゆっくり、そーっとそーっと糸を引き、手元に近づいたら「捕獲」です!
(引きが強いと逃げられるので注意!)
当時は手でつかんで捕獲していました。
「やったあ!」となります。
なかなかの満足感ですよ、あの瞬間は。

※画像はイメージです。
あらかじめお堀の水を虫かごに入れておき、そこに釣ったザリガニを入れて持ち帰ったものです。
今は時代が違うのかな。
なかなか周囲からザリガニ釣りの話を聞くこともありませんし、ザリガニもいろいろと生態系上の問題があって、現在は販売や放流が規制の対象となっているようですね。
昔の子供と今の子供の遊びももちろん違います。
でも、昭和生まれの子でザリガニが生息している所に住んでいた人たちって、それなりにザリガニ釣りを楽しんだ経験があるのではないでしょうか?
僕なんかが通っていた小学校では、クラスに水槽が設置されていて、釣ったザリガニを学校に持って行ってみんなで世話をしたものです。
今も小学校によっては水槽があって、メダカやカメなどを飼ったりしているケースはあるようですが、ザリガニの飼育は僕の周りでは聞かなくなりました。
小学生として昭和のあの頃に戻れるなら、もう一度、当時の友達とよっちゃんいかでザリガニ釣りを楽しみたいです!
当ブログは「にほんブログ村」のランキングに参加しております。
上のバナーをポチッとひと押し、応援をお願いします!
こんにちわ!
★よし★です。
皆さまは、自分が生きていく上で大切にしている言葉、戒めにしている言葉、拠り所としているような言葉などはありますか?
僕にもあります、そのような言葉。
「座右の銘」というやつですね。
今日はそんな話ができたらと思います。
1.「座右の銘」について
まず、この言葉の意味を改めて調べてみました。
※「実用日本語表現辞典」記述より
座右の銘とは、いつも自分の身近に書き記して、自分の戒めとする言葉のことである。
慣用句や故事、ことわざなどの中から選ばれることが多い。
簡単に言うと、自分が生きていく上で大切にしている言葉のことである。
座右の銘の「座右」とは座席の右側のことで身近、そば、かたわらといった意味を持つ。
「銘」は戒めなど心に刻みこんだ言葉のことである。
このように書かれています。
自分にとっての「理念」だったり「軸」となるものですよね。
企業の面接でも聞かれることがあるようです(僕は経験ありませんが)。

2.僕が誰かに「あなたの座右の銘は?」と聞かれたら
僕なら迷わず「凡事徹底」(ぼんじてってい)と答えます。
漢字から推測すると非常に地味な言葉ですよね。
でも僕はこの言葉、生きていく上でとっても大切にしています。
まず、「凡事徹底」の意味から。
※「実用日本語表現辞典」記述より
なんでもないような当たり前のことを徹底的に行うこと、または、当たり前のことを極めて他人の追随を許さないことなどを意味する四字熟語。
やはり一見、地味な印象の言葉です。
ですが、凡事を徹底し続けると、それがやがて大きな成果を生み出したり、周囲からの信頼獲得につながっていくということを、僕自身も経験を通して学んできました。
ですので、もし僕が企業の採用担当者の方などから「座右の銘は何?」などと聞かれたら、派手な言葉やビッグマウス等は性格的にも合わないですし、地味でありながらも実はとても強い言葉である「凡事徹底」と即答します。
3.さまざまな場面における「凡事」の徹底
例えばスポーツ。
あらゆるスポーツにおいて、基礎練習の徹底って本当に大切ですよね。
基礎練習も「凡事」のひとつだと思います。
個人競技であれ、団体競技であれ、うんざりするほどの基礎練習を何千回も何万回も繰り返し、身体に染み込ませることで、試合中にそれが必要な場面になったときに自然と練習の成果が出る、そんな経験ありませんか?
スポーツの種類によるのかもしれませんが、試合中のさまざまな場面で、その都度その都度頭で考える暇ってないことも多いですよね。
「普段の反復練習で身体に覚えさせることで、いざというときにとっさに出る」という感覚ではないでしょうか。
僕もいくつかのスポーツを経験してきましたが、頭で考える以前に身体がとっさに反応するんですよね。
そのための日頃の反復トレーニングであり、日頃からの凡事徹底であるということになるかと思います。
強い選手、強いチームって絶対に皆、凡事を徹底していると思います。
「巧者」「テクニシャン」と表現される選手であっても、基礎練習を誰にも負けないくらい徹底した、その上でのさまざまなテクニックの習得なんだと思います。
勉強もそう。
例えば英単語や英熟語をコツコツと覚えていく作業、地味ですがとっても大変なトレーニングだと思います。
スポーツでいう「基礎練習」に該当し、また「凡事」でもあると思います。
英語の勉強も、うんざりするほどの単語や熟語の練習が必ず伴ってきますよね。
それを投げ出さずにやり抜ける人が成果を出していく。
これも凡事を徹底し続けた成果になると思います。
仕事でも凡事徹底は大切だと思います。
例えば、ショップの入り口から窓ガラス、店内の床、カウンターからトイレの隅々まで清掃が行き渡っていて、壁の掲示物も最小限できれいにまとまった貼り方がされているお店って、客からしたらとても気持ちが良いですよね。
そんな店内で、店員さんが笑顔で出迎えてくれて、丁寧で誠実な接客をしてくれたら「ここで買いたい」「この人から買いたい」そう思いますよね。
これもひとつひとつのことはいずれも「凡事」だと思うんです。
それを徹底した結果が「成約」「リピート」「周囲からの信頼獲得」といったさまざまな成果につながっていくのだと思うんです。
このように「凡事徹底」という言葉は、地味な印象ではありますが、じつはとっても強い言葉。
大きな成果や信頼獲得につながる可能性を無限に秘めた言葉だと思うんです。
だから僕はこの「凡事徹底」という言葉がとても好きですし、今も、これからもずっと自分にとっての「座右の銘」であり続けること間違いなしです!
よかったら、皆さまの「座右の銘」なども僕に聞かせてください!
リンク
リンク
当ブログは「にほんブログ村」のランキングに参加しております。
上のバナーをポチッとひと押し、応援をお願いします!
お題「みなさんは賃貸派ですか? 持ち家派ですか? 最近家を買ったのですが、家の間取りを見るのが好きでいろいろな家に住める賃貸も改めて魅力的だなと思いました。皆さんはどちらですか?」
(みんなのお題より)

僕は断然、持ち家派です。
ある程度の広さの庭があって、花や木を植えたり、野菜を育てたり、といった生活に憧れておりました。
庭なり駐車スペース等でバーベキューなんかもできたらいいな、と思っておりました。
最初は庭の大部分を畑にすることも検討したのですが、さまざまな事情から断念し、現在は端っこの花壇を除いて大半が人工芝で覆われております。
子供が小さい頃はそこに寝転がったり滑り台等の遊具で遊んだりしていたのですが、今は特別何かがあるわけではなく、ただ人工の緑地が広がるのみです。
犬でも飼っていれば、庭部分をネットで覆うなりして、犬を思いっきり走らせ、遊ばせることもできるのですが、現在犬は飼っておりません。
まぁいずれにしても、やはり持ち家だからこそ周囲に気を遣わずに自由にできることというのはありますよね。
それから。
持ち家ならば、いつかは毎月のローン返済から解放される日が来ます。
老後の生活を考えると、生活の拠点に毎月高いお金を払うことがなくなった上に、それが「資産」として自分の手元に残るというのは非常に大きいです。
そういった現実的な側面から考えても、自分は持ち家派ですね!
当ブログは「にほんブログ村」のランキングに参加しております。
上のバナーをポチッとひと押し、応援をお願いします!
当ブログにお越しいただき、ありがとうございます!
★よし★と申します。
雑記ブログを運営しておりますが、さまざまな理由から子育て系の記事を書くことにも力を入れております。
今回は「経験が子供を鍛え、強くする」ことについて書いてみようと思います。
過去にも似たような記事は書いておりますが、また別の切り口からということで、ぜひ最後までお付き合いいただければと思います。
1.遊びその他の経験は社会を知るきっかけにもなる
子供もある程度の年齢になると行動範囲や交友関係も広がり、結果として遊びの選択肢も増えてきます。
近所の子や同じ幼稚園・小学校に通う子たちと家の前や近所の公園で遊んだり、親がどこかに連れて行って親の管理下で遊んでいた頃とは変わってきますよね。
自分たちで電車に乗って多少遠くまで出かけたり、自分たちでお店を予約して外食を楽しんだり、親から離れて友達とカラオケ・ボーリング・遊園地等に行ったり。
そういったひとつひとつの積み重ねって、子供の能力を少しずつ高めていると思いませんか?
電車の乗り方を覚えたり、SUICA・PASMO等について理解を深めたり、店の予約のしかたを覚えたり、カラオケ機器の使い方を覚えたり、いろんな施設のシステムを頭を使って理解したり。
また、コンビニでの買い物ひとつにしても、いろんなキャッシュレス決済について理解を深めるきっかけにもなると思います。
我が家には現在高3の息子と中2の娘がいますが、子供にも付き合いというものがあり、毎月一定額の小遣いは与えておりますが、その範囲でのやり繰りが厳しいとなれば、ポイントやクーポンを有効活用したり等、頭を使い工夫を凝らすようにもなってきます。
ネットショッピングにしてもそうです。
特に息子はアマゾンで時々買い物をしますが、ポイ活で貯めたポイントをアマギフに換えたりして節約をしようという意識がすっかり定着してきました。
また、荷物の受け取り方法についてもちゃんと知っていて、ローソンで受け取れることや宅配ロッカー(PUDOやAmazonロッカー)への配達を希望することで「親に内緒で買い物をしようと思えばできる」などと冗談交じりに話してきたりもします。
子供は遊びその他の経験を通して社会を知り、さまざまな能力を身に付けていくことがはっきりしていると思います。
日頃の経験が、血となり肉となっていくのではないでしょうか。
我が子達も、親より詳しい分野、たくさんあります。
2.制約をしすぎても子供は成長しない
息子が中学生のとき、なかなかの人数の友達と一緒に食べ放題のお店に行ったとき、ドリンクバーを注文していないのにソフトドリンクをコップに入れて席に戻ってきた子がいたそうです。
注文をする際に「ドリンクバー頼む人~?」と聞かれて、その子は挙手をしなかったのだとか。
思わずツッコミを入れたようです。
「お前、何やってんの?ドリンクバー注文してなかったよな?」
周りの友達も「何ボケてんだよ(笑)」となったそうです。
が、その話を聞いた僕は思いました。
その子は「ボケている」のではなく「わからない」のだと思います。
経験が不足していて「右も左もわからない」のだと思うんです。
その子は両親が厳しくて、普段は行動範囲が制限されたりしている子なんです。
たまたまその日は学校行事の打ち上げで息子たちに誘われて「みんなが行くから自分も行きたい」と親に話した結果、珍しく行くことを許されたという話だったみたいです。
とても裕福な家庭の子なんですが、よくよく思い出してみると家族で外食などはあまりしないという話をその子のお父さんから聞いたことがあるような気がします。
その子にしてみれば、周りの友達が皆好きな飲み物を入れて席に戻って来る様子を見て、自分も周りと同じことをやっただけなのだろうと思いました。
なんの悪気もないですよね。
それぞれの家庭の教育方針というのもあるのですが、こういったケースもあるので、僕も妻も、我が子達にはある程度の経験はさせていかないとな、と再考するきっかけになりました。
3.経験が自己肯定感を高め、社会に出ることへの自信にもなっていく
子供が社会のさまざまなシステムを知っていくと自信になり、自己肯定感は高まっていくと思います。

「右も左もわからない」「自分に自信がない」という状態だと、きっと高校生や大学生になってバイトの応募をするのもかなりの抵抗があるのではないでしょうか。
「自分にできるだろうか。不安しかない。できなかったら恥ずかしい。こんなこともわからないのかと思われないだろうか。」
というのと
「ある程度の予備知識はある。今までいろんな経験をしていろんなことを覚えてきた。最初わからないことがあっても、順次覚えていけばいい。」
というのでは、かなりの違いがあります。
社会に出ることへの不安というものは、大なり小なり学生なら誰でもあるとは思いますが、いろんな経験をしておけばその分不安も軽減されることは間違いないと思います。
4.小さいうちから年齢や能力に応じてさまざまな経験をさせていくのは大切だと思う
親として、子供の社会に適応できる能力をコツコツと育てていくことはとても大切な仕事だと思っています。
親が手を出さずに子供に経験させた方がいいことは、どんどん子供に経験させる。
時には子供を信じて一任する。
子供が親より詳しいことは、自分で調べずにあえて子供に聞く。
そんな姿勢で子供と接していこうと思っています。
「すごいな」「やるな」と言われれば子供もうれしいし、自己肯定感アップにもつながりますよね。
わが子のやる気を引き出す伝え方・励まし方がわかる!伝え方コミュニケーション検定 

学力の向上だけに偏らず、我が子が社会に出た後のことをイメージして子育てすることもとっても大切なことだと思います。
「学力」と「社会人力」をバランス良く育ててあげたいと思っています。
※関連記事
こちらもぜひお読みください。
当ブログは「にほんブログ村」のランキングに参加しております。
上のバナーをポチッとひと押し、応援をお願いします!
お題「夫婦(カップル)の馴れ初めを教えて下さい。参考にしますので(笑)」
(みんなのお題より)

いやぁ、これについて正直に話したら、ドン引きされちゃうかも…と思いつつも。
昨日の記事が真面目な話だったので、ちょっと雰囲気を変えるためにやっぱり書こうと思います。
出会いは都内の居酒屋。
僕はその日、当時勤務していた会社の研修があり、都内に行っていました。
で、そのまま直帰でいいというので、そこからわりと近くに住む大学時代の友人に声をかけました。
そしたらその友人、たまたま休日だったんです。
「久々に会って飲みにでもいくか!」という話になり、ある居酒屋にGo!となりました。
僕は当時23歳、まだ社会人2年目でした。
その居酒屋で2人がけのテーブル席で友人と向かい合って飲んでいたのですが、その隣の席で同じように友人と2人で来店・飲食していたのが現在の妻でした。
当然ながらお互い、まったく知らない人たちなので、最初は特に気にすることなく飲み食いしておりましたが、ここで事件が!
店員さんが、僕たちが注文した料理を間違えて隣の席で飲食していた妻とその友人の女性のところに運んでしまい、それを妻の友人が何も知らずに食べ始めてしまったのでした。
後から聞いた話では、妻が気づき、店員さんを呼んで確認したようで、その店員さんが僕たちに謝罪してきたわけです。
で、妻とその友人も「すみません。全然気づかなくて…。」と声をかけてきたのでした。
僕たちも話に夢中になっていたので、料理が隣席に運ばれたことさえ気づいていませんでした。
「あーいいっすよ、気にしないでください。」
そんな感じで返したと思います。
結局、店側の負担で注文した料理は改めて僕たちの席に届けられましたし、その場はいったんそれで終了しました。
ですが、それから少し経ったら、今度は僕の友人がコソコソと「あのコ(=妻の友人)がかわいい。」だの何だのと始まったのでした。
テーブルの下からツンツンと僕の足や靴を蹴って合図してくるのです。
知らねえよ(笑)
俺にどうしろと?
で、友人がその場で考えた作戦というのが「挟み撃ち作戦」。
どういうことかというと…ちょっと下の画像を使って説明いたしますね(笑)
この話をするのも、多少抵抗があるんですけど。
すぐ隣の席なんですから、別に普通に話しかければいいのに、何か変わったことがしたかったんでしょうね。

※画像はイメージです。
僕たちが座った席は、画像の右側のような席でした。
画像では4人がけとなっておりますが、実際には2人席が横に2つ並んでいた感じです。
なので、テーブルを半分にぶった切った状態を想像してみてください。
で、何をしたかというと、奥(=壁側)の席が切れ目がないのをいいことに、僕と友人で奥の席に座っていた妻の友人を挟み撃ちするような形で隣席にお邪魔し「一緒に飲みませんか」などと声掛けしたというわけです。
自分で書いていても恥ずかしいです。
繰り返しますが、この作戦を考案したのは僕の友人です。
ですが、僕も彼と共に作戦を実行に移した以上は「共犯」であることは確かです。
きっと今、たくさんの人がドン引きしていると思います(-_-;)
お願いです、行かないで!
せめてこの記事くらいは、最後まで読んでください!
でもって、結局テーブルをくっつけて、女性ふたりの飲食代も僕たちが払うということになりました。
というか、友人が独断でそのような決定をいたしました。
でも、女性ふたりは初対面でしたがいろいろと話しやすく、なんだかんだ楽しかったんですよね。
「料理を食べてしまった件もあったし、断りづらかったのかなぁ…」と僕には多少申し訳ない気持ちもありましたが、友人の目はずっとハートになっておりました。
結局、僕までそのふたりと連絡先を交換することになったのでした。
最後「また今度!」なんて言いながらも、僕にはその気はまったくありませんでした。
ですが、友人はその後妻の友人にアプローチしたようです。
が、実を結ぶには至らなかったようでした。
となると、ここで普通は終わりなのですが、信じられないことにある日、妻から僕にメールが入ったのです。
それからたまにメールで連絡を取り合うようになり、いろんな話をするようになりました。
ペースはすごくゆっくりなんですが、なんだかんだ途切れることなくやりとりは続きました。
そのうち悩みなど、深い話もしてくれるようになってきました。
メールでのやりとりが1年半くらい続いたある時、会ってみようかという話になり、まさかの再会をすることになりました。
こんなことになるとは思ってもいなかったです。
交際に発展したのは、再会してから約2か月後です。
前回の「お題・3」の記事で触れておりますが、僕は当時大失恋を引きずっており、長くて暗いトンネルの中にいて、朝起きてから夜寝るまで苦しんでいたのです。
そんな僕の心を、偶然出会ったひとりの女性が、少しずつ、少しずつ救ってくれたのでした。
グイグイ来ることもなく、僕のペースを尊重してくれていることも伝わってきていましたし、これは本当に大事にされているなという感覚になったわけです。
ドキドキから始まった恋愛ではなかったのですが、こういう形が一番長続きするのかもしれませんね。
そして約5年の交際を経たのち結婚し、現在に至ります。
もちろん、友人に対する感謝の気持ちも忘れていません(笑)
あの時の友人の考えや行動がこのような結果に結びついたのですから。
結局、最後は真面目な話で締める形となりましたね(笑)
最後まで読んでくださった皆様、ありがとうございます!
また当ブログに遊びにきてください。
当ブログは「にほんブログ村」のランキングに参加しております。
上のバナーをポチッとひと押し、応援をお願いします!
-- こんにちわ!
★よし★です。
昨晩、我が家ではわりと長い時間、妻と娘がバトルを繰り広げていました。
詳細を書くと怒られそうなのでやめておきますが、僕は(変な意味ではなく)娘が妻に対しても牙をむくようになってきたことが、なんだか嬉しく感じてしまいました。
1.以前は母親に対して強気に出れなかった娘が、ここ最近、言うべきことをきちんと言えるようになってきた。
娘は小学校高学年くらいから、少しずつですが母親に対しても自己主張はするようになってはいました。
ですが、ちょっと言い返されるとシュンとしてしまったり、すぐに泣いて引き下がったりといった具合で、なかなか今回のような対等なバトルを見ることはありませんでした。
娘は僕にも刃向かってくることはあります。
そりゃあ、反抗期ですからね。
別に悪いこととは思っていないし、むしろ歓迎しています。
でも父vs娘となると、僕が娘の話をとことん聞いた上で、伝えるべきことを伝えるというやり方なので、通常、激しい口論にはなりません。
ですが、母vs娘となるとどういうわけかお互い「引く」ということをしないので、そりゃあもう凄まじい打撃戦になります。
例えるなら、ふたりの女子ボクサーがリング上の至近距離で身体をくっつけながらバカバカ打ち合うようなイメージです。
鬼のような形相で、ボディ、アッパー、フックと多彩なパンチを上下左右に打ち分け、どうにかこうにか相手をノックアウトしようとするわけです。
うまくコツコツ当ててポイントを稼ぎ、判定勝ちを狙うような戦い方ではなく、お互いにノーガード、防御なんかはそっちのけでとにかく相手を倒すことしか考えていないような、本物の喧嘩バトルです。
内容は(怖くて?)詳しくは書けませんが、一般家庭でよくある話です。
「あること」で母に注意された娘が、母に対して「自分もできていないくせに」という反論をするところから始まる、両者のノンストップ・バトルです。

2.このくらいの年齢の子が親に反抗することは自然なこと。反抗できない・反抗を許さない環境こそがよっぽど問題。
子が成長過程において親に反抗してくることはごくごく当たり前のことだと思います。
ですが、親としても見るところは見ないといけないと思います。
もし子供の反発が、親子間の大きな溝・根深い問題に起因するものであれば、それは「子どもの成長過程における反抗」とはまた別モノであり、根本治療が必要だと思うからです。
成長過程における反抗は、親からしても前向きに捉えることができますが、根っこに大きな問題が潜んでいるような場合は、それを見逃すわけにはいきません。
バトルを繰り広げつつも、よく子供の話や主張に耳を傾け、感情移入して子の気持ちを理解しようとするような努力も必要なのかもしれません。
僕の親は「子供が親に向かって生意気な口をきいている」等の表面的事実のみをもって、それを「悪」と断定して子供の主張を力づくで制圧しようとするような親でした。
特に父親は「反抗は一切許さない」といった姿勢で向かってきていましたが、僕はそういったやり方が子供にとってはマイナスになるということを身をもって学んでいます。
「反発してきたっていいじゃないか、とことんやりあったっていいじゃないか、お互いに分かり合えるまで徹底的に付き合うよ」という気持ちがありますし、そこで親子の立場の違いとか年齢差がどうとか、そんなことを持ち出すつもりもありません。
好きなだけ自己主張しなさい、と。
子供が言いたいことを抑え込まれてしまうような環境のほうが、よっぽど問題だと思っています。
3.親がふたりがかりで子供を責めるのもNG!
片方の親が子供とやりあっている時、僕はもう片方の親はその子に寄り添い、聞き役に徹するべきだと考えています。
これも自分自身のつらい経験から学んだことです。
親ふたりからやられると、子供は逃げ場や居場所を失います。
「話を聴いて欲しい」「自分の気持ちを理解して欲しい」「寄り添って欲しい」というその子の思いがまったく届かなくなるのです。
子供からしたら、家庭内に逃げ場や居場所がないことほど、つらいものはないのです。
4.母娘バトルの結末
やりあうだけやり合って、最後は娘が生卵を床に叩きつけ、ドアを「バタン!」と閉めて2階の自分の部屋に向かいました。
自分の父ならここで娘を2階まで追いかけて徹底的につぶそうとしたのでしょうが、僕や妻はそんなことをしても事態は悪い方向に向かうだけで、なんのプラスももたらさないことは知っています。
娘も2階でしばらく自分の気持ちに整理をつけた後、1階に戻ってきました。
ちょうどその時、僕が風呂から上がって2階に行くタイミングだったので、娘に「なかなかやるじゃねーか」と声をかけたら、娘はニヤッと返してきました。
そして娘がリビングのドアを開ければ、そこで待っているのは妻の笑顔です。
もうすでに笑い話になっているのです。
母と娘が、お互いの”健闘”を称え合う様子がそこにありました。
僕は、これでいいと思っています。
母娘間に根本的な、深刻な問題が存在しているのなら、こうはなりません。
娘は根に持つでしょう。
僕も高3の息子と自然と目が合い、お互いに笑い合いました。
これにて一件落着です。
5.【余談】妻が息子とぶつかると…
最近はいつも息子に論破されています(笑)
言い返せなくなって、笑ってごまかして終わります。
息子もあまり本気で相手をしなくなってきていますね。
これもまた、息子の成長です。
父は嬉しいです(笑)
当ブログは「にほんブログ村」のランキングに参加しております。
上のバナーをポチッとひと押し、応援をお願いします!
こんにちわ!
★よし★です。
先週の話になりますが、家族間・親子間のコミュニケーションの大切さを再認識する機会がありましたので、書かせていただこうと思います。
1.春休み終了間際の「桃鉄大会」
我が家の子供達は、4月に入り、学年がそれぞれ上がって息子が高3、娘が中2となりました。
ふたりとも7日(月)から登校しておりますが、それまでは春休みでした。
休みとはいっても、部活や友達付き合い等もあります。
なかなかゆっくり同じ時間を過ごすことは難しかったのですが、春休み終了間際に全員が揃う機会がありました。
せっかくだから皆で何かしようかという話になり、子供達の希望により急遽、家族で桃鉄をやることになりました。
ご存知の方が多いとは思いますが、ごくごく簡単に説明いたします。
「桃鉄」というのは「桃太郎電鉄」の略で、サイコロを振って鉄道や航空ルートを進み、目的地(国内・海外)を目指すゲームです。
目的地に一番乗りした人は賞金をゲットしたり、目的地の物件を買ったりすることができます。
例えば、目的地が「盛岡」であれば「わんこそばや」が買えたりとかですね。
物件からは収益が発生したり、臨時収入が入ったりします。
そして最終順位は「資産」の額で決まりますので、プレイヤーは手持ちのお金を増やしながら、物件をたくさん買うことが求められます。
なお、これ以上説明しようとするとキリがないので、もしプレイしたことが無いという方がいらっしゃれば、YouTube等でプレイ動画を見てみてください。
どんなゲームなのかがイメージできると思います。
で、この桃鉄を家族4人で対決したわけです。
「よっしゃあ!」とか「あぁーーっ!」とか「おっつー!(笑)」とか、子供達はともかく、大人2人も子供のようにはしゃぎながら10年ほどプレイしました。
面白いですよね、桃鉄って。
僕はいつも家族全員から意地悪される役なのですが、この桃鉄は僕が子供の頃からあったゲームで、自分自身相当やりこんでいるため、いろんな策を駆使してだいたいは僕が最終的に勝つことが多かったのです。
が、今回はいつもビリだった娘が大躍進して見事優勝を果たしました。
年齢を重ね、身体も成長してくると、頭も成長するものですね。
やり方がうまくなってきました。
同じゲームを家族全員で仲良く楽しくプレイするのって、最高の家族間コミュニケーションですよね。
「家族の絆」が深まるのをはっきりと感じられます。
2.自分が子供の頃はこういった家族間のコミュニケーションがあっただろうか
ついつい考えてしまうんです。
自分が子供の頃はどうだったのか、ということを。
桃鉄も含め、家にこうした家族で遊べるゲームはありました。
いつも弟とばかりプレイしていたので、たまには家族でと両親に声をかけたことは何度もありました。
ですが、両親とも一緒に遊ぼうとはしませんでした。
両親ともゲーム自体に興味がない、操作を覚えるのも面倒くさい、よくわからないことをやりたくない、といった感じでした。
こういった場合、子供が最終的に求めているのは「ゲームを一緒にプレイすること」というよりは「親とコミュニケーションを取ること」だと思います。
言い換えれば「ゲームを一緒にプレイすることを通じて両親とコミュニケーションを深める」ことだとも言えると思います。
その機会を親側から遮断してしまっていたわけですね。
僕も弟も、親と一緒にゲームをして遊んだことはただの一度としてありません。

3.親子で同じ時間・目標などを共有することの大切さ
何もゲームの話だけに限定されるわけではありませんが、いろいろ振り返ってみると、僕の両親は子供と積極的に遊んだり、子供のチャレンジ精神を応援したり、目標を共有して伴走したりとか、そういったことがまったくといっていいほど、ありませんでした。
まず、子供の遊びに関心がなかったというのが、今の僕からしたら本当に不思議です。
自分の子供が現在どういったことに興味があるとか、子供の世界では今何が流行っているとか、1から10まで把握してくれとは言いませんが、親なら知りたいと思うし、知ろうとするのが親だと思ってしまいます。
でないと、子供と話題を共有できませんよね。
子供からしたら「つまらない親」「話ができない親」になるので、そこで親子間に大きな距離が生じます。
子供と遊んだり、共通の話題で盛り上がること、親子間のコミュニケーションとしてとっても大切なことだと思います。
それから、先ほど「チャレンジ精神」という言葉を出しましたが、僕は小学生の時、少年野球チームに入りたくて何度も親にお願いをしました。
よくある「〇〇リーグ」「〇〇ボーイズ」などと名のつく小学生の野球チームです。
僕は野球が好きで、当時はプロ野球選手になることが夢でした。
が、僕のお願いが聞き入れられることはありませんでした。
チームに入れてもらえない理由として母親が僕に言ってきたことは「ああいうところは親の出番が多いのよ」という驚くべき理由でした。
それを親が自分の心の中にとどめておく分にはまだ問題はないと言えそうですが、あえて本当のことを子供の前で口に出せるその神経を僕は疑ってしまったのでした。
子供の目標を親が応援したり、親子で目標を共有してスポーツに打ち込んでいる友達がとてもうらやましかったです。
4.過去から学んだことを現在の子育てに活かす
僕は、うちの親子関係がうまくいかなかった大きな原因が「親子間のコミュニケーション不足」にあると考えています。
過去から何を学び、それを現在の子育て・教育にどう活かすかは僕次第。
僕は(妻もですが)、子供とはよく遊びましたし、今も遊びます。
子供と遊ぶ際は、できるだけ大人であることを忘れ、子供に返ったつもりで遊ぶことを心がけてきました。
「一緒になってはしゃぐ」イメージです。
これは親子間の距離をグッと縮めるのに非常に有効だと思います。
子供に「遊んでもらっている」と感じさせるのではなく「一緒に遊んでいる」という感覚になってもらうこと、コレ結構大事だと思います。
子供の「遊び相手」になれれば、中学生になっても、高校生になっても子供は親と遊んでくれます。
同じ時間を過ごしたり、同じ目標を共有できる親子関係。
そういった環境が整っている家庭で育った子は、よほどのことがない限り、決して横道にそれたりはしないと考えています。
僕が今できることは、過去から学んだことを現在の子育てに活かすこと。
過去は変えようがありません。
今できることを全力で。
すべては子供のために、です。
当ブログは「にほんブログ村」のランキングに参加しております。
上のバナーをポチッとひと押し、応援をお願いします!
こんにちわ!
★よし★です。
以前、我が家には外壁塗装と蓄電池の訪問営業が頻繁に来るという記事を書かせていただきました。
僕は普段仕事で家にいないのですが、妻・息子・娘の3人で談笑したりしているタイミングで「ピンポーン!」と来られるとあまりいい気がしないという3人の言い分もあり、それならイ ンターホン付近に「セールスお断り」的なステッカーを設置して様子を見てみようかという話になったのでした。
その記事がコチラ↓↓↓↓↓↓↓↓
すごいですよね。
「チャイム押すな!!」とまで書かれています。
このステッカーを設置して約3か月。
その効果やいかに?!
1.ステッカーの効果
結論から申し上げます。
訪問営業、限りなくゼロになりました。
本当にほとんど来なくなったそうです。
ポストにチラシが入っていたりはしますが、我が家はそこまで目くじらを立てるつもりはありません。
世の中には「チラシも入れるな」という意思表示をされている方もいますよね。
「チラシが入っていたら着払いで返送します」とまで書かれている場合も。
そこまで徹底抗戦するつもりはないです。
訪問営業が激減したなら、それでよしです。

2.完全ゼロとはいかない
それでも、訪問営業、完全なゼロとはなっておりません。
以下の理由が考えられます。
①「そんなの関係ねぇ!」という強者(つわもの)営業マンの存在
世の中にはなかなかスゴイ人というのがいて、このステッカーのような強めのメッセージにも臆することなく「ピンポーン!」と押せちゃう人も普通に存在するでしょう。
「試しに押してみて、怒られるようなら2回目押さなきゃいい」くらいの考えの人もいると思います。
②ステッカーの存在に気づく前にインターホンを押してしまうケース
これも十分考えられます。
押した後に気づいて「あ、しまった」というパターンですね。
これ、普通にあると思います。
おそらく、このどちらかではないでしょうか。
3.【結論】設置の効果は大いに感じられる
上記のような理由から、完全ゼロというのはなかなか難しいと思います。
が、ステッカー設置前と設置後では明らかに状況は変化しており、現在「ほぼゼロ」状態という事から考えても設置の効果は非常に大きかったということになると思います。
「この家、面倒そうだな」という意識が働くのかもしれませんね。
ちょっと文言が強めではありますが、確実に撃退したいという方にはおすすめできそうな商品だという結論に達しました。
商品は「マグネット」「シール」の2種類のタイプがあります。
ご自宅の設置環境に合ったものをお選びください。
◆マグネットタイプはこちらから
リンク
◆シールタイプはこちらから
リンク
※関連記事もぜひお読みください。
当ブログは「にほんブログ村」のランキングに参加しております。
上のバナーをポチッとひと押し、応援をお願いします!
(みんなのお題より)

人間、人生で一度くらいは、ひとりの異性を深く好きになってしまうことはあると思います。
そんな経験、僕にもありました。
うまくいっている間は、すっごくいいんですよね。
めちゃくちゃ幸せで。
でも、出会いがあれば別れもある。
お相手の家庭の事情で離れることになりました。
中途退学ですね。
理由が理由だけに、気持ちの切り替えは容易にできなかったです。
で、そのあと長いこと、苦しみました。
朝起きてから夜寝るまで、起きている間はずっと苦しみがついて回ってきました。
生きている心地がしなかったです。
病院に行っていれば、なんらかの診断名がついていたと思います。
とにかく苦しかったです。
でも、転機って来るものですね。
ある人と出会い、すごく想われるようになったんです。
グイグイ来るタイプではなく、自然な愛情表現をしてくる人でした。
自分の気持ちが徐々に落ち着いていくのを感じました。
燃えるような恋愛というよりは…そうですね、いつしかなくてはならない存在となっていった感じですね。
いてくれるだけでとにかく心が安定する、そんな存在です。
想い続けることほど苦しいことはないですよね。
想われることの幸せ、ありがたみというのを当時すごく感じていました。
僕の気持ちも変化していきました。
「自分のことをここまで想ってくれる人を幸せにしたい」と。
で、その人は20年以上経った今も横にいます。
結局、「立ち直った」というより「立ち直らせてもらった」というほうが正しいかもしれません。
時間の経過、新たな出会い。
これがすべてでしたね。
当ブログは「にほんブログ村」のランキングに参加しております。
上のバナーをポチッとひと押し、応援をお願いします!
こんにちわ!
★よし★です。
今日は朝早くから県外へ。
昼過ぎには湘南に戻っていました。
帰り際、ずーっと気になっていたラーメン店に寄っちゃいました!
いやぁ、今回は期待以上でしたね。
早速、紹介いたします。
1. ラーメン店基本情報等

①店名
ラーメン萩原家 藤沢店
②所在地
神奈川県藤沢市大鋸1-3-1
青木ビル101
③駐車場
店舗ビル裏の駐車場内に4台分あり。
2番、5番、7番、8番が萩原家さん利用客の駐車スペース。
ちゃんと「萩原家」と表記されています。
④営業時間
日~木 11:00~15:00/17:30~22:00
金・土 11:00~15:00/17:30~23:30
⑤定休日
無休
※営業時間・定休日につきましては、訪問前にご自身でご確認ください。
⑥席数
カウンター11席。
あと奥にテーブル4席がある「らしい」です(見えませんでした)。
⑦注文制/食券制
食券制
店舗に入ってすぐ左に券売機があります。
⑧その他特記事項
店主さんは、矢口家さんで修行された方とのこと。
僕は矢口家さんのラーメンも大好きです。

そんなこともあって、萩原家さんは機会があればぜひ行きたいとずーっと思っていたお店なんです。
2.萩原家さんのラーメン

ラーメン + トッピング チャーシュー
(のり3枚、ほうれん草、ねぎ、チャーシュー5枚)
まず、このお店は太麺と細麺が選べるようです。
店主さんにどちらにするか聞かれました。
僕は太麺を選択!
あとはお好みを聞かれますので、以下につき希望があれば伝えます。
◆麺のかたさ(かため・普通・やわらかめ)
◆味の濃さ(濃いめ・普通・うすめ)
◆脂の量(多め・普通・少なめ)
「麺かためで」などと伝えます。
何も伝えなかった項目は「普通」と判断されますので、希望がある項目だけ伝えればOKです。
昼時で満席でしたが、待ち時間は5分くらいだったかな…意外と早く着丼しました。
まずスープから。
個々の感じ方次第ですが、僕には濃厚というほどの濃厚さは感じられず、濃すぎず薄すぎずの丁度いい具合のスープでした。
でも矢口家さんよりは明らかに濃厚かな。
醤油の旨味もしっかりと感じられます。
臭み・くどさはまったく無し。
一滴残らず飲みました。
麺は、丸山製麺の箱が置いてあったので、矢口家さんと一緒なのかなと。
でも僕が選択した太麺、普通の太麺より太かったですね。
そしてモチモチ感が半端なく、その食感もじゅうぶんに楽しめると思います。
麺の量は中盛・大盛・メガ盛りにできるようで、個人的には最低でも中盛以上にしたほうが、目一杯、萩原家さんのラーメンを堪能できると思いました。
ここはちょっともったいなかったかも。
チャーシューは自家製・肩ロース。
ビジュアル的には豪華さのようなものは感じられず、薄切りで控えめな印象なんですが、意外にも食べごたえ抜群でちょっと甘味らしきものも感じられました。
おいしかったですね。
個人の好みによりますが、僕にとってはスープ、麺、チャーシュー、すべてが大満足で「大当たり」と言っていいと思います。
萩原家さん、また是非行きたいです。
3.youtube動画
ショート動画です。
短い時間ですが、お楽しみください。
4.「気になるラーメン店がある!でも遠くて行けない!」そんなあなたに朗報!
おいしそうなラーメン店がテレビやSNSで紹介されて 「行ってみたい!食べてみたい!」 と思っても、 お住まいから距離があると時間も交通費もかかるので 、そのラーメンを食べるのをついついあきらめてしまいがち……。
ですが 「家にいながら、そのラーメン屋さんの実店舗の味に限りなく近い味のラーメンを食べられる」 なんていう “おいしい”話 がもしあれば、気になるお店のラーメンを食べることをあきらめずに済むかもしれませんよね?
そんな時には「宅麺.com」がおすすめ!
宅麺.comさんは2010年7月にサービスを開始!
有名店・行列店のラーメンそのままの味を自宅で楽しめるよう、店舗で冷凍したスープ・麺・具材をそのまま各家庭に届けることで、実店舗の味を再現することに強くこだわっておられます!
「気になるラーメン店」がある方、そのラーメンの取り扱いがあるかどうか、ぜひ以下より検索をしてみてください!
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
当ブログは「にほんブログ村」のランキングに参加しております。
上のバナーをポチッとひと押し、応援をお願いします!
 にほんブログ村
にほんブログ村