京都市立美術工芸学校とは 人気・最新記事を集めました - はてな (original) (raw)
京都市立美術工芸学校
このタグの解説についてこの解説文は、すでに終了したサービス「はてなキーワード」内で有志のユーザーが作成・編集した内容に基づいています。その正確性や網羅性をはてなが保証するものではありません。問題のある記述を発見した場合には、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
関連ブログ

明治・大正・昭和を生きた日本人絵付師の生涯•3年前
第四章 京都下宿時代(3) 今では書生等という言葉は使わないが当時は学校の生徒でも書生さんと言った。そして決まって黒の紋付き羽織に小倉の袴で羽織の紐は白で二尺位(約六十糎)もあった。それを先の方で結び首に掛けて歩いていた。下駄は朴歯の太い鼻緒のついた桐の厚いものでゴロンゴロンと殊更、音を立てゝ得意がっていた。 此等の書生さん仲間では男色が流行して時々稚児さんの事で血を見る様な争いもあった。 特に九州地方の人々の間に多かった様である。私とは同級生のN君は、熊本の士族で剣道の達人で、よく画論を闘わせた一人であったが、御国柄この稚児さんの事に関しては熱心であった。 明治三十?年四月頃この宿へ一人の婦人が止宿させて呉れと訪れた。…
今では書生等という言葉は使わないが当時は学校の生徒でも書生さんと言った。そして決まって黒の紋付き羽織に小倉の袴で羽織の紐は白で二尺位(約六十糎)もあった。それを先の方で結び首に掛けて歩いていた。下駄は朴歯の太い鼻緒のついた桐の厚いものでゴロンゴロンと殊更、音を立てゝ得意がっていた。 此等の書生さん仲間では男色が流行して時々稚児さんの事で血を見る様な争いもあった。 特に九州地方の人々の間に多かった様である。私とは同級生のN君は、熊本の士族で剣道の達人で、よく画論を闘わせた一人であったが、御国柄この稚児さんの事に関しては熱心であった。 明治三十?年四月頃この宿へ一人の婦人が止宿させて呉れと訪れた。…
#明治時代#京都市立美術工芸学校#京都府立高等女学校#京華社#森村組
関連ブログ

明治・大正・昭和を生きた日本人絵付師の生涯•3年前
第四章 京都下宿時代(2)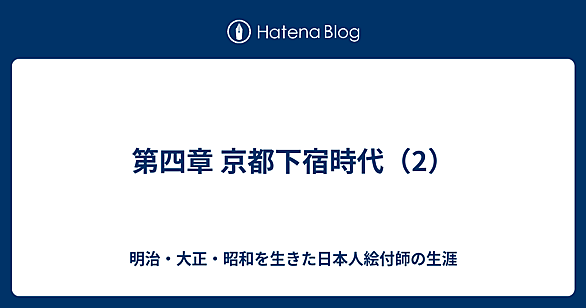 主な事は万事女将が切り回していたが下宿代の事等はあまり督促がましい事を聞いた事が無かった。下宿人は全部で十二、三人は居た様だ。私は始め二階の三畳七分五厘という四畳に足りない隅の室で半年許り辛抱していた。下宿代も安かったが三畳七分五厘舎の主人と自称していたのも、この時だ。 その後、下の八畳の部屋へ移ったが初めは彫刻家の先輩で国安稲香という人と同宿していた。彼の兄さんが京都森村組出張所の会計係の小滝さんと言って父も私も、そこで知り合いであった関係から国安君の話が出て同君も私を知る様になった。科は違っていても先輩なので何となく心強く兄貴の様に思って交際していた。国安君と小滝さんは性格が全く異なり小滝…
主な事は万事女将が切り回していたが下宿代の事等はあまり督促がましい事を聞いた事が無かった。下宿人は全部で十二、三人は居た様だ。私は始め二階の三畳七分五厘という四畳に足りない隅の室で半年許り辛抱していた。下宿代も安かったが三畳七分五厘舎の主人と自称していたのも、この時だ。 その後、下の八畳の部屋へ移ったが初めは彫刻家の先輩で国安稲香という人と同宿していた。彼の兄さんが京都森村組出張所の会計係の小滝さんと言って父も私も、そこで知り合いであった関係から国安君の話が出て同君も私を知る様になった。科は違っていても先輩なので何となく心強く兄貴の様に思って交際していた。国安君と小滝さんは性格が全く異なり小滝…
#明治時代#京都市立美術工芸学校#小村大雲#美術工芸#京都

明治・大正・昭和を生きた日本人絵付師の生涯•4年前
第四章 京都下宿時代(1)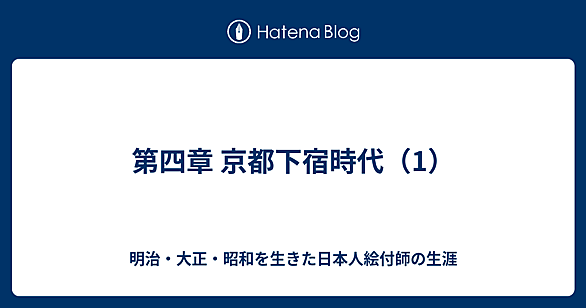 明治三十一年三月父が名古屋へ転勤してから下宿生活となり最初京都の中央、活花の家元池の坊で名高い六角堂の門前鐘楼の傍らに父の知人の煎り豆専門の店があった。一先ず其の家へ下宿し其所から寺町丸太町の学校へ通学していた。が道も遠く何かと不便なので半年ばかりで川畑春翠君の二階へ移り其所も一年程で同家の都合で引き払い仲町竹屋町下る井上という下宿へ落ち着いた事は先に延べた。 この家も明治三十五年頃京都御所、梨木神社前の田能村直入画伯邸の隣に広い家が空いていたので其所へ転宅し下宿屋を続けたので私も又そこへ移って世話になった。 この下宿の親父は井上捨次郎といって当時四十五、六才の男盛りで女将の名は「てい」といっ…
明治三十一年三月父が名古屋へ転勤してから下宿生活となり最初京都の中央、活花の家元池の坊で名高い六角堂の門前鐘楼の傍らに父の知人の煎り豆専門の店があった。一先ず其の家へ下宿し其所から寺町丸太町の学校へ通学していた。が道も遠く何かと不便なので半年ばかりで川畑春翠君の二階へ移り其所も一年程で同家の都合で引き払い仲町竹屋町下る井上という下宿へ落ち着いた事は先に延べた。 この家も明治三十五年頃京都御所、梨木神社前の田能村直入画伯邸の隣に広い家が空いていたので其所へ転宅し下宿屋を続けたので私も又そこへ移って世話になった。 この下宿の親父は井上捨次郎といって当時四十五、六才の男盛りで女将の名は「てい」といっ…
#京都市立美術工芸学校#六角堂#明治時代#京都#梨木神社#明治31年#明治35年#田能村直入

明治・大正・昭和を生きた日本人絵付師の生涯•4年前
第三章 美術工芸学校時代(3)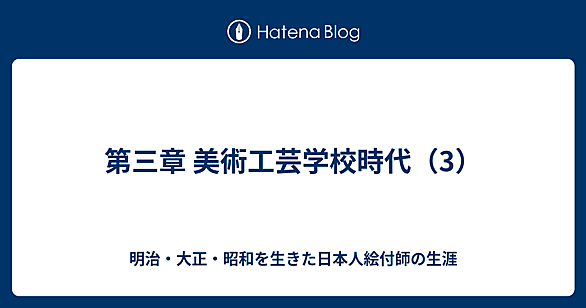 北条静という人の所へ停雲に誘われてバイオリンを習いに通ったが半年許りでやめた。彼はその後一人で通っていた様だ。 学校では月に二、三回郊外写生の課目があるので、その日は思う儘、山野を跋渉し一日を郊外で過ごした。その服装といえば黒紋付の羽織袴で草履を履き写生帖を懐に矢立を腰に挟み竹の皮包みの弁当を持ち朝は早く宿を出て夜は星を戴いて疲れた足を引きづって帰ったものだ。 豊島停雲、島田海南、川畑春翠とは何時も一諸だった。この郊外写生はまる一日の行程で京都付近は隅から隅迄殆ど行かない所は無い程だった。 遠くは比叡山を越え近江の坂本に下り琵琶湖を廻っては八景を尋ね三井寺の晩鐘を聞き乍ら帰りを急ぐ事も、宇治や…
北条静という人の所へ停雲に誘われてバイオリンを習いに通ったが半年許りでやめた。彼はその後一人で通っていた様だ。 学校では月に二、三回郊外写生の課目があるので、その日は思う儘、山野を跋渉し一日を郊外で過ごした。その服装といえば黒紋付の羽織袴で草履を履き写生帖を懐に矢立を腰に挟み竹の皮包みの弁当を持ち朝は早く宿を出て夜は星を戴いて疲れた足を引きづって帰ったものだ。 豊島停雲、島田海南、川畑春翠とは何時も一諸だった。この郊外写生はまる一日の行程で京都付近は隅から隅迄殆ど行かない所は無い程だった。 遠くは比叡山を越え近江の坂本に下り琵琶湖を廻っては八景を尋ね三井寺の晩鐘を聞き乍ら帰りを急ぐ事も、宇治や…
#京都市立美術工芸学校#京都#明治時代#竹内栖鳳#荒神橋#明治34年#明治35年

明治・大正・昭和を生きた日本人絵付師の生涯•4年前
第三章 美術工芸学校時代(2) 明治三十一年三月父が名古屋の森村組出張所へ転勤となったので、私は下宿生活をする事となった。最初は父の知人であった六角堂前の煎豆屋の二階を、三食付き月五円五十銭で泊っていた。同級生に川端敬雄(春翠)(卒業後山元春挙先生の門下となり草笛会の同人として桜を得意としていたが惜しい事に十年位前故人となった)という私より一つ年下の友人が予備科から一緒で一番仲が良く然も金持ちの三男坊だったので遠くへ写生に行った時等は種々の費用を出しておいて呉れた。そんな仲だったので彼の家へはよく遊びにも行き御馳走にもなり時には泊ってきた事も度々あった。 私の下宿から学校迄は相当遠かったが、当時電車等の乗物が無かったので朝早…
明治三十一年三月父が名古屋の森村組出張所へ転勤となったので、私は下宿生活をする事となった。最初は父の知人であった六角堂前の煎豆屋の二階を、三食付き月五円五十銭で泊っていた。同級生に川端敬雄(春翠)(卒業後山元春挙先生の門下となり草笛会の同人として桜を得意としていたが惜しい事に十年位前故人となった)という私より一つ年下の友人が予備科から一緒で一番仲が良く然も金持ちの三男坊だったので遠くへ写生に行った時等は種々の費用を出しておいて呉れた。そんな仲だったので彼の家へはよく遊びにも行き御馳走にもなり時には泊ってきた事も度々あった。 私の下宿から学校迄は相当遠かったが、当時電車等の乗物が無かったので朝早…
#京都市立美術工芸学校#山元春挙#富田渓仙#日本美術院#小野湖山#明治時代#都路華香#江馬天江

明治・大正・昭和を生きた日本人絵付師の生涯•4年前
第三章 美術工芸学校時代(1)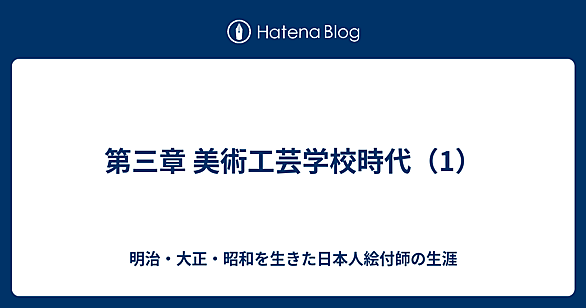 予備科では翌々年の三月迄、横山大観先生の指導を受け、絵画本科へ進学してからは鈴木瑞彦先生に教えを受ける事となった。当時考古学、美術史は校長今泉雄作氏が担当して居られた外、富岡鉄斎、竹内棲鳳(栖鳳)菊池芳文、山元春挙等の諸先生が居られ京都画壇の錚々たる大家が揃っていた。図案科では谷口香愫先生が一学年から五学年迄を担当して居られた。又彫刻科には大村西厓先生が居られ卒業生の先輩、国安稲香君が助手を務めていた。 生徒は各科にニ、三十名位で合計ニ百名余り。服装は制服と好きして安部仲麿の様な古代の官制にあった闕腋(けってき)というもので帽子は今の裁判官が使用している物と略同じである。それに緑色の絹の組紐を…
予備科では翌々年の三月迄、横山大観先生の指導を受け、絵画本科へ進学してからは鈴木瑞彦先生に教えを受ける事となった。当時考古学、美術史は校長今泉雄作氏が担当して居られた外、富岡鉄斎、竹内棲鳳(栖鳳)菊池芳文、山元春挙等の諸先生が居られ京都画壇の錚々たる大家が揃っていた。図案科では谷口香愫先生が一学年から五学年迄を担当して居られた。又彫刻科には大村西厓先生が居られ卒業生の先輩、国安稲香君が助手を務めていた。 生徒は各科にニ、三十名位で合計ニ百名余り。服装は制服と好きして安部仲麿の様な古代の官制にあった闕腋(けってき)というもので帽子は今の裁判官が使用している物と略同じである。それに緑色の絹の組紐を…
#京都市立美術工芸学校#横山大観#富岡鉄斎#竹内栖鳳#山元春挙#明治時代

明治・大正・昭和を生きた日本人絵付師の生涯•4年前
第二章 京都伏見時代(3)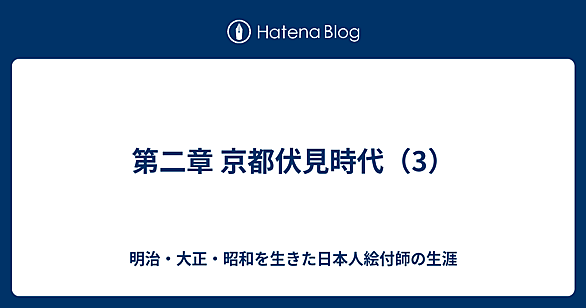 そこで腕白小僧も東京から京都へ来て、板橋の学校へ神妙に通学していた。 処が丁度付近に住んでいた稲荷の神官の息子で一級上の道楽者?私より以上に腕白で怠け者が、登校する時の良い道連れであった。毎朝誘って呉れるので始めは誠に良い友達で親切な人だと喜んでいた。処が一ヶ月すぎ二ヶ月たち、だんだんお互いに気心が判って来ると、朱に交われば、赤くなってきた腕白小僧は学校へ行って勉強するより遊ぶ方が面白くなってきて、つい誘われる儘に一日休み、又次の日も、今日は桃山へ城跡を見に行くとか、先陣争いをした宇治橋の古戦場や平等院へ行くとか、勝手な理由をつけては来る日も来る日も、朝は決まった時間に弁当を鞄に入れて如何にも…
そこで腕白小僧も東京から京都へ来て、板橋の学校へ神妙に通学していた。 処が丁度付近に住んでいた稲荷の神官の息子で一級上の道楽者?私より以上に腕白で怠け者が、登校する時の良い道連れであった。毎朝誘って呉れるので始めは誠に良い友達で親切な人だと喜んでいた。処が一ヶ月すぎ二ヶ月たち、だんだんお互いに気心が判って来ると、朱に交われば、赤くなってきた腕白小僧は学校へ行って勉強するより遊ぶ方が面白くなってきて、つい誘われる儘に一日休み、又次の日も、今日は桃山へ城跡を見に行くとか、先陣争いをした宇治橋の古戦場や平等院へ行くとか、勝手な理由をつけては来る日も来る日も、朝は決まった時間に弁当を鞄に入れて如何にも…
#明治時代#京都伏見稲荷#京都市立美術工芸学校#菩提所芬陀院
 今では書生等という言葉は使わないが当時は学校の生徒でも書生さんと言った。そして決まって黒の紋付き羽織に小倉の袴で羽織の紐は白で二尺位(約六十糎)もあった。それを先の方で結び首に掛けて歩いていた。下駄は朴歯の太い鼻緒のついた桐の厚いものでゴロンゴロンと殊更、音を立てゝ得意がっていた。 此等の書生さん仲間では男色が流行して時々稚児さんの事で血を見る様な争いもあった。 特に九州地方の人々の間に多かった様である。私とは同級生のN君は、熊本の士族で剣道の達人で、よく画論を闘わせた一人であったが、御国柄この稚児さんの事に関しては熱心であった。 明治三十?年四月頃この宿へ一人の婦人が止宿させて呉れと訪れた。…
今では書生等という言葉は使わないが当時は学校の生徒でも書生さんと言った。そして決まって黒の紋付き羽織に小倉の袴で羽織の紐は白で二尺位(約六十糎)もあった。それを先の方で結び首に掛けて歩いていた。下駄は朴歯の太い鼻緒のついた桐の厚いものでゴロンゴロンと殊更、音を立てゝ得意がっていた。 此等の書生さん仲間では男色が流行して時々稚児さんの事で血を見る様な争いもあった。 特に九州地方の人々の間に多かった様である。私とは同級生のN君は、熊本の士族で剣道の達人で、よく画論を闘わせた一人であったが、御国柄この稚児さんの事に関しては熱心であった。 明治三十?年四月頃この宿へ一人の婦人が止宿させて呉れと訪れた。…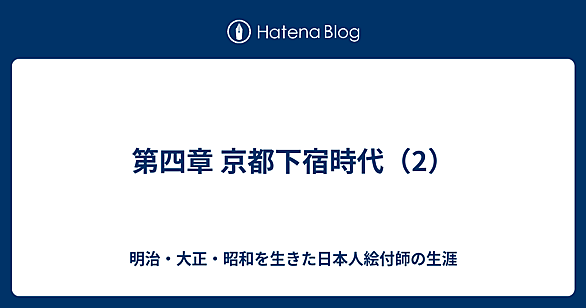 主な事は万事女将が切り回していたが下宿代の事等はあまり督促がましい事を聞いた事が無かった。下宿人は全部で十二、三人は居た様だ。私は始め二階の三畳七分五厘という四畳に足りない隅の室で半年許り辛抱していた。下宿代も安かったが三畳七分五厘舎の主人と自称していたのも、この時だ。 その後、下の八畳の部屋へ移ったが初めは彫刻家の先輩で国安稲香という人と同宿していた。彼の兄さんが京都森村組出張所の会計係の小滝さんと言って父も私も、そこで知り合いであった関係から国安君の話が出て同君も私を知る様になった。科は違っていても先輩なので何となく心強く兄貴の様に思って交際していた。国安君と小滝さんは性格が全く異なり小滝…
主な事は万事女将が切り回していたが下宿代の事等はあまり督促がましい事を聞いた事が無かった。下宿人は全部で十二、三人は居た様だ。私は始め二階の三畳七分五厘という四畳に足りない隅の室で半年許り辛抱していた。下宿代も安かったが三畳七分五厘舎の主人と自称していたのも、この時だ。 その後、下の八畳の部屋へ移ったが初めは彫刻家の先輩で国安稲香という人と同宿していた。彼の兄さんが京都森村組出張所の会計係の小滝さんと言って父も私も、そこで知り合いであった関係から国安君の話が出て同君も私を知る様になった。科は違っていても先輩なので何となく心強く兄貴の様に思って交際していた。国安君と小滝さんは性格が全く異なり小滝…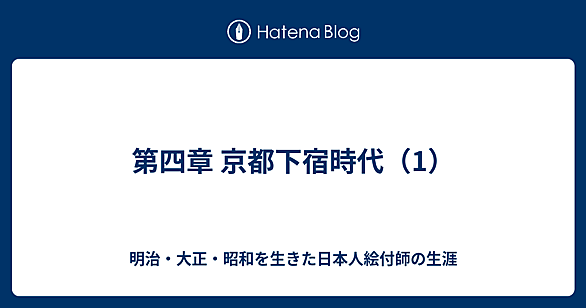 明治三十一年三月父が名古屋へ転勤してから下宿生活となり最初京都の中央、活花の家元池の坊で名高い六角堂の門前鐘楼の傍らに父の知人の煎り豆専門の店があった。一先ず其の家へ下宿し其所から寺町丸太町の学校へ通学していた。が道も遠く何かと不便なので半年ばかりで川畑春翠君の二階へ移り其所も一年程で同家の都合で引き払い仲町竹屋町下る井上という下宿へ落ち着いた事は先に延べた。 この家も明治三十五年頃京都御所、梨木神社前の田能村直入画伯邸の隣に広い家が空いていたので其所へ転宅し下宿屋を続けたので私も又そこへ移って世話になった。 この下宿の親父は井上捨次郎といって当時四十五、六才の男盛りで女将の名は「てい」といっ…
明治三十一年三月父が名古屋へ転勤してから下宿生活となり最初京都の中央、活花の家元池の坊で名高い六角堂の門前鐘楼の傍らに父の知人の煎り豆専門の店があった。一先ず其の家へ下宿し其所から寺町丸太町の学校へ通学していた。が道も遠く何かと不便なので半年ばかりで川畑春翠君の二階へ移り其所も一年程で同家の都合で引き払い仲町竹屋町下る井上という下宿へ落ち着いた事は先に延べた。 この家も明治三十五年頃京都御所、梨木神社前の田能村直入画伯邸の隣に広い家が空いていたので其所へ転宅し下宿屋を続けたので私も又そこへ移って世話になった。 この下宿の親父は井上捨次郎といって当時四十五、六才の男盛りで女将の名は「てい」といっ…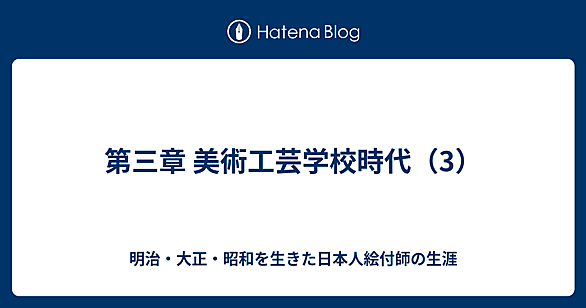 北条静という人の所へ停雲に誘われてバイオリンを習いに通ったが半年許りでやめた。彼はその後一人で通っていた様だ。 学校では月に二、三回郊外写生の課目があるので、その日は思う儘、山野を跋渉し一日を郊外で過ごした。その服装といえば黒紋付の羽織袴で草履を履き写生帖を懐に矢立を腰に挟み竹の皮包みの弁当を持ち朝は早く宿を出て夜は星を戴いて疲れた足を引きづって帰ったものだ。 豊島停雲、島田海南、川畑春翠とは何時も一諸だった。この郊外写生はまる一日の行程で京都付近は隅から隅迄殆ど行かない所は無い程だった。 遠くは比叡山を越え近江の坂本に下り琵琶湖を廻っては八景を尋ね三井寺の晩鐘を聞き乍ら帰りを急ぐ事も、宇治や…
北条静という人の所へ停雲に誘われてバイオリンを習いに通ったが半年許りでやめた。彼はその後一人で通っていた様だ。 学校では月に二、三回郊外写生の課目があるので、その日は思う儘、山野を跋渉し一日を郊外で過ごした。その服装といえば黒紋付の羽織袴で草履を履き写生帖を懐に矢立を腰に挟み竹の皮包みの弁当を持ち朝は早く宿を出て夜は星を戴いて疲れた足を引きづって帰ったものだ。 豊島停雲、島田海南、川畑春翠とは何時も一諸だった。この郊外写生はまる一日の行程で京都付近は隅から隅迄殆ど行かない所は無い程だった。 遠くは比叡山を越え近江の坂本に下り琵琶湖を廻っては八景を尋ね三井寺の晩鐘を聞き乍ら帰りを急ぐ事も、宇治や… 明治三十一年三月父が名古屋の森村組出張所へ転勤となったので、私は下宿生活をする事となった。最初は父の知人であった六角堂前の煎豆屋の二階を、三食付き月五円五十銭で泊っていた。同級生に川端敬雄(春翠)(卒業後山元春挙先生の門下となり草笛会の同人として桜を得意としていたが惜しい事に十年位前故人となった)という私より一つ年下の友人が予備科から一緒で一番仲が良く然も金持ちの三男坊だったので遠くへ写生に行った時等は種々の費用を出しておいて呉れた。そんな仲だったので彼の家へはよく遊びにも行き御馳走にもなり時には泊ってきた事も度々あった。 私の下宿から学校迄は相当遠かったが、当時電車等の乗物が無かったので朝早…
明治三十一年三月父が名古屋の森村組出張所へ転勤となったので、私は下宿生活をする事となった。最初は父の知人であった六角堂前の煎豆屋の二階を、三食付き月五円五十銭で泊っていた。同級生に川端敬雄(春翠)(卒業後山元春挙先生の門下となり草笛会の同人として桜を得意としていたが惜しい事に十年位前故人となった)という私より一つ年下の友人が予備科から一緒で一番仲が良く然も金持ちの三男坊だったので遠くへ写生に行った時等は種々の費用を出しておいて呉れた。そんな仲だったので彼の家へはよく遊びにも行き御馳走にもなり時には泊ってきた事も度々あった。 私の下宿から学校迄は相当遠かったが、当時電車等の乗物が無かったので朝早…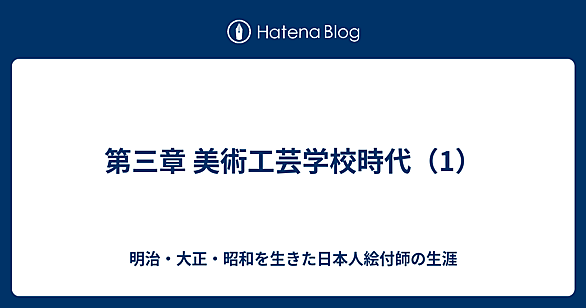 予備科では翌々年の三月迄、横山大観先生の指導を受け、絵画本科へ進学してからは鈴木瑞彦先生に教えを受ける事となった。当時考古学、美術史は校長今泉雄作氏が担当して居られた外、富岡鉄斎、竹内棲鳳(栖鳳)菊池芳文、山元春挙等の諸先生が居られ京都画壇の錚々たる大家が揃っていた。図案科では谷口香愫先生が一学年から五学年迄を担当して居られた。又彫刻科には大村西厓先生が居られ卒業生の先輩、国安稲香君が助手を務めていた。 生徒は各科にニ、三十名位で合計ニ百名余り。服装は制服と好きして安部仲麿の様な古代の官制にあった闕腋(けってき)というもので帽子は今の裁判官が使用している物と略同じである。それに緑色の絹の組紐を…
予備科では翌々年の三月迄、横山大観先生の指導を受け、絵画本科へ進学してからは鈴木瑞彦先生に教えを受ける事となった。当時考古学、美術史は校長今泉雄作氏が担当して居られた外、富岡鉄斎、竹内棲鳳(栖鳳)菊池芳文、山元春挙等の諸先生が居られ京都画壇の錚々たる大家が揃っていた。図案科では谷口香愫先生が一学年から五学年迄を担当して居られた。又彫刻科には大村西厓先生が居られ卒業生の先輩、国安稲香君が助手を務めていた。 生徒は各科にニ、三十名位で合計ニ百名余り。服装は制服と好きして安部仲麿の様な古代の官制にあった闕腋(けってき)というもので帽子は今の裁判官が使用している物と略同じである。それに緑色の絹の組紐を…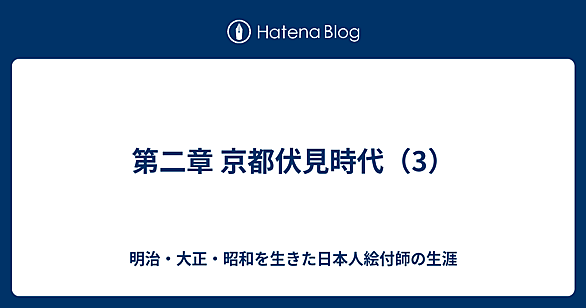 そこで腕白小僧も東京から京都へ来て、板橋の学校へ神妙に通学していた。 処が丁度付近に住んでいた稲荷の神官の息子で一級上の道楽者?私より以上に腕白で怠け者が、登校する時の良い道連れであった。毎朝誘って呉れるので始めは誠に良い友達で親切な人だと喜んでいた。処が一ヶ月すぎ二ヶ月たち、だんだんお互いに気心が判って来ると、朱に交われば、赤くなってきた腕白小僧は学校へ行って勉強するより遊ぶ方が面白くなってきて、つい誘われる儘に一日休み、又次の日も、今日は桃山へ城跡を見に行くとか、先陣争いをした宇治橋の古戦場や平等院へ行くとか、勝手な理由をつけては来る日も来る日も、朝は決まった時間に弁当を鞄に入れて如何にも…
そこで腕白小僧も東京から京都へ来て、板橋の学校へ神妙に通学していた。 処が丁度付近に住んでいた稲荷の神官の息子で一級上の道楽者?私より以上に腕白で怠け者が、登校する時の良い道連れであった。毎朝誘って呉れるので始めは誠に良い友達で親切な人だと喜んでいた。処が一ヶ月すぎ二ヶ月たち、だんだんお互いに気心が判って来ると、朱に交われば、赤くなってきた腕白小僧は学校へ行って勉強するより遊ぶ方が面白くなってきて、つい誘われる儘に一日休み、又次の日も、今日は桃山へ城跡を見に行くとか、先陣争いをした宇治橋の古戦場や平等院へ行くとか、勝手な理由をつけては来る日も来る日も、朝は決まった時間に弁当を鞄に入れて如何にも…