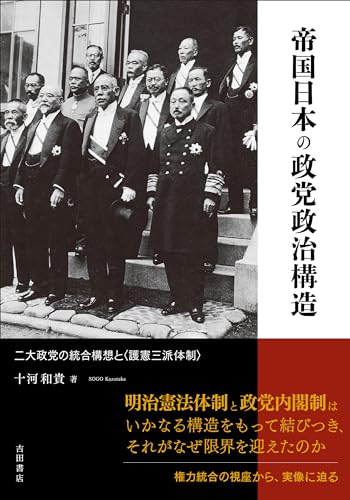西東京日記 IN はてな (original) (raw)
社会的にも政治的にも日本で最も大きな影響力を有していると思われる宗教団体の創価学会について、カナダに生まれ、現在はアメリカのノースカロライナ州立大学の哲学・宗教学部教授を務める人物が論じた本。
副題は「現代日本の模倣国家」で、創価学会をミニ国家になぞらえた見取り図のもとで議論が行われているのですが、本書の何よりの面白さは著者によるフィールドワークの部分ですね。
創価学会の家庭に入り込み、任用試験とそれに向けての勉強、創価学会における女性の役割、信者と池田大作の関係などを明らかにしていく部分は、日本人の書いた創価学会本でもなかなか描かれていないものではないかと思います。
ここでも、そのフィールドワークの部分を中心に紹介したいと思います。
ちなみに校閲もかなり厳密になされており、著者のいくつかの誤解なども注で指摘されています。
目次は以下の通り。
はじめに
第一章 模倣国家としての創価学会
第二章 知的協会から宗教へ――創価学会の歴史
第三章 創価学会のドラマチックな物語【ナラティブ】
第四章 正典への参加――新宗教における聖典の形成
第五章 若者の育成――標準化教育を通じた師弟関係
第六章 良妻賢母と改宗の歩兵たち
おわりに
監修者あとがき
前半は創価学会の模倣国家的な側面と創価学会の歴史が語られています。
模倣国家的な側面については、そういう面はあってもそれは多くの組織に共通することではないか? という思いもあるので、このあたりは読んで判断してみてください。
歴史の部分について興味深いのは、その教育学的な起源を指摘している点です。
創価学会の初代会長は牧口常三郎ですが、彼はもとは北海道で尋常小学校の教員であり、さらなる知的な取り組みを求め上京し、キリスト教知識人の新渡戸稲造とも交流を持っています。
その後、牧口は東京で再び教員となりますが、既存の学校制度を合理主義やプラグマティズムで改革しようとする彼の姿勢は同僚教師や文部省と衝突し、教職を辞すことになります。
教職を辞めた牧口は1930年に『創価教育学体系』の第1巻を刊行します。出版者は創価教育学会となっており。これが創価学会の始まりとも言えます。創価学会の出発点は学術書の刊行なのです。
実は牧口は日蓮正宗への改宗について、これといったきっかけを述べていません。1916年に田中智學の講演を聞いたことがきっかけとも考えれますが、牧口は田中の超国粋主義的な日蓮主義組織、国柱会には参加しませんでした。
1931年の満州事変以降、戦時色を強める日本の中で、創価教育学会も教育改革だけではなく幅広い目標を目指すようになり、宗教的要素も強めていきます。
1936年から牧口は日蓮正宗の総本山大石寺で毎年夏期講習会を開くようになり、年々、その参加者は増加しました。
しかし、政府の宗教統制に反発した牧口は1943年7月に逮捕され、創価教育学会も解散させられました。牧口は1944年11月に獄中死しています。
二代目会長の戸田城聖も教員出身であり、中学受験用の学習参考書『[推理式]指導算術』などを出版し、併せて100万部売り上げたといいます。さらにここで得たお金を他の事業に注ぎ込み、醤油工場や証券会社も経営しました。
戸田は『創価教育学体系』の出版費用を捻出するなど牧口に尽くしました。戸田も43年に検挙されますが、獄中で法華経と日蓮の本を読む、題目を1日1万回唱えるという目標を立て、すべての生命がつながっているという悟りを得たといいます。
1945年7月に釈放された戸田は、戦後すぐに通信教育の事業を興します。
1946年3月、創価教育学会は創価学会となります。戸田のもとで創価学会は折伏を進めるなど宗教団体として教団の拡大に動きますが、その組織に「学会」という文字は残しました。
この戸田が妙悟空というペンネームで『聖教新聞』に連載した小説が『人間革命』です。この『人間革命』は池田大作(ペンネームは法悟空)によって書き継がれ、続編の『新・人間革命』とともに創価学会の「聖典」ともいうべき存在になります。
創価学会を貫くものは日蓮仏教と近代人道主義、ロマン主義といったものなのですが、これが『人間革命』という小説の中で融合しているのです。
戸田版の『人間革命』の中で実名で登場するのは牧口のみであり、池田版の『人間革命』で実名で登場するのは牧口と戸田のみです。他は仮名であったり、何人かの人物を混ぜ合わせたような形になっているのですが、読んでいる信者は、誰だかピンときますし、池田の足跡と小説の出来事を重ね合わせながら読みます。
記述において、戸田の死後の主導権争いといった池田にとって都合の悪いことは省かれているわけですが、その代わりに一貫したストーリーが提供されています。
特に池田が戸田の後継者としての地位を固めたとされる大阪事件については劇的な形で扱っています。
池田は、1957年の参議院補欠選挙で投票日前後に何百もの有権者宅を訪問し、タバコ、現金をばらまいたという罪で他の幹部ととも逮捕されます。最終的に池田は無罪になり、この事件は弾圧に打ち勝った輝かしい事例として扱われることになるのです。
『人間革命』でも、池田をモデルとした山本伸一という人物を通して、この事件は戦時中に逮捕された牧口や戸田と同じような、あるいは日蓮が受けた弾圧と結びつけます。これによって山本(池田)は創価学会の正統な後継者としての地位を得ることになるのです。そして、戸田と池田はともに「巌窟王」・モンテ・クリスト伯のイメージとも結びつけられています。
年配の学会員に会うと、『人間革命』や『新・人間革命』を持ち出してきて、自分が匿名で登場する部分を指摘してくることがあるといいますが、こうした「聖典」に参加しているという高揚感も創価学会という新しい宗教の魅力となっていると考えられます。
近年では、池田大作が若い学会員と交流した様子や、池田が海外でさまざまな栄誉を受けた場面を集めたDVDが売られているといいます。
創価学会は「教育」を出発点としていましたが、巨大な宗教団体となった今もその性格を残しています。
父親に捨てられて母親とともに創価学会に改宗した女性は、その後の創価学会での成長を「ちがう学校」(186p)と表現していますし、今でも若い信者の育成に教育的なシステムを置いています。
もちろん、創価大学を頂点とする学校もあるのですが、本書の第5章でとり上げられている任用試験です。著者は自らこの試験を受け、その様子を報告しています。
著者が受けたのは2007年11月で、このときは13万5000人以上が任用試験を受けたといいます。この試験に合格すると助師の資格が得られます。さらに男子部/女子部は任用試験に続いてさらに難しい試験があり、三級、二級、一級と階級が3年ごとに与えられ、壮年部と婦人部では、初級試験、中級試験、上級試験があり、受かるとそれぞれ助教授補、助教授、教授になれます。創価「学会」の名の通り、ここでも学術界の名称がとられています。
試験の内容は暗記するように指定された日蓮の『御書』のくだりから抜けている単語を書く、十界を正しい順番で書く、仏教用語を感じで書くといったもので、学校のペーパーテストとよく似ています。
著者は、この任用試験のための学習グループにも参加し、学会員の家でともに勉強しながら試験に臨んだといいます。
この試験システムは若い信者、特に2世に対して生涯にわたって創価学会への献身を植え付ける役割を果たしていると考えられます。そして、学校の成績の責任が日本では親、特に母親に帰責されがちなのと同様に、子どもの創価学会での試験の成績が振るわなければ信者である母親が責められることになります。
ただし、合否だけが重要ではないといいます。著者は試験に望むにあたって調査の中で知り合った各地の創価学会員から激励の電話を受けたといいます。その中には著者の大勝利のために唱題しているのだと言ってきた人物もいて、試験の合格よりも献身が重視されていることがうかがえるといいます。
また、この試験システムは、かつて上のレベルの学校に行けなかった学会員に対して、学びを提供したという側面もあります。
1967年の読売新聞の調査によると、学会員の回答者の55%は最終学歴が中学で、その教育水準は平均と比べても低めでした。そんな彼らに戸田城聖は、学ぶことによって学会の中での地位が上がるような仕組みをつくったのです。
この学びのシステムは21世紀になっても機能していますが、その内容は易しくなっているといいます。
以前は、日蓮の『御書』を読み込んだりする必要がありましたが、今は『大白蓮華』という創価学会の機関誌の試験対策特集を読めばよい形になっているといいますし、試験も2014年からマーク方式になっています。
以前は、幹部の選抜のための制度だったものが、現在は2世、3世を創価学会の活動に参加させるための手始めという性格を強めているのです。
第6章は「良妻賢母と改宗の歩兵たち」とのタイトルで婦人部について扱っています。
学会の上層部には女性は少ないのですが、学会の日々の活動を支えているのは女性たちです。創価学会はかなり性別分業的な組織となっており、各地の婦人会館は男性は立入禁止となっています。
かつての日本政府が国民を育てるために女性に「良妻賢母」を求めましたが、創価学会にもそうした傾向があります。一方、創価学会の女性は決して従属的なだけの存在ではなく、創価学会の活動を主体的に支えているとも言えます。
また、学会員の女性たちは家を家族の空間としてだけでなく学会活動の場としても提供し、時間的にも家庭生活と学会活動の両立を図る必要があります。中にはこれが原因で破綻してしまう家庭もあるのです。
著者は実際に創価学会家庭に入ってフィールドワークをしていますが、そこで熱心に学会活動をしてきた母親に対して30代の息子が「世界平和だって? 世界平和のために戦いに出かける前に、なんで自分の家の平和を守らなかったんだよ?」と問い詰める声を聞いてしまったりもしています。
その息子によれば、彼の両親は夜の6時〜9時はいつもおらず、弁当なども自分で作っていたとのことです。その時間、両親は学会活動をするか、娘を創価大学にいれるために働いていました。
この家庭では一時期夫婦仲も悪くなったそうですが、こんなときに母親は何をしたかというと南無妙法蓮華経を100万回唱えるということです。問題は学会活動ではなく、むしろ活動の不足にあると捉えられたのです。
彼女は睡眠を3時間程度にまで減らして200万回、300万回と唱題を増やしていき、そのうち夫も一緒に唱題を行うようになりました。そして夫婦で1000万回という記録を達成し、その過程で夫婦仲も修復されたとのことです。
戸田城聖は、女性信者の力を認め、学会発展の鍵は女性にあると考えながらも、一方で「竜女は竜女で、これは直らないだ。女からヤキモチとか、貪欲とか、グチを取ろうたって、取れない、あるのが当たり前なのだ」といった女性蔑視的な発言もしています。
ただし、だからこそ欠点を持つ女性はより真剣にご本尊にすがらなければならないという考えも生み出します。
池田大作が会長になると、創価学会は日蓮仏教に焦点をあてた運動から、文化を通じたもっと包括的な社会への取り組みへと転換し、全国に女性コーラスグループがつくられました。文化活動によって女性を組織しようとしたわけです。
1970年代に婦人部の重要性が高まると、池田の妻である池田香峯子の存在感も増してきます。一方、学会の上層部からは女性は排除され続けました。
本書では夫婦どちらも創価大学を卒業した第2世代の学会員である渡辺夫妻の様子も紹介しています。
夫婦共働きの家庭で婦人である渡辺さんは忙しくしていますが、一般家庭よりもさらに忙しいのは夜7時半の集会に学会員が自宅にやってくるからです。家事はその前までに済ませておかなければなりません。
集まってきた学会員たちは支部長を中心として、聖教新聞の購読数のグラフなどを確認し、改宗しそうな人の情報を交換します。さらに任用試験の受験予定者などを報告し、みんなに成功のために唱題するように依頼します。
つづいて婦人部長が地域フェスタや選挙の話、聖教新聞の購読状況などの話をします。そして情報共有がなされ、フェスタの内容をどうするか? 購読数を増やすにはどうするか? といったことが話し合われるのです。
仕事と家事に加えて、こうした学会活動がプラスされているわけですが、これを可能にしているのは渡辺さんの驚異的な頑張りやスケジュール管理です。
もちろん、こうした熱心な親が子どもを傷つけることもあるわけで、本書がとり上げている美穂さんもそうした例です。ただし、難しいのはそうした美穂さんもルーチン化した学会活動はくだらないと思いつつも、『人間革命』に描かれた戸田や池田の初期の情熱には感動しており、学会から完全に離れたわけではありません。
創価学会の教えはほぼ絶縁した粗暴な父親との絆でもあり、あっさりと捨て去ることはできないのです。
創価学会は既婚女性に立派な2世信者を育てる良妻賢母を求めていますが、学会の活動は家庭的な役割から母親を引き離します。
また、創価学会の組織はジェンダー化されており、この組織が社会の変化に対してどのように対応できるのかは未知数です。
とりあえず、現在の創価学会は母親にかなり負荷をかけながら、その活動を継続させている状況です。
最初にも書いたように前半の創価学会を擬似国家に見立てる理論的な部分についてはそれほどピンとこない部分もあるのですが、後半のフィールドワークから見えてくる、学校的なシステムとしての学会、学会におけるジェンダーの部分は面白いです。
また、著者が外国人であり、しかも日本語が相当にできるということがこの貴重なフィールドワークを可能にしているのでしょう。
創価学会がどんな組織であり、どんな人たちがどんなスタンスで参加しているのかということをうかがい知ることができる貴重な本です。
監督のアレックス・ガーランドは『28日後...』の脚本の人だということを見終わってから知って、「なるほど」と思いました。
『28日後...』はストーリーとうよりはシチュエーションやシーンを中心に構成された作品ですが、この『シビル・ウォー』もそうだと思います。
監督兼脚本のアレックス・ガーランドが描きたいのは、アメリカ内戦のストーリーではなくて今のアメリカに生まれそうなシチュエーションやシーンなんですよね。
『シビル・ウォー』は内戦に突入したアメリカを描いた映画ですが、内戦の過程を描くのではなく、内戦の中でニューヨークからワシントンD.C.へと向かう(危険な地域を避けるためにかなり回り道をしながら)、ジャーナリストを描いたロードムービーになっています。
ファシスト的な大統領が憲法を無視して3期目に突入し、FBIを解散させるなどの行為を行ったため、テキサス州とカリフォルニア州の同盟からなる「西部勢力」が連邦から離脱し、内戦が始まるという設定で、映画ではこの「西部勢力」がワシントンD.C.に迫っているという状況になっています。
途中で大統領が国内への空爆を命じたということなどは出てくるのですが、圧倒的な航空優勢があるはずの連邦軍が州軍主体と思われる「西部勢力」に押されている理由などは特に明示されません。
ちなみに「テキサス州とカリフォルニア州の同盟」というのは代表的なレッド・ステイトとブルー・ステイトを並べたわかりやすい弾除けですよね。
といわけで、この映画が描きたいのシチュエーションやシーンです。内戦下のアメリカということで当然ながら残酷なしーんも出てくるわけですが、ここでは主人公のリー・スミスと彼女に憧れるジェシーがともに戦場カメラマンであり(ジェシーは戦場カメラマン志望)、共に旅をするジョエルやサミーもジャーナリストであるということがその残酷さを和らげます。残酷な状況も1枚の写真として切り取られ、過去のものになるからです。
また、音楽も映像の緊張をずらすために使われていたりして、緩急をつけながら観客に内戦下の緊迫感を伝えるような構成になっています。
この内戦下の緊迫感を観客に体験させるという点でこの映画は成功していると思いますけど、個人的にはラストの部分でリアリティが崩壊してしまっているとも感じます。
以下ネタバレなので嫌な人は読まないでください。
犯罪小説の名手として知られるロス・トーマスの初期の長編。とは言っても、個人的にはロス・トーマスの作品を読むには初めてですし、あまりこの手の小説は読まないのですが、アフリカの選挙戦を扱った作品ということで読んでみました。
Amazonに載っている紹介文は以下の通り。
辣腕の選挙コンサルタントとして鳴らしたシャルテルは、大手広告代理店DDT広報部のアップショーとともに、英連邦から独立間近のアフリカの小国アルバーティア初の国家元首選挙に駆り出される。資源に恵まれながらも腐敗にまみれたこの国で、DDTに有益な人物を当選させるために、二人は汚い手段を駆使してでも選挙キャンペーンを成功させようとする。だが、やがて事態は混乱をきたし、彼らにすら手に負えない様相を呈してくる――。MWA最優秀新人賞受賞作『冷戦交換ゲーム』に続く第2作にして、アフリカ諸国の政治的カオスを活写し暴力描写に溢れたクライマックスが印象的な、ロス・トーマスの初期傑作、本邦初訳。
独立直後の最初の大統領を決める選挙ですが、ここに広告代理店や選挙コンサルタント、さらにはCIAまでが乗り込んできます。
主人公たちはイギリスの大手広告代理店から依頼を受けながら、敵対する代理店やCIAを出し抜いて選挙の勝利を掴もうとするわけです。
ダブルスパイを使ったり、ヘリや飛行船を持ち出したりとなかなかダイナミックな作戦を使うわけですが、原著は1967年に出版されているということもあって、まだ持ち出されている手段は大雑把です。
時代を感じるという点でいうと、主人公のアップショーがアフリカに行くと、すぐに平和部隊の一人としてきているアメリカ人の若い女性と知り合っていい感じになるんですけど、あまりにあっさりといい仲になるので、「こいつはスパイなのか?」と思いながら読んでいたら全然そんな事なかったです。
この時代、助成に関するご都合主義はあって当然で、現代の感覚で疑ってはいけませんね。
というわけで「選挙」を期待するとやや物足りないところもあるのですが、ストーリーとしては読ませます。
選挙コンサルタントのシャルテルという人物の造形や、まさに立ち去ろうとしているイギリスの植民地官僚の姿などはよく描けていますし、最後のドンデン返しからラストへの流れも鮮やかです。
エンタメ的な小説としては十分な面白さがあります。
自分は1970年代半ばの生まれで、90年代の前半に明治大学に入学したのですが、入学式の日にヘルメットを被った活動家の人たちが新入生にビラを配っている光景に驚いたのを覚えています。
もうなくなったと思っていた学生運動的なものがまだ残っていたことに驚いたわけですが、それくらい70年代後半〜90年代にかけて学生の政治運動というものは退潮してしまった(少なくともそのイメージがあった)状態でした。
これはなぜなのか?
この70年代後半〜90年代にかけての若者の政治や社会運動からの撤退の謎を、1974年に創刊され、85年に刊行を終えた雑誌『ビックリハウス』の分析を通して明らかにしようとしたのが本書です。
『ビックリハウス』については糸井重里による「ヘンタイよいこ新聞」のコーナーなどが今までも社会学者などによって分析されてきたので、ご存じの方も多いでしょう。自分も世代ではないですが、宮台真司や北田暁大の著作を通じてある程度のイメージがありました。
ただ、本書の著者は86年生まれであり、完全に『ビックリハウス』が終わったあとに育った世代になります。
そこでどうしたかというと、約10年分の『ビックリハウス』をすべてテキスト化し、計量テキスト分析をかけるという荒業を行っています。この計量分析と内容の分析を通じて、なぜ若者の中で政治や社会運動を冷笑、揶揄するような姿勢が強まっていったかを探っています。
もちろん、『ビックリハウス』の分析だけで、70年代後半以降に日本社会でおきた大きな変化のすべてを説明できるわけではないですが、1つの雑誌の分析を通じて、社会の変化の一端を捉える興味深い内容になっています。
目次は以下の通り。
第1部 日本人は政治と社会運動に背を向けたのか?――問題意識・先行研究・方法と事例
1 消費社会と私生活主義は日本人を政治から遠ざけたのか?――問題意識
2 「雑誌の時代」と『ビックリハウス』─先行研究
3 事例、方法、分析視角
第2部 戦後社会の価値変容――戦争経験、ジェンダー、ロックの視点から
4 語りの解放と継承のずれ――「戦後」から遠く離れて
5 女性解放――運動がなしえた個人の解放、解放された個人への抑圧としての運動
6 「論争」から「私的」へ――みんなで語るそれぞれのロック
第3部 みんなの正しさという古い建前、個人の本音という新しい正義
7 社会運動・政治参加――規範と教条主義に対する忌避・回避
8 「差別」が率直さの表明から不謹慎さを競うゲームになるまで
9 自主的で主体的な参加の結果、「政治に背を向けた」共同体
10 意図せざる結果への小路――考察と結論
おわりに
70年代後半以降、若者が政治や社会運動への関心を失っていった理由として、「私生活主義」や「マイホーム主義」の広がりといったことがあげられますが、これは公と私を対立的に見る見方であり、例えば、70年代に立ち上がった生活クラブなどの消費を通じて社会を変えようという運動などを見ると、かなり単純化された見方だと言わざるを得ません。
また、70〜80年代にかけて、デモや選挙について有効性を感じる人は減る傾向がありますが、「集会・会合出席」、「署名」といった行為は80年代にかけてむしろ増えてる傾向もあり、一方的に政治的活動が不活発になったわけではありません。
それでも、当時の若者は「基本的には「政治に背を向けた」私生活主義を体現する存在」(46p)として論じられてきました。
本書はそうした若者を中心とする読者共同体を形成していた雑誌に注目しています。
70年代〜80年代は数々の雑誌が創刊された時代で、若者の世代的アイデンティティの構築に大きな役割を果たしました。また、当時の雑誌は読者からの投稿・投書を募っていたものが多く、そこで読者共同体がつくられました。
この時期には、政治的・対抗的な色彩の強いサブカル誌が創刊されています。『面白半分』、『話の特集』、『宝島』などです。そして、政治性・対抗性を有しているにもかかわらず、歴史的にそうとはみなされていなかったのが『ビックリハウス』だといいます。
『ビックリハウス』も初期のコンセプトは「ヒッピー・ジェネレーションのサバイバル教本、『ホール・アース・カタログ』に影響された」(75p)とあるように、対抗性を持っていたはずなのですが、後世からはそうした評価はなされていません。
大塚英志が「「プロと素人の差を喪失させようとしている」点に階級を解体させる意図をもつ「革命」を読み取っている」(77p)ように、ある種の革新性はあったのですが、それは政治的関心を欠いた「未政治運動」の共同体のような形で終わっています。ここに著者は注目するわけです。
『ビックリハウス』は1974〜85年までパルコの出資でタウン情報誌として創刊されたもので、アングラ劇団「天井桟敷」で活動していた萩原朔美と榎本了壱がパルコに企画を持ち込んだことから始まりました。
1977年からは高橋章子が二代目編集長となり、「新人類」「女性」の旗手として各種メディアでもとり上げられました。編集部も女性が多数を占めるようになったといいます。
80年前後からは糸井重里や橋本治が編集・寄稿に加わり、連載を持った有名人もYMO、おすぎ、鈴木慶一、栗本慎一郎、ナンシー関、赤瀬川原平、日比野克彦、村上春樹、三浦雅士、とんねるず、犬飼智子など多岐にわたりました。
ただし、部数的には83年のピーク時で18万部で、高橋章子によると公称10万部で実際は5万部という程度の部数にとどまっています。
読者の平均年齢は18歳前後で男女比は半々、ただ投稿者の割合は2:1で男性が多く、高校生、浪人生、大学生からの投稿が多かったといいます。好きなタレントでは82〜84年にかけて戸川純とビートたけしがトップを占めていました。
第2部ではこの『ビックリハウス』について、「戦争(反戦・平和・運動)」「女性(フェミニズム・ウーマンリブ)」、「ロック(対抗文化)」という3つのテーマについて、計量テキスト分析を通してその言論の特徴を浮かび上がらせようとしています。
まずは「戦争(反戦・平和・運動)」です。
この話題について、『面白半分』は安保についての連載があり、『話の特集』は海外ルポタージュで反戦・平和の話題がとり上げられていました。重信房子の連載「ベイルート1982年夏」が連載されたのも『話の特集』です。
読者層がやや若かった『宝島』でも、「アトミック・カフェ・フェスティバル」、ジョン・レノン追悼キャンペーンなどでこうしたテーマに触れています。
一方、『ビックリハウス』ではどうだったのでしょうか?
70年代後半については、戦争は戦争映画の紹介記事、著名人の体験談として戦争が語られていることが多いです。
一方、80年代に入ると映画の他に、スネークマン・ショーによる「戦争反対」キャンペーンについての賛同や投稿も目立ちます。このスネークマン・ショーのキャンペーンはネタなのかマジなのかわからないものですが、読者は比較的「マジ」に受け取っていたといいます。
同時に親や教師が語る戦争体験の話が「おもしろエピソード」的に紹介されているのもこの時期の特徴です。
この時期は、戦争経験者によって周囲の職場などに戦争経験者がいなくなり、「戦友」以外にも戦争の話をするようになった時期だとも言われていますが、『ビックリハウス』ではこうした話が最近びっくりしたことを報告する「ビックラゲーション」の中で紹介されています。
例えば、「政・経の中村先生は友人Tを「起きんかっ!」と、どなったあと「満州で蒙古人150人を扱うには、これくらいの声が必要だ」と、おっしゃった」という投稿と、それに対する「中村先生の戦後は、まだ終わってないっっ!! ほおっておいていいんだろうかー。生徒としてどう対処すべきか考えよ。騎馬民族の衣装で投稿するとかさ。ちょっと、ハデかな。」とう編集者のコメントです(139p)。
ここでは特に編集者のコメントによって戦争経験が「笑い」の文脈に回収されています。
この時期のサブカル誌は女性解放や性の開放、個の開放を後押ししつつも一部の女性運動には極めて冷ややかな目を向けていました。例えば、中ピ連(中絶禁止法に反対しピル解禁を要求する女性解放連合)の代表であった榎美沙子は『話の特集』の嫌いな著名人の常連でしたし、『宝島』でも攻撃されています。
『ビックリハウス」でも2代目編集長の高橋章子は働く女性のロールモデルのように見られていた時期もあり、男性読者の「女の人は結婚に逃げられるからうらやましい」という発言に「そういう考え、許せないなあ」(154p)と応じているように、性別分業的な考えを強く批判しています。
一方、『ビックリハウス』の投稿や編集者のコメントに通底するものとして主婦への蔑視があります。アダルトビデオ廃止運動を行う女性に対して「だから主婦ってバカだって言われちゃうんですよ」(157p)と編集者がコメントしているように、頭の硬い暇人のように扱われています。
かといって、バリバリのキャリアウーマンが理想視されているわけでもなく、こちらも揶揄の対象になっています。
「性」についての部分でも、頻出語として「おっぱい、胸、バスト」、「尻、おしり」などがありますが、自虐的な笑いとともに言及されることが多いです。
『ビックリハウス』の編集者たちは女性解放には基本的に同調しつつも、「女性であることの構造的不利を主張する女性解放運動に対して距離を置く言明を強調して」(169p)いました。
高橋は女だからお針セットくらい持ってないとヘンだという言説に対して、それはヘンだと認めつつ、「しかし、ヘンだからといって女性差別反対とか言ってプラカードなどかついだりしないところが私のエライところである」(170p)と自著の中で述べています。ここには社会運動的なものへの忌避とともに、ある程度の社会参加を成し遂げた自分たちにとって女性解放運動は、自分たちを再び「女」という柵に囲い込むものだという意識もあったのではないかと著者は見ています。
最後は「ロック(対抗文化)」です。ロックに関しては、その後も「洋楽の歌詞を理解しなければ聴いたことにならないか?」「ロックとは音楽ではなく生き方」みたいな論争があり、「本物のロック」「本物のロックファン」をめぐる論争があったりするわけですが、それは70〜80年代にかけてもありました。
特に『宝島』では、1978年に「ロック論争」が行われるなど、ロックの衰退や「ロックとはなにか?」といったことが論じられています。
『ビックリハウス』でも1976・77年に読者投稿欄でロック論争が行われています。
特に77年6月号に載った、日本人は歌詞を理解しないで聞いているから日本のロックシーンが進歩しないという18歳の男性からの投稿は大きな反響を呼びます。
これに対して編集部は論争については「けなしあい」「あげあし取り」が多かったとして、理論ではなく「極私的ロック論」を募集します。
編集部はどのようなあり方が正しいかではなく、私はこんな風に聴いているという多様な聞き方の共有を目指したのです。
この歌詞の正確な理解を重視せずに、人それぞれの聴き方を重視したという点では同世代の音楽雑誌『ロッキング・オン』と通じる面があります。
第3部では第2部の分析結果をもとに、どうしてこのようになったのかが読み解かれています。
まずは社会運動や政治参加への忌避です。女性解放運動についての評価にあるように『ビックリハウス』の読者・編集者共同体は、性別役割分業などを否定していましたが、同時にそれを告発する女性解放運動からは距離を置こうとしていました。
この『ビックリハウス』の特徴は、他のサブカル誌とは少し違っています。『話の特集』はキーパーソンの矢崎泰久・中山千夏が政党「革新自由連合」を結成したこともあり、選挙活動の記録などが載っていました。『面白半分』も『話の特集』ほどではありませんが、野坂昭如の「四畳半の下張」をめぐる裁判がとり上げられていました。『宝島』でも学生運動や時事問題に対する言及があります。
『ビックリハウス』でも政治への言及はありますが、1978年を境に「戯画化・パロディ化」して論じる傾向が強くなるといいます。
例えば、1980年12月号には読者アンケートに基づく記事があり、その中に「鈴木善幸をどう思いますか?」という質問があるのですが、「きらい」という声が多くある一方で、「名前まけ」「サロンパスくさそう」「かわいい」「ホクロの場所が今イチ」などのイジり的なコメントが目につきます。
また、ストに対する言及でも、パロディや日常のびっくりネタのような形で言及されていることが多いです。
パロディについては、そこに政治性や対抗性があるべきだという議論もありますが、『ビックリハウス』の寄稿者でもあったタモリや糸井重里はそういったスタンスを批判しており、また高橋章子も『ビックリハウス』のパロディを「オチョクリ」だと語っています。
『ビックリハウス』の基本としてあるのは「べき論」への忌避であり、それは例えば、1983年の村上春樹の寄稿の中の自分のつれあいが絶対に投票にいかないことに関して、「「それは権利を放棄していることだ」と言う人がいるけれど、権利というものは本来的にそれを放棄する権利も包含しているのであって、そうでなければそれはもう権利でもなんでもないのである」(231p)という文章にも現れています。
こうした「べき論」への忌避は学生運動の経験者でもある糸井重里からも持ち込まれていますし、学生運動の世代ではない高橋章子(52年生まれ)も学生運動についてカッコ悪いというという認識を持っています。
また、糸井重里・栗本慎一郎の「空飛ぶ教室」では、よく「国家を感じる」というスラングが用いられていますが、これは「共同の幻想としてイヤともなんとも感じないウチに押し付けられ、無意識にそーさせてしまう力」(235p)と説明され、学生運動や社会運動などが「国家を感じる」ものとされています。
本来ならば、国家に対抗しているはずの運動が、教条主義的なものへの忌避という視点で国家と同一視されているのです。
第8章ではマイノリティに対する言説が扱われています。
『話の特集』、『面白半分』では、社会問題をとり上げつつも同時に差別語の禁止に対する反対姿勢も目立ち、差別語をふくむ「率直さ」を養護するような姿勢も目立ちます。『宝島』もそうですが、「ゲイ」や「女性」を未知の世界として見るような記事、田舎いじりの記事(「VOW」)も目立ちます。
『ビックリハウス』でも表現規制に対する反発は他誌と共通しており、一貫して表現の自由を養護する立場に立っています。
しかし、例えば、性的マイノリティについて『宝島』が啓発的な視点も持っていたのに対して、『ビックリハウス』では笑いのネタとして扱われています。
日用品の別の使い道を考えるコーナーでは、先割れスプーンについて、「スプーンでもフォークでもない特徴を生かして、おかまの人たちの代名詞として使う」、「おしりの穴に刺し、ホモよけに使う」(253p)といった投稿が載っています。
編集者のコメントで「差別ですよ」というツッコミも見られますが、それは怒りや注意ではなく、笑いを誘うためのものであり、すべてを差別認定することで差別用語の無意味さを逆説的に示す形になっています。
また、あえてギリギリの表現を用いることで笑いを誘う、不謹慎さを競うゲームのような投稿も見られるようになります。
「マイノリティ」と言えるかどうかは微妙ですが、「田舎」「地方」に対するいじりや差別的な視点は『ビックリハウス』の定番で、田舎のダサさを笑うのが基本的なスタンスでした。
『ビックリハウス』の編集部は特に読者たちを誘導しようという意図はなく、若者たちの感性を重視しました。
高橋章子が「宗教の人たちが”答”を教えている、あれはうちは絶対ナシでやってるから。自分の思ったことを言えという一点でやり続けてる。それが、それこそこちら側のメッセージだね」(276p)と述べていますが、それはある意味で規範性や教条主義を排した「民主的」な態度でした。
このスタンスを例えば鶴見俊輔は評価しているのですが、一方で椎名誠は「この種の奥社参加型雑誌のいやらしいところは素人がプロに媚びているところ」「投稿者は目下のウケウケの傾向を素早く察知し、編集長がヨロコビそうな話やセリフをしこたま送り込んでくる」(278p)と批判的に見ています。
実は初期の『ビックリハウス』では「フルハウス」という評論や社会的主張を募集するコーナーがあったのですが、投稿が集まらずに終わっています(寄稿者には高校生時代の中条省平もいたとのこと)。
そこで読者投稿を集めやすいものとしてクローズアップされたのがパロディや体験談でした。 これによる政治性・対抗性はますます抜け落ちます。これについて著者は次のように述べています。
つまり、『ビックリハウス』という政治性・対抗性なき若者共同体は、編集者たちが読者たちを社会運動への揶揄や率直な差別発言をするように導いたから成立したわけではなく、投稿という自主的・主体的な行為による共同体への参加と、その参加の敷居を下げるためのシステム構築によって成り立つ「意図せざる結果」だったのだ。(282p)
最後の第10章では分析の結果として得られた知見を既存の世代論などと比較検討しています。
また、『ビックリハウス』の女性編集者が主婦でもキャリアウーマンでもない「どちらでもない」人間を目指したものの、男性編集者や読者から「ブス」「いき遅れ」という枠に当てはめられ、そして自虐的にそれを内面化してしまう様子も紹介されています。
規範や啓蒙から距離を取ろうとした彼女らにとって、こうしたレッテルを強く拒否するという行動は生まれにくいのです(彼らが反対する言葉狩りになってしまう)。
このように本書は70年代後半〜80年代にかけての社会の変化について、『ビックリハウス』という雑誌を通じて分析しています。
もちろん、本書の分析で変化のすべてが説明できるものではないですが、若者の変化を用意したある種の構造を説明しており面白いです。
そして、読んでて感じたのは『ビックリハウス』と現在の学校文化の意外な近さ。
『ビックリハウス』は当然ながら「反・学校」だったはずですが、現在の学校では生徒の自主性や感性が尊重され、生徒の授業参加や意見表明を求めながら、政治や社会運動については忌避するという、本書が分析した『ビックリハウス』的な構造があります。また、投稿者とそれを取捨選択する編集者という関係も現在の生徒と教師の関係ににているかもしれません。
学生運動が遠い過去のことになったにもかかわらず、相変わらず日本の学校において政治や社会運動が忌避されている要因というのは改めて考えるべきかもしれませんし、ここからは『ビックリハウス』が尊重した読者の「主体性」が本当に主体性足り得るものだったか?という疑問も生まれてきます。
(そして、この『ビックリハウス』と学校の問題は、北田暁大が『嗤う日本の「ナショナリズム」』で分析した「天才たけしの元気が出るテレビ」におけるアイロニーとベタな感動の同居につながっていて、現在の学校ではアイロニーをベタな感動で乗り越えようという努力がなされている)
その他、分析の中から浮かび上がる、主婦、特に表現規制などの運動をする主婦への揶揄や蔑視などもジェンダーと社会運動の観点から興味深いと思いますし、さまざまな楽しみ方ができる本だと思います。
最近流行りのバンドものですが、登場人物3人をギター、ベース、ドラムではなく、ギター、キーボード×2という編成(キーボードの一人のルイはテルミンなどの他の楽器もやる)にしているのがまずは正解。
始めたばかりの素人がギター、ベース、ドラムのスリーピース編成で聞かせる演奏をするというのはよほどの天才でない限り難しいと思うのですが、リズムを電子ドラムに任せることで、そのあたりをうまく処理している。
そして、最後のライブシーンでは3曲披露するのですが、そのどれもがいい!
音楽は牛尾憲輔なのですが、作中で3人がそれぞれつくっているという設定を組んで、まったく違うテイストの曲を3曲用意している。
ライブシーンは最後のみで、そのために序盤から終盤にかけてのアクセントいう点に関してはやや弱いのですが、その不満も最後のライブで解消されますね。
ドラマに関してもやや弱い面があり、バンドを組む3人のうち、主人公のトツ子以外のきみとルイはそれぞれ家族との間の問題を抱えているのですが、きみが突然学校をやめた理由の説明もやや弱いと思いましたし、ルイは母親に対して音楽活動を隠そうとする理由も、医者になって自分の跡を継いでくれというプレッシャーがあるのはわかりますが、あの母親像からするとやや弱い気がしました。
ただ、きみに関してはドラマの弱さをキャラデザの良さで補えている感じですね。
本作にはシスター日吉子(声が新垣結衣)というほぼ完璧な美形なキャラが登場するのですが、きみはそれとはちょっと違った強さを持った美形で、主人公のトツ子が惹かれるのもわかるようなデザインになっています。そして、山田尚子監督+サイエンスSARUということで、アニメとしての動かし方もうまいですね。
あと、この映画の問題というか蛇足はミスチルのEDですかね。主人公たちのやるバンド(しろねこ堂)がギターバンドならありだったのかもしれませんが、最初にも書いたように主人公たちのバンドが方向性の違ったものなので、あまり映画の世界にうまく接続できていないと思います。
全体的にやや地味な話ではありますので、ミスチルの主題歌はプロデューサー的には一種の保険なのだと思いますが、ここまで劇中曲が良いのなら、EDもしろねこ堂で良かったと思います。
芥川賞受賞作の「春の庭」他、「糸」、「見えない」、「出かける準備」を収録しています。分量的には「春の庭」が中編、他は短編という形になります。
読んでからちょっと時間が経ってしまったこともあるので、ここでは表題作の「春の庭」だけをとり上げます。
主人公の太郎は世田谷の取り壊しが決まったアパートに住んでいます。取り壊しが決まっているので契約期間が終わった住人から出ていくようなアパートなのですが、太郎はギリギリまでそこに住もうと考えています。
そんなときに、住人の一人の西という女性が、アパートの隣の「水色の家」に並々ならぬ関心を示していることを知ります。
ひょんなことから太郎は西と酒を飲んだりするようになり、西が「水色の家」に関心を持つ理由や西の生活ぶりなどを知ることになります。
ただし、太郎と西の間に恋愛的な要素はなく、二人の関心はあくまでも「水色の家」です。このあたりの「住宅」というものを丁寧に描こうとする姿勢は著者ならではですね。
そして、柴崎友香といえば後半の「あっ」となる展開が1つの売りだと思いますが、本作の特徴は最後に太郎の姉というまったくの外部の視点が挿入されることですね。
基本的にアパートとその裏の狭い空間を舞台にした閉じた小説なのですが、ここで開かれることになります。
『寝ても覚めても』や『わたしのいなかった街で』のほうが、より「あっ」となる小説ですが、この「春の庭」も著者の特徴が感じられる作品です。
1924年の加藤高明の護憲三派内閣以降、政友会と憲政会(→民政党)が交互に政権を担当する「憲政の常道」と言われる状況が出現しますが、なぜ、このような体制が要請されたのでしょうか? そして、この政権交代の枠組みを運営したのは誰なのでしょうか?(明治憲法のもとでは議会での多数派が組閣を導くわけではない)
また、護憲三派内閣以降の政党内閣の歴史は「政友会の堕落の歴史」のように語られることがあります。
田中義一は鈴木喜三郎などのファッショ的な人物を政友会に取り込んで選挙干渉を行い、対外政策では幣原外交を捨てて対中政策で失敗し、その後の浜口内閣に対しては軍部と結託して統帥権干犯問題を持ち出し、五・一五事件のあとは鈴木喜三郎総裁への西園寺の不信感から政権が回ってこず、天皇機関説問題では右翼と組んで政党内閣を支えた理論にとどめを刺す、こんなイメージもあるのではないかと思います。
なぜ、初の本格的政党内閣をつくった政友会は自ら政党内閣の寿命を縮めるような行為をしてしまったのでしょうか?
こういった疑問とともに本書を読んでいくと、そこに浮かび上がってくるのは「明治憲法における各省の割拠的体制をいかにして統合していくのか」という問題です。
本書はこの問題を中心にして、元老の再生産問題、護憲三派内閣の位置づけ、植民地統治と拓務省をめぐる問題、各省の割拠性を克服するための田中内閣、浜口内閣、第2時若槻内閣、犬養内閣の取り組み、さらに斎藤実内閣に対する政党のスタンスなどを見ていきます。
個人的には田中義一内閣の性格付けと、斎藤実内閣がうまくいった要因と、うまくいったがゆえに政党内閣復活の機運がしぼんでいく部分などを特に興味深く読みました。
この時代の政治についての知識がある程度ある人向けの本ではありますが、日本近現代史に興味がある人はもちろん、幅広く政治に興味がある人が読んでも面白いと思います。
目次は以下の通り。
序 章 政党内閣制を権力統合の視座から問う意味
第Ⅰ部 「挙国一致」の変相としての「護憲三派体制」
第一章 大正後期の政局と宮中の台頭――松方正義・牧野伸顕・平田東助を中心に
第二章 二大政党の権力統合構想と「護憲三派体制」の確立
補 論 植民地統治をめぐる相克――文官総督制下の台湾を中心に
第Ⅱ部 「護憲三派体制」における二大政党の統合構想とその限界
第三章 田中内閣の拓務省構想と外務省への挑戦――産業立国の射程
第四章 浜口内閣の政策体系と第二次若槻内閣の行政改革構想――制度的統合への帰結
第五章 犬養総裁期政友会の行政制度設計とその終着――「責任内閣政治」の隘路
終 章 二大政党の統合構想と「護憲三派体制」
明治憲法の国務大臣単独輔弼や天皇大権と結びついた多元的な権力機構は、専決的な権限を持つ首相(大宰相主義)と議会に対して連帯して責任を負うイギリス流の議院内閣制をともに排除していました。
一方、天皇無答責の原則は天皇が実際に統合を担うことを許しておらず、体制運用のためには明文規定とは異なる何らかの統合主体が必要となっていました。
当初、これを担ったのは藩閥勢力(元老)であり、つづいて政党がこれを担うことになります。
美濃部達吉は国務大臣が天皇だけでなく議会に対しても政治上の責任を負うとして、その国務大臣の合議体である内閣(閣議)を最高意思決定機関とすることで、明治憲法体制の分権性を克服できると考えました。
そして、この閣議の統一性のためには大臣が同一の政見をを持つ組織から組織されていることが必要で、ここから政党内閣制が要請されます。
つまり、政党の結合力でもって官僚機構の統合を図ろうというわけです。
しかし、結果としてみれば、日本では十分に官僚を「政党化」することはできず、政党内閣は各省の割拠性に悩まされ続けました。
第1章では元老が消えていく中で、その役割を誰が担うのかという問題がとり上げられています。
元老といえば思い出されるのは山縣有朋ですが、ここで注目されているのは松方正義です。松方は元老であり、1917年からは内大臣を務めていました。
1921年、中村雄次郎宮内大臣が宮中某重大事件の責任を取って辞職すると、松方は後任に牧野伸顕をつけます。牧野は松方と同じ薩派ですが、松方は牧野に「宮内の首脳」としての働きを期待していました。
高橋是清から加藤友三郎に首相が交代する際、松方は宮内大臣の牧野も後継首相の決定に関与させ、山本権兵衛や清浦奎吾も巻き込む形で話を進めます。
このときに山本や清浦と並び「準元老」とされていた平田東助が外されたこともあって、松方・牧野と西園寺公望・平田の対立構造があったとされていますが、本書では平田の考えも実は松方・牧野と近かったことを指摘しています。実際、平田は1922年に松方の推挙もあって内大臣になっています。
松方には元老再生産の考えがあり、自分たちがいなくなったあとも元老的な存在が必要だと考えていました。そのために行われた人事が牧野宮相であり、平田内大臣だったと考えられます。彼らを宮中の要職につけることで後継首相の選定に関与させようとしたのです。
本書は、内大臣秘書官長の入江貫一の残した史料などをもとにして平田の構想を探っています。
平田は内大臣を廃止、あるいは存続させたうえで5人以内の内輔を設置するというもので、元老再生産の意向があったものと思われます。
この構想は西園寺と牧野が難色を示したために立ち消えになりますが、著者はここからも松方と平田が同じような考えを持っていたとみています。
その後、平田は病気で内大臣の職を退き、後任が問題になります。牧野は斎藤実を推しますが、西園寺は牧野の就任を求め、東郷平八郎の就任の可能性も示して、これを承諾させます。
なぜ、牧野にとって東郷は駄目だったのか? 著者はこの問題を牧野が内大臣秘書官長に引き抜いた大塚常三郎を通じて読み解きます。
大塚は長年、朝鮮総督府で働いていた人物で、原敬による朝鮮の「内地延長主義」に対抗した人物でもありました。原は政党内閣による権力一元化の一環として、朝鮮総督府にも政党勢力の進出させようとするわけですが、大塚はこうした政党勢力の浸透に対抗して「朝鮮議会」設置構想などを打ち出しています。
この政党との距離感がポイントで、党派化が著しかった内地の地方官よりではなく党派化に抵抗していた植民地官僚の大塚がふさわしいと考えられた背景には、内大臣秘書官長も党派性があってはいけないという牧野の考えがあったと思われます。
そして、牧野にとって東郷は政党勢力と適切な距離をもって判断できる人物だとはみなされていなかったとも考えられます。
牧野は政党内閣を認めつつも、それと距離をとる宮中要職の能動化によって、安定した政治の運営を目指そうとしていたのです。
第2章では護憲三派内閣の成立とその後の第二次加藤内閣への動きがとり上げられています。
議院内閣制を否定する明治憲法のもとでは政党内閣にも何らかの「挙国一致」の要素を残そうとする動きが起こることになります。原敬内閣では政友会による一党支配体制が構築されて「挙国一致」的な雰囲気が出たのですが、その後に政党による「挙国一致」が実現したのが護憲三派内閣ということになります。
政党内閣による政権交代が視野に入ってくると、政策の連続性を担保するための後藤新平の「大調査機関」といった構想が出てきます。この構想は単純に政策の統一性を保証するだけでなく、各省の割拠性を克服するものとしても注目を集めました。
この構想は当時の高橋是清蔵相が消極姿勢を示したこともありが流れますが、代わりに高橋が打ち出したのは農商務省を農林・商工省に分割し、商工省に調査機関を置くというものでした。
高橋は参謀本部や文部省の廃止といった急進的な政策も打ち出していくことになりますが、基本的には国務大臣の行う事務を効率化しつつ、国務大臣のリーダーシップによって各省の割拠性を克服していくことを考えていました。
護憲三派の加藤高明内閣では、農商務省の分離は実現しましたが、各省を横断した事務系統の統一的整理は行われませんでした。
政友会は行政整理によって事務官僚の専管事務を削減し、それに対する反発を「政党化」によって乗り切る考えで、そのためには文官任用令の改正も必要だと考えていましたが、憲政会は行政官僚の自律性を担保しながら政党優位の政治体制の構築を目指す考えであり、官僚の「政党化」とは距離をとっていました。
こうした憲政会のスタンスに同調するのが牧野らの宮中勢力になります。護憲三派内閣による過度な政党化はしないというスタンスは天皇・宮中からも支持され、これを逸脱しようとすればその動きは天皇・宮中から否定されることになります(後述するように田中義一内閣はこれに引っかかった)。
これについて、著者は次のように述べています。
この枠組みが、政党政治の崩壊を考えるうえでもきわめて重要なポイントになったことを強調するために、本書では「護憲三派体制」という概念を提起する。これは具体的には、政党内閣による責任内閣政治の遂行を基本的な理念としつつ、その統合手段として過度な「政党化」を用いないことを原則とする体制、と定義する。そして、これを調整する天皇・宮中によってそれは、憲政会の意図や政友会の妥協的意思から大きく乖離したものへと拡大していく。二大政党は、天皇・宮中の定める枠組みのなかでしか、「政党化」に基づく統合方針を取ることができなくなるのである。(131p)
この天皇・宮中の意思を示すのが、田中義一内閣における台湾総督府の人事です。
田中は朝鮮総督に自らと近い山梨半造、満鉄総裁には政友会切手の政策通である山本条太郎を、関東長官には政友会系の木下謙次郎を就任させるなど、植民地長官の「政党化」を進めました。
しかし、小川平吉が「台湾は云々の事情あり、動かし難し」(145p)と書くように、天皇の意思によって台湾総督の人事は封じられていました。
1927年6月の段階で、天皇は牧野を呼び寄せ、田中内閣の地方長官の大更迭、事務次官人事への介入に懸念を示していました。さらに上山満之進台湾総督について、憲政会系だからといって交代させようとする動きがあることについて具体名をあげて田中に対して釘を差しました。
天皇は政友会の植民地の「政党化」を目指す動きを否定したのです。
また、天皇は田中内閣が目指した文官任用令の改正についても難色を示し、これを受けて牧野も「天皇の意思」を示して田中内閣に対抗する姿勢を示しました。結局、田中内閣は文官任用令の改正を断念します。
この植民地人事に対する昭和天皇の介入は浜口内閣でも行われ、朝鮮総督に文官の伊沢多喜男を就任させようとした人事に対して天皇・宮中はこの党派性の高い人事を嫌い、斎藤実の再登板に落ち着いています。
第2章のあとの置かれた補論では台湾統治をめぐる問題が論じられています。原敬は「内地延長主義」を掲げて文官の田健治郎を就任させますが、原の「内地延長主義」+「政党化」に対して田は「政党化」については抵抗する姿勢を示しており、両者は連携しつつもその思惑は違ったといいます。
さらにその後の台湾統治の問題も論じていますが、詳しくを本書をお読みください。
第3章では田中義一内閣における拓務省の設置構想がとり上げられています。
拓務省の設置は満蒙問題に対する田中内閣の積極姿勢の現れとして捉えられることが多いかもしれませんが、ここでは「政党化」されていなかった外務省への朝鮮という形で改めてこの拓務省の構想を検討しています。
満州では、外務省の出先機関である奉天総領事館、満鉄、関東庁、関東軍、さらに朝鮮総督府が分立していました。
政友会はこの問題を解決する方法として「政党化」を持ち出すわけですが、ここで「政党化」が難しかったのが高等文官試験で試験科目が独立するなど高度な専門性が求められ、党派的人事が及びにくい外務省でした。実際、原内閣でも外相は陸相や海相とともに政友会の党員ではない内田康哉が就任しています。
田中内閣はこうした外務省のあり方にくさびを打ち込もうとしたのです。
田中内閣には朝鮮、台湾といった植民地と密接な関わりを持つ満蒙、シベリア、南洋地方へ進出しようとする構想がありましたが、外務省や領事はこうした動きに基本的には冷淡で、それも不満となっていました(シャム公使館から帰国した有田八郎は経済活動に冷淡な外務省の姿勢を批判している)。
また、満州に関しても、在満朝鮮人問題の解決や経済的な進出に消極的な外務省に対する不満がありました(ただし、ここでも外務省の本省と満州駐在領事官の間にはその姿勢に違いがある)。
そこで構想されたのが「拓殖省」です(「拓務省」として実現するが、当初の名前は拓殖省だった)。
植民地や満州、南洋における機動的な経済開発を実現するためには領事館の機能を拡大するという方策もありますが、外務省という政党の力が及ばない組織の統制下にある領事の機能を高めることはさらなる割拠化をもたらすおそれがあります。
そこで外務省を迂回して経済開発を行い、外務省の自律性を弱める狙いも持ったものが拓殖省の構想でした。
基本的に田中外交は「失敗」の烙印を押されることが多いですし、著者もその拙劣さを認めていますが、自ら外相を兼任し、満鉄総裁の山本条太郎に張作霖との交渉を行わせるなど、田中には一貫して外務省の自立性を抑えて外交を展開しようとする意図がありました。
そして、拓殖省の設立によって、本土と植民地と満蒙や南洋を含んだ一貫した政策を展開し、政友会の方針である「産業立国」を実現しようとしたのです。
さらに朝鮮総督に任命した山梨半造に関しても、田中は山梨を閣議に出席させて朝鮮統治方針の指示を与えており、総督を首相に従属させ、朝鮮総督府の自立性を弱めようとしていました。
しかし、田中内閣の拓殖省構想は頓挫します。外務省から猛反発を受けたのに加えて、田中が初の男子普選となった1928年2月の第16回衆議院議員総選挙で絶対多数を確保することができず、政友会の内部が深刻な分裂状態となり、さらにそれを契機に田中の陸軍への影響力も急速に衰えていったからです。
加えて、山本条太郎満鉄総裁を通じた張作霖との協調路線が張作霖爆殺事件で瓦解します。
他にも、前朝鮮総督であった斎藤実が朝鮮を他の植民地と同列に扱うことに異議を唱え、拓殖省官制から朝鮮を外すように要請します。そして、これがきっかけに朝鮮総督府の官僚や朝鮮「親日派」からも批判の声が上がります(斎藤が朝鮮を他の植民地と同列に扱うことを批判したのに対して、朝鮮「親日派」は朝鮮を植民地扱いすることを批判した)。
こうした反対を受けて拓殖省の構想は次第に骨抜きになっていき、当初の構想からずいぶん後退した形で「拓務省」として設立されることになります。
結局、拓務省は植民地の利害を代弁するような存在になり、植民地の割拠性を強めるような形になってしまうのです。
第4章では浜口内閣〜第2次若槻内閣の扱っています。
浜口内閣は田中内閣の東亜h的な人事が「党弊」との批判を受けたことから、慎重に人事を進めますが、朝鮮総督に民政党と近い伊沢多喜男を就任させ、文官総督を実現しようとしました。しかし、先述のようにこの人事は昭和天皇の意思の前に挫折し、斎藤実が朝鮮総督に就任します。
拓務省については廃止も考えていた浜口内閣ですが、こうなると拓務省を通じて植民地をコントロースする必要も出てくることになり、拓務省は植民地と内閣の間の調整機能を担う形に落ち着きます。
産業立国主義のもとで積極財政を掲げた田中内閣では各省大臣の「予算分捕」の状況を発生させることとなりましたが、浜口内閣では井上準之助蔵相のもとで厳しい緊縮政策が行われました。
ただし、民政党は政友会と違って行政整理には熱心ではなく、補助金の整理などによってこれを進めようとしました。
また、この緊縮財政政策は各省の割拠性を乗り越えるための統合機能も果たしました。緊縮財政と産業の合理化によって国際貸借を改善するという政策体系のもとで各大臣は各省の行政長官ではなく、内閣の一員として振る舞わせようとしました。
政策の中心軸は井上準之助の大蔵省と幣原喜重郎の外務省にあったとされていますが。本書ではさらに商工省の政策立案能力の活用にも注目しています。
しかし、この政策は世界恐慌によって動揺します。民政党の内部からも積極財政を求める声が起こり、政策による統合は困難になってきます。
さらに強いリーダーシップをもった浜口首相が退陣することで、この方法は行き詰まりました。第2次若槻内閣は無任所大臣の設置などによって割拠性を克服しようと考えますが、有効な手を打てないままに退陣しました。
第5章は犬養毅内閣を扱っています。
犬養内閣は国策審議会の設置を計画していました。これは高橋是清蔵相と与党の意見調整を行う場という位置づけだったとされていますが、五・一五事件のため実現せずに終わっています。
先述のように積極財政を掲げた田中内閣のもとでは各省の予算要求が熾烈になり、各省の割拠性が浮き彫りになりました。
山本条太郎もこのような、各省が省益にとらわれて予算を要求し、「それを「撃退」することを自己の任務と考える大蔵省の姿勢を問題視」(371p)していました。
山本はこの時期、田中内閣を挫折を踏まえて「政務と事務の区別」を前提としつつ、無任所大臣の活用などを通じて、各省の利益を超えたところでの政策形成を模索するようになります。
犬養も山本を無任所大臣として入閣させようとしますが、これは枢密院の反対で立ち往生しました。
構想としては、国策審議会を設置するとともに、それを山本に仕切らせることで、行政長官化した大臣たちを抑えて政策の統合性を確保しようとするものでしたが、五・一五事件によってこれが実現することはありませんでした。
つづく斎藤実内閣では、「政民連携」の動きも起こり、「護憲三派」を思わせる「挙国一致」のムードも強まります。
斎藤内閣は事務官身分保障の制度化を実現します。これは昭和天皇と牧野内大臣が斎藤内閣の選定時に「事務官と政務官の区別を明かにし、振粛を実行すべき」(385p)との要請を受けてのものであり、これによって「政党化」を軸にした統合手段は現実的にほぼ不可能になりました。
これ以降、事務官の自立化が顕著になり、「新官僚」の台頭を招くことになります。
斎藤内閣は新しい組織をつくるのではなく、斎藤首相ー高橋是清蔵相ー山本達雄内相の長老政治家による連携によって割拠性を乗り越えようとし、これはかなりの成果を収めました。
高橋は新組織ではなく、五相会議のようなインナーキャビネット方式を採用し、ここで荒木貞夫陸相の意見をかなり抑えることに成功しています。
しかし、この斎藤内閣の成功は「憲政常道」復帰のタイミングを失わせることにもなりました。
また、長老政治家の個人的人格に依拠した政治は、藩閥時代の寡頭政治への回帰とも捉えることができ、政党の力で各省の割拠性を克服するという政党内閣のあり方からますます乖離するものでした。
そして、この個人の人格に頼った政治は二・二六事件で高橋と斎藤を失うことによって崩壊することになります。
高橋蔵相と大蔵省を中心とした統合の体系は民政党の今までの路線と親和的であり、政友会の「政党化」路線とは大きく違ったものでした。また、斎藤内閣が行政整理に消極的だったことも政友会には不満でした。
そこで政友会は斎藤内閣の挙国一致体制から離脱することになります。議会多数派であった政友会は自らを中心とする政権を志向することになるのです。
本書では清水銀蔵というあまり知られていな政友会所属の政治家の考えが紹介されていますが、そこでは内閣はすべて無任所大臣で構成すべきという議論がなされています。「かつての太政官制へと回帰するような発想」と評されていますが、まさしく割拠性を否定するための先祖返りという感じです。
政友会は岡田内閣成立とともに野党の立場になり、岡田内閣を「官僚内閣」として批判していくことになります。
著者は推測だとしながらも、清水は議会ではなく政党こそが民意を反映する機関だと考えていたといいます。政友会の横田千之助はムッソリーニの「民衆主義」を支持していたといいますし、ここに政友会がファシズムに接近する流れが見えてきます。
最初に書いたように、本書は大正〜昭和の戦前期の日本の政治についての知識がないと面白く感じられないかもしれませんが、一定の知識がある人にとっては今までとは違った視点を教えてくれる本で興味深いと思います。
特に田中義一内閣については、今まで良いイメージがまったくなかったのですが、本書を読んで結果はともかくとして、田中と政友会の意図については見えてきたものがあると思います。
また、昭和天皇と牧野伸顕が満州某重大事件で田中にとどめを刺しただけでなく、その他の面でも政党の行動にかなり強力な枠をはめていたことが印象的でした。
おそらく昭和天皇は当時としては「リベラル」な思想の持ち主だったのでしょうが、党派性を党派性で抑え込むマディソン的な考えについてはほぼ理解がなく、斎藤実のような立派な人格者による統治をよしとしたんでしょうね。
このあたりの昭和天皇や宮中をめぐる議論も刺激的です。
博士論文をもとにした本ですが、さまざまな論点を含んだスケール感のある面白い本ですね。